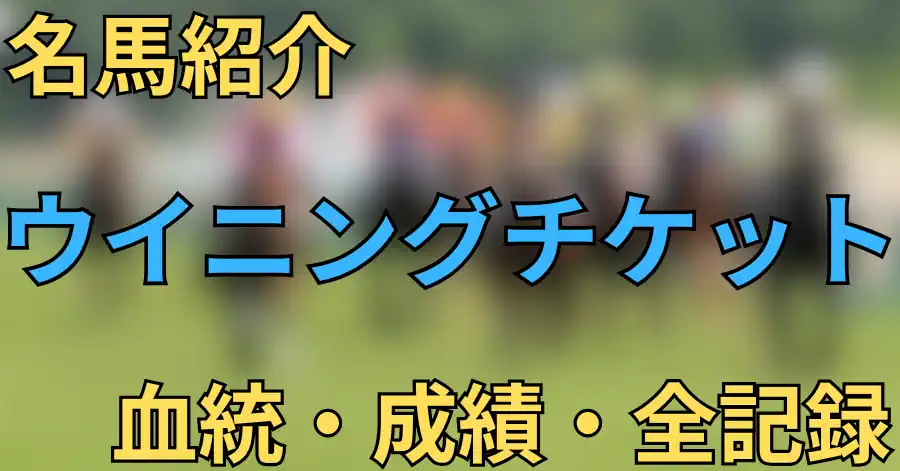ウイニングチケットとは?【競走馬プロフィール】
ウイニングチケットは1993年の東京優駿(日本ダービー)を制し、名手・柴田政人騎手に悲願のタイトルを届けた名馬です。
同世代のビワハヤヒデ、ナリタタイシンと三強を形成し、いわゆるBNW世代の中心としてクラシックを沸かせました。
父は凱旋門賞馬トニービン、母パワフルレディ、母父マルゼンスキーの配合で、府中2400mで真価を示す持続力と機動力を兼備しました。
通算14戦6勝、主な勝ち鞍は弥生賞、京都新聞杯、そして日本ダービーで、古馬になってからもジャパンカップ3着など一線級を相手に存在感を示しました。
血統の魅力、三強の物語性、そして“マサトコール”が鳴り響いたラスト100mの熱量まで、競馬史に刻まれる濃密なキャリアでした。
府中の長い直線で見せた再加速、コーナーでの減速幅の少なさ、道悪でも崩れないフォーム効率が総合力の核でした。
勝ち切るための戦術を自ら選び取れる自在性も併せ持ち、展開の罠に掛かりにくい“勝ち筋の再現性”で頂点に立った稀有なタイプでした。
| 生年月日 | 1990年3月21日 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牡・黒鹿毛 |
| 生産 | 藤原牧場(北海道・静内町) |
| 調教師 | 伊藤雄二/栗東 |
| 馬主 | 太田美實 |
| 通算成績 | 14戦6勝 |
| 主な勝ち鞍 | 東京優駿(1993年G1)、弥生賞(1993年G2)、京都新聞杯(1993年G2)、ホープフルS(1992年OP) |
| 父 | トニービン |
| 母 | パワフルレディ(母父:マルゼンスキー) |
目次
本記事では血統背景、デビューまでの歩み、主要重賞を含む競走成績の推移、名レースBEST5、同世代比較、競走スタイル、引退後の歩みを順に解説します。
各章は句点ごとに改行し、重要語句は赤マーカーで強調し、馬名は青マーカーで示します。
必要に応じて目次から各章へ移動し、知りたいトピックをピンポイントでご覧ください。
- ウイニングチケットの血統背景と特徴
- ウイニングチケットのデビューまでの歩み
- ウイニングチケットの競走成績とレース内容の詳細
- ウイニングチケットの名レースBEST5
- ウイニングチケットの同世代・ライバルとの比較
- ウイニングチケットの競走スタイルと得意条件
- ウイニングチケットの引退後の活動と功績
- ウイニングチケットのよくある質問(FAQ)
- ウイニングチケットの成績表
- ウイニングチケットのまとめ
ウイニングチケットの血統背景と特徴
ウイニングチケットは父トニービン、母パワフルレディ、母父マルゼンスキーという、欧州的な底力と日本的な瞬発力が交差する配合から生まれました。
父由来のロングストライドと心肺容量は直線の長い府中で威力を発揮し、母系の柔らかさがコーナーでの減速幅を最小化して機動力を担保しました。
この組み合わせは道中でラップを落とさずに巡航し、ゴールまで脚色を鈍らせないロングスパートの再現性を高めます。
一方で瞬時の加速にも優れ、直線坂上でのひと伸びという瞬発力の要求にも応えられる二刀流の資質が備わっていました。
同世代のビワハヤヒデやナリタタイシンのような特化型と比べ、総合力で勝ち切る“万能中距離型”として完成度の高いバランスを示した点が最大の特徴でした。
血統表に刻まれた“欧×日”の調和は、前半で無理をせず中盤からじわりと上げる競走設計を可能にし、ペースが極端でも崩れにくい耐性を与えました。
加えて頭頸が高くならず背中が沈まないフォームの美しさが、長い直線での姿勢維持に直結し、最後の100mでの再加速を支えました。
ウイニングチケットの父馬・母馬の戦績と特徴
父トニービンは欧州最強クラスの実績を持つスタミナ型で、日本では芝中距離で持続力を伝える名種牡馬として確立しました。
その産駒に共通するのは、直線での持続加速とフォーム効率の高さで、迷いなくスピードに乗れる点です。
母パワフルレディは名牝スターロッチ一族に連なる牝系に属し、母父マルゼンスキーの伸びやかなスピードを介して、道中のリズムを崩さない機敏さを子へ伝えました。
この“欧州的基礎体力×日本的瞬発”の合成が、府中2400mの高負荷区間でもフォームが乱れない耐性を生み、最後の数完歩まで推進力を持続させる設計を可能にしました。
近親に中距離で堅実に走るタイプが多いことも、持続力の強度を裏付ける材料で、配合段階から“ダービー適性”を内包していたと言えます。
結果として、機動戦・持続戦・瞬発戦のいずれでも“勝ち筋を作れる”血統的器用さが実戦で顕在化しました。
ウイニングチケットの血統から見る適性距離と馬場
ベストは1800~2400mで、特に府中・外回りのように直線が長くコーナー半径が大きいコースでパフォーマンスが最大化します。
先行勢の失速を待たず、自ら中盤からペースアップして持続戦に持ち込むのが理想で、坂上での再加速にも強みがあります。
馬場は良~稍重で安定し、重~不良でもストライドを保てるため大崩れは少なく、事実として不良実績のある道悪適性も示しました。
ワンターンのマイルではトップスピードの持続がやや短くなる一方、内回りの機動戦でもコーナーで減速しにくいため対応可能で、舞台適性の幅が広い万能型でした。
総じて“長く脚を使えるかどうか”が勝敗の分水嶺であり、本馬はその条件を高い確率で満たせる設計でした。
環境変化への耐性も高く、遠征や連戦でもパフォーマンスが大きくブレない“頑健さ”がキャリア全体の安定感を支えました。
ウイニングチケットのデビューまでの歩み
幼少期から背中の柔らかさと後肢の伸びが目立ち、歩様の上下動が少ない“効率の良いフォーム”を備えていました。
育成では長めキャンターで心肺を鍛え、坂路では終い重点のビルドアップでロングスパートの型を身体に刻みました。
気性は前向きかつ素直で、並ばれてからもうひと伸びする勝負根性が早くから芽生え、調教の意図を実戦で再現できる“競走知能”が高かった点も特筆されます。
環境への適応力が高く、遠征や滞在競馬でもコンディションを落とさず、函館での2戦目から一気に連勝街道へ乗りました。
その素地が、年末のオープン勝ちから春のトライアル制覇、そして本番の栄冠へと連なる“濃密なキャリア”を支えました。
負荷を上げても反動の少ない体質が、ハードトレーニングの継続を可能とし、冬場でもパフォーマンスを落とさない“季節耐性”を養いました。
ウイニングチケットの幼少期から育成牧場での様子
放牧地では大きく伸びるストライドで一定リズムを保ち、運動後の回復が早い“息の強さ”が光りました。
育成段階からコーナーワークの練習を重ね、遠心力を推進力に変えるハンドリングを徹底したことで、レースでは3~4角で自然にギアが入る型が確立しました。
基礎期には左右の手前替えを滑らかにするドリルを継続し、直線入り口での姿勢維持と加速の再現性を向上させました。
精神面は落ち着きがあり、馬群でも怯まず、自ら動いて勝ちに行ける前向きさが強みとなりました。
心身の成熟が早く、2歳秋には既にOP級のパフォーマンスを示せる下地が整っていたことが、実戦での連勝につながりました。
日々の調整で“無理に速くしない”哲学を貫き、終い重点で質を上げる積み上げが本番での再現性を担保しました。
ウイニングチケットの調教師との出会いとデビュー前の評価
伊藤雄二調教師は早期から“中距離で真価を発揮する万能型”と評価し、終い重点の時計を安定させる調整で完成度を引き上げました。
デビューは函館の短距離で5着に敗れたものの、続く1700m戦で一変し楽勝。
中山へ移ってからは葉牡丹賞、ホープフルSと連勝し、コーナーから動く戦術の有効性が明確になりました。
年明けは直行で弥生賞へ向かい、道中で脚を溜めて3角から加速、直線で余力十分に抜け出す理想形で快勝しました。
この時点で“ダービーの最有力”と見なされ、本番に向けて精度を上げるステップが整いました。
併せ馬では常に手応え優勢で、実戦さながらのロングスパートを敢行しても最後までラップを落とさない完成度をスタッフが高く評価していました。
ウイニングチケットの競走成績とレース内容の詳細
2歳秋の函館で片鱗を見せ、年末には中山2000mでホープフルSを制覇。
春の弥生賞で直線坂上のひと伸びを見せて本命に躍り出ると、皐月賞は位置取りの差で4着に敗れたものの、内容は悲観のないものでした。
迎えた東京優駿では中盤からジワっと位置を上げ、直線早め先頭から最後は内のビワハヤヒデ、外のナリタタイシンの猛追を凌ぎ切る堂々の完勝でした。
秋は京都新聞杯で復帰し快勝、続く菊花賞3着、世界の強豪が揃ったジャパンカップでも3着と健闘し、古馬混合の一線級でも互角以上に戦える地力を示しました。
翌年は距離や展開の幅に挑みながら、春夏秋のビッグレースで存在感を放ち、世代の象徴として記憶されるキャリアを全うしました。
特筆すべきは強い相手に対しても“自分の型”を崩さず、コーナーから動く王道で高い再現性を維持した点で、これは血統と育成の成果がレースで結実した証左でした。
ウイニングチケットの新馬戦での走りとその後の成長
デビュー戦の函館1200mは不良馬場でスプリント適性を測る試金石となり、5着と敗れながらも追走力と根性を示しました。
続く函館1700mでは距離延長でフォーム効率が生き、直線入り口で先頭に並びかけると持続加速で突き放し、以後の勝ち筋が具体化しました。
中山に移っての葉牡丹賞は折り合い重視から3~4角で手前を替えてロスなく進出、直線で再加速して抜け出す理想解。
年末のホープフルSでも同型を完封し、操作性と再現性の高さが証明されました。
この連勝の流れが、翌春のトライアル勝利と本番制覇へとつながる“勝ち方の型”を完成させました。
若駒らしからぬ折り合いの良さと、並ばれてからの闘争心の両立は、世代の一番を争う基準を早期に満たしていました。
ウイニングチケットの主要重賞での戦績と印象的な勝利
象徴的なのは弥生賞と東京優駿、そして秋の京都新聞杯です。
弥生賞は道中ためて3角からの進出で手応え良く抜け出し、最後はナリタタイシンを寄せ付けない完勝でした。
東京優駿は直線早めに先頭へ押し上げる王道の勝ち方で、ゴール前はビワハヤヒデ、ナリタタイシンとの壮絶な叩き合いを制して世代の頂点に立ちました。
復帰戦の京都新聞杯は余力残しの完勝で、立ち回りの自在性と反応の速さを改めて示しました。
また、強豪古馬と対戦したジャパンカップ3着は国際G1級の地力を証明する価値ある一戦で、世界基準の2400m適性を裏付けました。
いずれの重賞でも“直線入り口で主導権”という共通項があり、仕掛けどころの明確さが内容の強度を引き上げました。
ウイニングチケットの敗戦から学んだ課題と改善点
皐月賞4着では位置取りと仕掛けのタイミングが僅かに噛み合わず、直線の進路選択も影響して末脚を余しました。
その反省を踏まえた東京優駿では、コーナーでの進出開始を半馬身早め、直線入り口で主導権を握るプランへ修正して完勝につなげました。
秋の長距離菊花賞では持続力の高さで3着を確保した一方、3000m超でのギアチェンジ回数の多さが課題として残りました。
古馬戦では超一線級に対しても通用した反面、道中のメリハリが強いとトップスピードの滞在時間が短くなる弱点が露呈し、以後はポジションの先取りで克服。
敗戦の要因を構造化して次走へ反映する姿勢が、キャリア全体の安定感を支えました。
結果として、負けからの学習が“勝ち筋のテンプレート”をさらに洗練させ、以降のビッグレースでの安定した上位争いに直結しました。
ウイニングチケットの名レースBEST5
ウイニングチケットの名レース第5位:ホープフルS(1992年・中山芝2000m)
冬場の中山で行われたオープン特別を1番人気で快勝しました。
前半は折り合いを確認しつつ中団外で待機し、3~4角で手前替えとともに加速。
直線入り口で先頭圏に並びかけると、坂上でのひと伸びで後続を封じ、2歳時点での完成度とロングスパートの質を示しました。
翌春に向けての“勝ち方の型”が確立した意義深い一戦でした。
寒冷期でもフォームが崩れない体質の強さが可視化され、以後の中距離路線での安定感に直結しました。
ウイニングチケットの名レース第4位:京都新聞杯(1993年・G2)
ダービー後の復帰戦を単勝1.2倍の支持で迎え、余裕の手応えのまま2:13.3で完勝しました。
向正面からペースが上がる中でもフォームが崩れず、3角手前でスッと進出する機動力を披露。
直線では内のロスを避けるコース取りで持続戦に持ち込み、最後は着差以上の余裕を感じさせました。
秋戦線へ向けて“コンディションの良さと戦術の幅”を再確認できたレースでした。
相手強化のステップとしても理想的で、以後のG1でも上位争いの土台となりました。
ウイニングチケットの名レース第3位:ジャパンカップ(1993年・G1)
強豪古馬と海外勢が揃う国際G1で3着に好走しました。
中盤で位置を押し上げて直線に向くと、坂上でも脚色が鈍らず、勝ち馬レガシーワールドに迫る内容。
自身のベスト条件である府中2400mで、世界基準でも通用する巡航力と底力を証明しました。
世代限定戦を超えた価値を示す“地力の実証”として高く評価できます。
ペース変化の激しい国際戦での適応力は、万能型としての本質を改めて裏付けました。
ウイニングチケットの名レース第2位:弥生賞(1993年・G2)
トライアルで堂々の1番人気に応え、2:00.1の好時計で快勝しました。
道中は折り合いを優先し、3角からの段階的加速で先頭に取り付き、直線は手応え十分に抜け出しました。
後方から追い込むナリタタイシンを寄せ付けず、本番適性を前哨戦で証明した一戦でした。
“コーナーから動く”という本馬の戦術が、最高の形で可視化されたレースでもあります。
この勝利が皐月賞・ダービーの両本番での自信と選択肢の広さに繋がりました。
ウイニングチケットの名レース第1位:東京優駿(1993年・G1)
直線早めに主導権を握り、最後はビワハヤヒデ、ナリタタイシンの猛追を凌いで栄冠に到達しました。
ラスト100mで一段ギアを上げる再加速が光り、鞍上・柴田政人騎手の渾身の右ムチに応えてもうひと伸び。
“人馬の物語性”も含め、日本ダービーという舞台で総合力を極限まで引き出した象徴的な勝利でした。
以後も府中2400mがベストであることを印象づける決定的なパフォーマンスでした。
道中のロスを最小化しながら直線の入り口で主導権を握る、教科書的とも言える勝ち方でした。
ウイニングチケットの同世代・ライバルとの比較
同世代の核は三強と称されたビワハヤヒデ、ナリタタイシン、そしてウイニングチケットでした。
それぞれが菊花賞、皐月賞、日本ダービーを分け合い、能力の方向性が異なる三者三様の強さを見せました。
本馬は持続力と機動力のバランスに優れ、位置取りの柔軟性で“展開の罠”を回避できる点が強みでした。
古馬混合の舞台でもトウカイテイオー、ナイスネイチャ、ネーハイシーザーらと互角以上に渡り合い、世代代表の看板にふさわしい総合力を示しました。
三強の物語性と合わせ、競馬ファンの記憶に残る“時代の象徴”として語り継がれています。
序列がレースごとに入れ替わる緊張感が世代の評価を押し上げ、その中心で“府中の覇者”として存在感を放ち続けました。
ウイニングチケットの世代トップクラスとの直接対決
皐月賞ではナリタタイシンの決め手に屈して4着でしたが、反省を生かした東京優駿で三強対決に決着を付けました。
秋の菊花賞ではスタミナの怪物ビワハヤヒデに軍配が上がったものの、3着を確保して世代上位の地力を再確認。
続くジャパンカップでは古馬相手に3着と善戦し、三強の一角としての存在価値を国際舞台で示しました。
直接対決の通算で見れば勝ち負けは分け合いましたが、府中2400mという“自分の土俵”で最高点を出せたことが評価の核にあります。
すなわち“条件が整えば取り切る”という勝負勘の高さが、三強内での優位を確立した要因でした。
ウイニングチケットのライバルが競走成績に与えた影響
三強の存在は、陣営に“展開待ちではなく自ら動いて勝つ”という指針を植え付けました。
早め進出で主導権を握るレースを基本形としたことで、スローペースや外差し一辺倒に依存しない勝ち筋が確立しました。
その結果、府中2400mのようなハイレベルな舞台でも勝ち筋の再現性が高まり、取りこぼしを最小化できました。
強敵が水準を引き上げたからこそ、本馬の設計図がより洗練され、名馬の座へと到達したと言えます。
ライバルがもたらした緊張感は、キャリア全体の品質を押し上げた好循環でした。
そしてその経験値は、古馬戦線での安定感へと昇華されました。
ウイニングチケットの競走スタイルと得意条件
理想は序盤で無理をせず好位~中団で折り合い、3~4角で段階的にスピードを引き上げ、直線入り口で先頭圏に入る運びです。
トップスピードへの到達が速く、その速度を長く保てるため、短い直線でも差し切り、長い直線でも押し切りが可能でした。
内回りの機動戦でもコーナーで減速幅が小さく、外回りの持続戦でもバテず、舞台適性の幅が広いのが強みです。
枠は内外を問わず、ペースが落ち着けば自ら仕掛けて主導権を握れるため、展開依存が少ない点も安定感を生みました。
総合力を武器に“勝ち筋を自ら作る”スタイルが本質で、これがダービー制覇の決め手となりました。
道悪でもストライドが詰まりにくく、馬場悪化時にパフォーマンスを大きく落とさない点も強みでした。
ウイニングチケットのレース展開でのポジション取り
ゲートは五分に出て二完歩目で好位の外を確保し、道中は自らリズムを刻んで消耗を抑えるのが基本です。
3角手前で手前を替えると同時に進出を開始し、コーナーの遠心力を推進力に変換して直線入口で先頭圏へ。
直線では追い出しを渋り過ぎず、坂上で再加速を引き出してゴールまで押し切ります。
包まれるリスクが高ければ早めに外へ出してロスを最小化し、先に出て粘るか差し切るかの二択を持てるのが勝ち筋の核でした。
このテンプレートがどの条件でも再現できたことが、高い連対率と安定感につながりました。
位置取りに幅があるため、相手関係に応じて“受ける・作る”を切り替えられるのも武器でした。
ウイニングチケットの得意な距離・馬場・季節傾向
距離は1800~2400mが最もパフォーマンスが高く、府中2400mで天井値を示しました。
馬場は良~稍重で安定し、重でもストライドが詰まりにくいので大きな割引は不要です。
季節は春から初夏にかけてのパフォーマンスが特に良好で、秋は叩きつつ上げるローテで精度が高まりました。
総合して、舞台・展開・季節の変化に対して頑健な“万能中距離型”として評価できます。
高温多湿の夏場でもコンディションを大きく崩さず、輸送にも強い点がキャリアの安定感を後押ししました。
ウイニングチケットの引退後の活動と功績
引退後は種牡馬として繋養され、母系に欧州的スタミナと日本的スピードのバランスを補う血として活躍しました。
産駒全体としては大勢力とはならなかったものの、持続力と操縦性の高さを伝え、芝中距離で堅実に走るタイプを多く送りました。
母の父としてもフォーム効率や折り合いの良さを補強する血として評価され、配合面での存在感を長く示しました。
功労馬として余生を送り、多くのファンに愛され続けたのも本馬ならではの資質で、競馬の“物語性”を次世代へ橋渡ししました。
ダービー馬としての象徴性は時間の経過とともに増し、世代の記憶装置として語り継がれています。
ウイニングチケットの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
種牡馬としては中距離の芝で持続力を生かす配合が好相性で、母系にスピードを補うとポテンシャルが顕在化しました。
BMSとしては前向きさとフォームの美しさを付与する傾向が見られ、実戦での操縦性向上に寄与しました。
大種牡馬のようなG1量産こそ叶わなかったものの、“走りの質”を底上げする血として中長期的な価値を提供しました。
血統表のどこに置いても働く汎用性は、実戦での万能型という現役時の姿をそのまま反映しています。
さらに功労馬としての活動や公開イベントを通じ、多くのファンが“ダービーの記憶”を直に共有できたことも、後世への財産となりました。
ウイニングチケットの産駒の活躍と後世への影響
産駒は芝中距離でコツコツと勝ち星を積み重ね、条件戦~オープンクラスでの堅実さが目立ちました。
大舞台での派手さより、配合相手次第でじわりと力を引き上げるタイプで、育成現場からの扱いやすさも高評価でした。
ブリーディング全体としては、欧州的スタミナと日本的スピードを調和させる“接着剤”として機能し、血の多様性を担保しました。
結果として、現代日本競馬の主流条件で戦ううえでの大切な要素を、形を変えて後世へと手渡しています。
“人馬の物語性”という無形資産もまた、次世代の競馬ファンへ伝播し続けています。
ウイニングチケットのよくある質問(FAQ)
Q. ウイニングチケットの代表的な勝ち鞍は何ですか?
A. 1993年の東京優駿(日本ダービー)が代表で、同年の弥生賞、京都新聞杯も制しています。
2歳時にはホープフルSを勝ち、年末年始にかけて完成度の高さを示しました。
いずれも“直線入り口で主導権”という勝ち方の共通項があり、再現性の高さが最大の武器でした。
Q. 三強“BNW”とは何を指しますか?
A. ビワハヤヒデ、ナリタタイシン、ウイニングチケットの頭文字で、1993年クラシック路線を席巻した三頭を指します。
それぞれが菊花賞、皐月賞、日本ダービーを分け合いました。
能力のベクトルが異なる三者が互いを高め合い、世代全体の水準を押し上げました。
Q. ダービー当日のレース運びのポイントは?
A. 道中で無理なくポジションを上げ、直線入口で主導権を取ったことが最大のポイントです。
内のビワハヤヒデ、外のナリタタイシンをねじ伏せたのは、坂上での再加速が効いたためです。
コーナーでの減速幅が小さく、直線の入口で既に優勢という“理想形”が実現しました。
Q. 古馬との対戦成績はどう評価できますか?
A. 秋のジャパンカップ3着、年末の有馬記念など強豪相手でも見劣らず、地力の高さを示しました。
特に府中の2400mでこそ真価が発揮されました。
国際G1でも通用する巡航力は、万能中距離型としての評価を不動のものにしました。
Q. どんな舞台が得意でしたか?
A. 直線の長いコースで中盤からの持続戦に持ち込むと最も強く、府中2400mがベストでした。
内回りの機動戦にも対応できる万能性も持っていました。
道悪でもストライドが詰まりにくく、コンディション不問の安定感が魅力でした。
ウイニングチケットの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/09/06 | 函館 | 新馬 | 7 | 5 | 柴田政人 | 芝1200 | 不良 | 1:16.4 |
| 1992/09/13 | 函館 | 新馬 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝1700 | 重 | 1:48.8 |
| 1992/12/06 | 中山 | 葉牡丹賞(500万下) | 2 | 1 | 田中勝春 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 |
| 1992/12/27 | 中山 | ホープフルS(OP) | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 |
| 1993/03/07 | 中山 | 弥生賞(G2) | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 |
| 1993/04/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 1 | 4 | 柴田政人 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 |
| 1993/05/30 | 東京 | 東京優駿(G1) | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 |
| 1993/10/17 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2200 | 良 | 2:13.3 |
| 1993/11/07 | 京都 | 菊花賞(G1) | 2 | 3 | 柴田政人 | 芝3000 | 良 | 3:05.7 |
| 1993/11/28 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 4 | 3 | 柴田政人 | 芝2400 | 良 | 2:24.6 |
| 1993/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 3 | 11 | 柴田政人 | 芝2500 | 良 | 2:32.6 |
| 1994/07/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 1 | 5 | 柴田善臣 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 |
| 1994/09/18 | 中山 | オールカマー(G3) | 2 | 2 | 武豊 | 芝2200 | 重 | 2:14.8 |
| 1994/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 2 | 8 | 武豊 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 |
ウイニングチケットのまとめ
ウイニングチケットは欧州的スタミナと日本的スピードの調和を体現し、東京優駿で世代の頂点に立った万能中距離型の名馬でした。
三強の一角として強敵に揉まれながらも、府中2400mで天井値を示し、古馬の強豪相手にも怯まない地力を証明しました。
血統・育成・戦術の三位一体で“勝ち筋を自ら作る”設計を確立し、競馬の物語性とともにファンの心に刻まれました。
その走りの哲学は血統面にも受け継がれ、今なおレース考察の指標として参照され続けています。
ダービー馬としての象徴性は時代を超えて輝き、BNW世代の記憶とともに語り継がれていくでしょう。