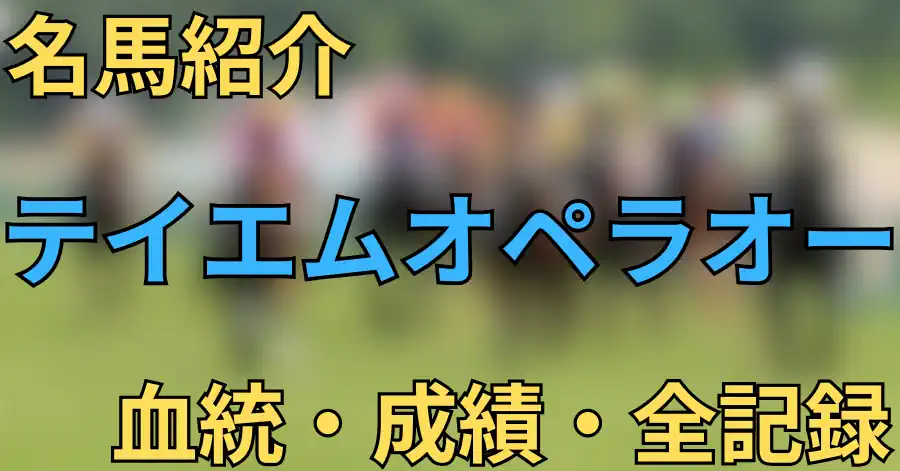\>
テイエムオペラオーとは?【競走馬プロフィール】
テイエムオペラオーは1999年の皐月賞馬で、2000年には春秋の天皇賞、宝塚記念、ジャパンC、有馬記念を総なめにして年間無敗を達成した世紀末覇王です。
父に欧州中距離の王者オペラハウス、母に米名牝系のワンスウエドを配した国際色豊かな配合で、機械のように止まらない巡航力と追われてからもう一段伸びる勝負根性を兼備しました。
主戦の和田竜二騎手と磨いたコーナー開始のロングスパートは再現性が極めて高く、馬場や展開が変わっても最後に必ず前へ出るのが最大の武器でした。
通算26戦14勝、重賞12勝(G1を7勝)、総獲得賞金は18億3518万9000円で当時の世界最高記録を樹立し、JRA顕彰馬として殿堂入りしています。
| 生年月日 | 1996/03/13 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牡・栗毛 |
| 生産 | 杵臼牧場(北海道浦河町) |
| 調教師 | 岩元市三/栗東 |
| 馬主 | 竹園正継 |
| 通算成績 | 26戦14勝 |
| 主な勝ち鞍 | 天皇賞(春)(G1)×2、天皇賞(秋)(G1)、宝塚記念(G1)、ジャパンC(G1)、有馬記念(G1)、皐月賞(G1) |
| 父 | オペラハウス |
| 母 | ワンスウエド(母父:Blushing Groom) |
目次
- 1 目次
- 2 テイエムオペラオーの血統背景と特徴
- 3 テイエムオペラオーのデビューまでの歩み
- 4 テイエムオペラオーの競走成績とレース内容の詳細
- 5 テイエムオペラオーの名レースBEST5
- 6 テイエムオペラオーの同世代・ライバルとの比較
- 7 テイエムオペラオーの競走スタイルと得意条件
- 8 テイエムオペラオーの引退後の活動と功績
- 9 テイエムオペラオーの2000年無敗シーズンの意義
- 10 テイエムオペラオーとメイショウドトウのライバル関係
- 11 テイエムオペラオーの配合特性と適性レンジ
- 12 テイエムオペラオーの戦術解剖:ロングスパートの作り方
- 13 テイエムオペラオーの敗戦分析とリカバリー戦略
- 14 テイエムオペラオーのよくある質問(FAQ)
- 15 テイエムオペラオーの成績表
- 16 テイエムオペラオーのまとめ
目次
本記事では血統背景、デビューまでの歩み、主要重賞を含む競走成績の推移、名レースBEST5、同世代比較、競走スタイル、引退後の歩みを順に解説します。
重要語句は赤マーカーで強調し、馬名は青マーカーで示します。
必要に応じて目次から各章へ移動し、知りたいトピックをピンポイントでご覧ください。
- テイエムオペラオーの血統背景と特徴
- テイエムオペラオーのデビューまでの歩み
- テイエムオペラオーの競走成績とレース内容の詳細
- テイエムオペラオーの名レースBEST5
- テイエムオペラオーの同世代・ライバルとの比較
- テイエムオペラオーの競走スタイルと得意条件
- テイエムオペラオーの引退後の活動と功績
- テイエムオペラオーの2000年無敗シーズンの意義
- テイエムオペラオーとメイショウドトウのライバル関係
- テイエムオペラオーの配合特性と適性レンジ
- テイエムオペラオーの戦術解剖:ロングスパートの作り方
- テイエムオペラオーの敗戦分析とリカバリー戦略
- テイエムオペラオーのよくある質問(FAQ)
- テイエムオペラオーの成績表
- テイエムオペラオーのまとめ
テイエムオペラオーの血統背景と特徴
父オペラハウスは英G1キングジョージの覇者で、しなやかな背中と無理なくスピードに乗る巡航性能を産駒へ強く伝える種牡馬です。
母ワンスウエドは米国の名牝系に連なる繁殖で、母父Blushing Groomの血は瞬時の反応と勝負根性を付与します。
この配合は欧州的な底持久力と米国的な反応速度を併せ持つハイブリッドで、直線入口の減速幅を最小化してからの再加速という勝ち筋を設計段階で内包していました。
胴にゆとりがあり肩の出が大きい体型はロングストライドに適し、コーナリングでも外へ張らず最短距離を辿れる重心設計が強みです。
仕上がりの早さとタフネスが共存し、間隔を詰めてもバテない回復力を示したため、連戦のG1でもパフォーマンスを落とさない持続力が武器になりました。
さらに血統面の普遍性が舞台適応の幅を広げ、良〜重まで極端な苦手条件を作らない再現性の高さに直結しています。
テイエムオペラオーの父馬・母馬の戦績と特徴
父オペラハウスは欧州の王道路線で磨かれた巡航速度の高さとフォームの効率性を伝える種牡馬で、スタミナの土台が厚いのが特徴です。
母ワンスウエドは現役戦績こそ目立たないものの、母父Blushing Groomを通じてスムーズな加速と闘争心を強化し、配合全体のバランスを整えています。
この組み合わせにより、序盤は我慢、3〜4角でビルドアップ、直線は持続という流れが自然に作れ、テイエムオペラオー本来の資質が引き出されました。
同世代のアドマイヤベガ、ナリタトップロード、古馬のグラスワンダー、以後に台頭するメイショウドトウら強豪と渡り合えた背景には、血統が生む総合値の高さがありました。
評価軸は名血、遺伝力、適応性で、どの局面でも破綻の少ない万能性が証明されています。
テイエムオペラオーの血統から見る適性距離と馬場
適性距離は2000〜2400が最適解で、3200の長距離でも質を落とさない稀有なタイプです。
ワンターンの東京でも、コーナー4回の中山・阪神でも直線入口での減速が小さく、最後の200で速度を一段上げられるのが強みでした。
ラップはミドル〜ハイの一貫ラップで真価を発揮し、道悪では跳びの大きさを生かしてストライドで粘る競馬が可能です。
季節面では春と秋の仕上がりが良好で、間隔を詰めてもバテない回復力が連戦の安定を支えました。
総合的に、舞台・馬場・展開に応じて勝ち筋を複数用意できる戦術幅が最大の武器でした。
テイエムオペラオーのデビューまでの歩み
幼少期から背腰の強さと前躯の可動域が際立ち、放牧地でも群れの中でスムーズに加速・減速ができるバランス感覚を示しました。
育成段階では直線主体のキャンターで心肺機能を養い、坂路では序盤我慢・終い重点のメニューでロングスパートの下地を構築しています。
ゲートは素直で二完歩目の出脚が良く、実戦で自然に好位〜中団を確保できるため、道中の消耗を抑えて直線での再加速につなげられました。
早期はダートで基礎体力を固め、すぐに芝へシフトしてゆきやなぎ賞、毎日杯を連勝し、クラシック路線の主役へ浮上しました。
皐月賞では後方外から長い脚で差し切り、持続と瞬発のハイブリッド性能を証明。
総合すると、完成度、回復力、機動力が早期から揃っており、以後の王道路線での安定に直結しています。
テイエムオペラオーの幼少期から育成牧場での様子
基礎付けの段階からトモの可動域が広く、踏み込みの深さが推進力へ直結していました。
直線ウッドで12〜13秒台を安定して刻む持続性能を育み、心拍の戻りが早い体質が連戦耐性を高めています。
コーナーワークでは外へ張らずに最短を通る感覚が早期に身につき、直線入口の減速を最小化する技術が形成されました。
育成後期は坂路でビルドアップし、ラスト200で『もう一段』伸びるフォームが完成。
精神面では馬群のプレッシャー下でも怯まない胆力が育ち、密集隊列でも狭いスペースへ入っていける性格的強みが作られました。
キーワードは基礎体力、直線持続、胆力です。
テイエムオペラオーの調教師との出会いとデビュー前の評価
岩元厩舎は週半ばの終い重点と週末の回復重視を軸に、過負荷を避けつつ瞬発のキレを磨く調整を実施しました。
助手やジョッキーの跨り感は『背中が柔らかい』『自分で前へ進む』で一致し、追ってから止まらない持続を高く評価しています。
ダート戦で基礎を固めてから芝重賞へ移行する柔軟なローテで、段階的に中距離の王道路線へシフトしました。
総じて、厩舎の調整力と馬の学習能力が噛み合い、デビュー前から高い完成度の土台が整っていました。
テイエムオペラオーの競走成績とレース内容の詳細
2歳は新馬2着で脚部を労りながらの始動でしたが、3歳冬〜春にダート未勝利→芝2000の条件→毎日杯→皐月賞と一気呵成の4連勝で主役に躍り出ました。
ダービー3着、菊花賞2着、有馬記念3着とG1で崩れない内容を重ね、翌2000年は京都記念から阪神大賞典、天皇賞(春)、宝塚記念、京都大賞典、天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念まで怒涛の8戦全勝。
2001年は産経大阪杯4着から天皇賞(春)で連覇、宝塚記念2着、秋は京都大賞典を勝って天皇賞(秋)2着、ジャパンC2着、有馬記念5着と最後まで下限値の高い走りを保ちました。
相手と舞台が変わっても崩れない再現性、コーナーから速度を上げ続けるロングスパート、直線入口での再加速がキャリアの核でした。
テイエムオペラオーの新馬戦での走りとその後の成長
京都芝1600の新馬は中団外で折り合い、直線で長いフットワークを見せて2着。
年明けダート1400で4着を挟み、ダート1800の未勝利で余力十分に初勝利。
芝2000のゆきやなぎ賞、毎日杯を連勝してクラシックの主役へと浮上し、皐月賞では後方外から差し切り勝ちを収めました。
この過程で『位置取りの柔軟性』『直線で減速しないフォーム』『狭いスペースを割る胆力』を同時に獲得し、以後の王道路線での安定につながっています。
キーワードは完成度、進路確保、直線持続です。
テイエムオペラオーの主要重賞での戦績と印象的な勝利
2000年は京都記念→阪神大賞典→天皇賞(春)→宝塚記念→京都大賞典→天皇賞(秋)→ジャパンC→有馬記念まで8連勝という史上級のシーズンでした。
天皇賞(秋)は重馬場の中で持久質のラップを先に動いてねじ伏せ、ジャパンCは好位から直線で抜け出す王道競馬。
有馬記念は内で脚を温存して馬群を割り、ゴール前はメイショウドトウを封じてフィニッシュ。
さらに春の天皇賞ではラスカルスズカを相手に持久力勝負を制し、秋の京都大賞典ではナリタトップロードに先着して基礎スピードの高さを再確認しました。
展開と馬場が変わっても勝ち切る勝負強さ、3〜4角で先んじて押し上げる機動力が同居していた点が特筆されます。
テイエムオペラオーの敗戦から学んだ課題と改善点
2001年産経大阪杯4着は外枠・展開不向き・進路確保の遅れが重なったもので、次走の天皇賞(春)では隊列の内で脚を温存し直線で解放して連覇を果たしました。
秋の天皇賞、ジャパンCの連続2着は相手の瞬発力が僅かに上回り、直線入口での位置取りとギアチェンジのタイミングが明暗を分けました。
しかし叩き台→本番の流れの精度を高め、隊列の中で『出口』を先に作る準備動作を徹底するなど、課題を要素分解して修正するプロセスが確立していました。
総じて、修正力と適応力が名馬の証であり、敗戦が次の勝利の伏線として機能していたと言えます。
テイエムオペラオーの名レースBEST5
テイエムオペラオーの名レース第5位:毎日杯(G3)
皐月賞前の試金石で、道中は内の最短を通ってロスを抑え、3〜4角でじわっと進出しました。
直線は外へ持ち出してから長い脚を使い切り、ゴールまで減速しない理想形を体現しています。
ミドルペースの一貫ラップを押し切ったことは、その後の王道路線での再現性の高さを予告する内容でした。
同世代のタガノブライアンらを相手に内容で上回り、立ち回りと底力のバランスが光りました。
完成度と進路確保の巧さが同居した指標的レースです。
テイエムオペラオーの名レース第4位:宝塚記念(G1)
3〜4角で早めに動いて前を射程に入れ、直線は内の狭いスペースを割って抜け出しました。
前後半がほぼイーブンの持久戦で、被されても怯まない胆力と、最後の200での再加速が勝因です。
同世代の強敵メイショウドトウとの攻防を制した意義は大きく、以後のロードマップに自信を与えました。
阪神内回りという機動力の要る舞台で王道競馬を完遂した価値は高く、接戦での勝負強さを可視化した一戦でした。
テイエムオペラオーの名レース第3位:天皇賞(春)(G1)
淀の3200は心肺とフォームの総合検定です。
序盤は折り合いに専念し、向こう正面からじわっとスピードを上げてスタミナを削る設計に移行。
4角出口では前との距離を一気に詰め、直線で長いフットワークを解放して押し切りました。
ラスカルスズカの粘りを上からねじ伏せた内容で、『早め進出→直線で止まらない』というロングスパートの完成形が映えています。
テイエムオペラオーの名レース第2位:天皇賞(秋)(G1)
重馬場で時計が掛かる持久質の一戦。
3角手前から動いて先頭へ並びかけ、直線は持続力でねじ伏せる堂々たる王道競馬でした。
瞬時の切れより総合値勝負になったことで、一貫ラップに強い資質が最大化。
メイショウドトウとのマッチレースを制し、秋の古馬王道路線の主役を確固にしました。
テイエムオペラオーの名レース第1位:ジャパンC(G1)
世界の一線級が集う舞台で、好位のインで脚を温存しながらロスを最小化。
直線で外へ持ち出してから長いフットワークで前を飲み込み、最後は堂々と抜け出しました。
国際標準の厳しいラップに対応し、相手と馬場を問わない普遍性と勝負強さを証明した象徴的な勝利です。
続く有馬記念まで勝ち切って年間無敗を完成させ、歴史的評価を決定づけました。
テイエムオペラオーの同世代・ライバルとの比較
1999年はアドマイヤベガ、ナリタトップロードとの『三強』でクラシックを牽引し、古馬ではグラスワンダー、翌年に掛けてはメイショウドトウが最強の好敵手でした。
テイエムオペラオーは展開と馬場への適応力が高く、誰が相手でも内容で互角以上に渡り合えるのが特長です。
ミドル〜ハイの一貫ラップで崩れない下限値が高く、着順以上に価値のある競馬を積み重ねました。
総合力と戦術の幅で比較しても、歴史的ハイレベルな相手関係の中で頭一つ抜けた存在と言えます。
テイエムオペラオーの世代トップクラスとの直接対決
皐月賞では差し切りでアドマイヤベガ、ナリタトップロードを撃破し、ダービー3着、菊花賞2着と年間を通して高い安定性を示しました。
古馬混合の王道路線では天皇賞(秋)やジャパンCで内容の濃い走りを連発し、メイショウドトウとのマッチレースを制して年間無敗を達成。
鍵は3〜4角での先んじた進出と直線での再加速で、相手の長所を相殺する戦い方で優位を築きました。
また京都大賞典ではナリタトップロード、有馬記念ではグラスワンダーら強豪とも真っ向勝負を展開し、対戦成績の質を高めています。
テイエムオペラオーのライバルが競走成績に与えた影響
メイショウドトウの持続力、アドマイヤベガの瞬発、ナリタトップロードのスタミナと機動力という明確な個性に対処する過程で、戦術の精度はさらに磨かれました。
厳しい相手と当たり続けた経験は精神面の安定にも寄与し、馬群を割る胆力と位置取りの柔軟性が強化。
この相互作用が2000年の年間8戦全勝へ直結し、翌年の春天連覇にも波及したと評価できます。
結果として、キャリア全体の価値を押し上げる相乗効果が生まれました。
テイエムオペラオーの競走スタイルと得意条件
基本形は道中で脚を温存し、3〜4角でビルドアップして外へ出し、直線はロスなくトップスピードへ乗せる戦い方です。
被されても怯まない胆力があり、馬群の狭いスペースを割るのが得意で、直線入口の減速幅が小さいためラスト200で再加速できます。
馬場は良〜稍重でブレが小さく、重でも大崩れしません。
距離は2000〜2400が最適で、3200の長距離でも質を落とさない稀有さが魅力です。
総合して、ロングスパート、進路確保、再現性が勝ち筋の核でした。
テイエムオペラオーのレース展開でのポジション取り
スタート直後は出脚の良さで無理せず好位〜中団を確保。
向こう正面で外3列目へスライドして加速の助走を取り、4角出口で手前替えと同時に外へ持ち出すと、減速せずトップスピードへ移行できます。
密集隊列では早めに『出口』を用意する意識が重要で、直線入口までに外1頭分のスペースを確保できれば最後の200でさらに伸びます。
こうした準備動作の質が接戦での勝負強さを生み、ゴール前で優位に働きました。
鍵語は位置取りとコース取りです。
テイエムオペラオーの得意な距離・馬場・季節傾向
ベストは2000〜2400で、3200でも対応可能という幅広さが魅力です。
春は仕上がりが早く、高速〜標準の時計域で安定し、夏は一息入れて秋に再ピークを作るサイクルが理想的でした。
秋は重〜良まで守備範囲が広く、直線で止まらないロングスパートが再現されます。
ターゲットの2〜3走前からビルドアップし、追い切りは終い重点で『減速しない直線入り』を体に覚え込ませるのが最適でした。
評価軸は距離適性と季節適性です。
テイエムオペラオーの引退後の活動と功績
種牡馬としては平地G1勝ちこそ出なかったものの、芝・ダート双方で堅実に勝ち上がる産駒を輩出し、ジャンプ競走でもタイトルホースを送り出しました。
母父としては背中の柔らかさと直線での『もう一段』を供給し、配合設計の幅を広げています。
キャリア全体が象徴するのは、相手と馬場を問わない普遍性と、準備と修正のプロセスで勝ち筋を作る再現性です。
顕彰馬選出にふさわしい実績と記録を残し、長期的な血統的影響も評価されています。
テイエムオペラオーの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
平地では短距離〜中距離に適性を見せる産駒が多く、交流重賞や地方の番組でタイトルを積み重ねました。
気性は前向きで調教耐性が高く、追ってから止まらない推進力を伝えるのが共通項です。
母父としては芝・ダートを問わず直線での再加速を底上げし、配合の自由度を広げています。
総じて、産駒の勝ち上がり率と耐久性に優れ、長期的に現場を支えるタイプの種牡馬でした。
テイエムオペラオーの産駒の活躍と後世への影響
JRA・地方を問わず堅実に勝ち星を重ね、ジャンプ路線でも活躍馬を送り出すなど、番組適応の幅広さで競馬全体の底上げに寄与しました。
母父としての価値は今後も維持・上昇が見込まれ、配合設計における選択肢を増やす存在であり続けるでしょう。
血の広がりという観点で、長期的な持続的影響が期待されます。
引退後の功績は数字以上に戦術・配合の両面で学びの多いケーススタディになっています。
テイエムオペラオーの2000年無敗シーズンの意義
2000年は京都記念→阪神大賞典→天皇賞(春)→宝塚記念→京都大賞典→天皇賞(秋)→ジャパンC→有馬記念を勝ち切り、年間8戦全勝という偉業を成し遂げました。
重・良・高速・持久いずれの条件でも崩れず、コーナーからのロングスパートと直線の再加速で常に主導権を握っています。
相手はメイショウドトウ、ナリタトップロード、古馬の強豪に海外勢まで加わる強力布陣。
それらを相手に内容でねじ伏せた普遍性は稀有で、日本競馬の標準を世界級へ押し上げたシーズンでした。
テイエムオペラオーとメイショウドトウのライバル関係
2000〜2001年にかけてのメイショウドトウとの攻防は、互いの特性を高め合う名ライバル関係でした。
持続力で圧すテイエムオペラオーに対し、相手は粘り強い先行からの押し切りが武器。
阪神内回りや中山では機動力が、東京や京都外回りでは直線の再加速が勝敗の分岐点となりました。
この拮抗が戦術の精度を研ぎ澄まし、結果として年間無敗、翌年の春天連覇という金字塔に結びついています。
テイエムオペラオーの配合特性と適性レンジ
オペラハウス×ワンスウエドの配合は、欧州型の巡航と米国型の反応を融合するもので、2000〜2400を頂点に3200まで対応する稀有なバランスを実現しました。
サンデー系や米国型パワー血統との組み合わせで直線の『もう一段』を強化でき、配合上の自由度の高さが産駒・母父成績の底上げに寄与しています。
まとめると、巡航持続と反応速度の両立がキーワードです。
テイエムオペラオーの戦術解剖:ロングスパートの作り方
勝ちパターンは『道中の消耗を抑える→3〜4角でギアを段階的に上げる→直線入口で減速しないまま加速を継続』という一連の流れに集約されます。
向こう正面で外3列目へスライドして進路と加速の助走を確保し、4角出口で手前替えと同時に外へ持ち出すことでロスを最小化しました。
直線では早めに前へ並びかけて心理的プレッシャーを与え、最後の200で再加速するのが理想形です。
この型は相手の切れ味を相殺し、持久力勝負へ誘導する効果があり、舞台・馬場を問わず高い再現性を誇りました。
テイエムオペラオーの敗戦分析とリカバリー戦略
敗戦時は外枠や隊列の外でロスを抱えたケース、直線入口での進路確保に数歩遅れたケースが多く、位置取りとコース取りの微差が結果へ直結しました。
産経大阪杯の次走である天皇賞(春)では、序盤で内のポケットを確保してロスを圧縮し、スタミナの消耗を抑えてから押し切る再現性を取り戻しています。
秋の連続2着後も京都大賞典を勝って基礎スピードを再確認し、ターゲット本番でのパフォーマンスを引き上げました。
つまり課題を要素分解し、次走で修正力と適応力を発揮する仕組みが確立していた点が名馬の証左でした。
テイエムオペラオーのよくある質問(FAQ)
Q. 主な勝ち鞍は?
A. 皐月賞(G1)、天皇賞(春)(G1)×2、宝塚記念(G1)、天皇賞(秋)(G1)、ジャパンC(G1)、有馬記念(G1)です。
2000年は年間8戦全勝でGI5勝を達成した歴史的シーズンでした。
Q. ベストの適性距離は?
A. ベストは2000〜2400で、3200でも質を落とさない距離適性を持ちます。
良〜稍重で再現性が高く、重でも大崩れしにくいのが特徴です。
Q. 代表的なライバルは?
A. メイショウドトウ、アドマイヤベガ、ナリタトップロードが代表格です。
特にメイショウドトウとは拮抗した名勝負が多く、戦術の精度を高める好敵手でした。
テイエムオペラオーの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/08/15 | 京都 | 3歳新馬 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝1600m | 良 | 1:36.7 |
| 1999/01/16 | 京都 | 4歳未勝利 | 2 | 4 | 和田竜二 | ダ1400m | 良 | 1:28.0 |
| 1999/02/06 | 京都 | 4歳未勝利 | 1 | 1 | 和田竜二 | ダ1800m | 良 | 1:55.6 |
| 1999/02/27 | 阪神 | ゆきやなぎ賞(4歳500万下) | 2 | 1 | 和田竜二 | 芝2000m | 稍重 | 2:05.3 |
| 1999/03/28 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2000m | 良 | 2:04.1 |
| 1999/04/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 5 | 1 | 和田竜二 | 芝2000m | 良 | 2:00.7 |
| 1999/06/06 | 東京 | 日本ダービー(G1) | 3 | 3 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:25.6 |
| 1999/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 3 | 3 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:24.4 |
| 1999/11/07 | 京都 | 菊花賞(G1) | 2 | 2 | 和田竜二 | 芝3000m | 良 | 3:07.7 |
| 1999/12/04 | 中山 | ステイヤーズS(G2) | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝3600m | 良 | 3:46.2 |
| 1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 5 | 3 | 和田竜二 | 芝2500m | 良 | 2:37.2 |
| 2000/02/20 | 京都 | 京都記念(G2) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200m | 良 | 2:13.8 |
| 2000/03/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3000m | 稍重 | 3:09.4 |
| 2000/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200m | 良 | 3:17.6 |
| 2000/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200m | 良 | 2:13.8 |
| 2000/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:26.0 |
| 2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2000m | 重 | 1:59.9 |
| 2000/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:26.1 |
| 2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2500m | 良 | 2:34.1 |
| 2001/04/01 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 1 | 4 | 和田竜二 | 芝2000m | 良 | 1:58.7 |
| 2001/04/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200m | 良 | 3:16.2 |
| 2001/06/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2200m | 良 | 2:11.9 |
| 2001/10/07 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:25.0 |
| 2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2000m | 重 | 2:02.2 |
| 2001/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2400m | 良 | 2:23.8 |
| 2001/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 1 | 5 | 和田竜二 | 芝2500m | 良 | 2:33.3 |
テイエムオペラオーのまとめ
名血のシナジーに裏打ちされた基礎性能と、敗戦を糧に戦術を磨き上げた修正力が融合し、2000年には年間無敗という金字塔を打ち立てました。
相手・馬場・展開を問わない普遍性と、3〜4角からのロングスパートという必勝形がキャリアの核です。
引退後も母父として直線の『もう一段』を伝え、配合と戦術設計の両面で今なお学ぶ点が多い指標的存在です。
総括すると、いつの時代に置いても通用する『総合力で勝つ』競走馬像を体現した名馬でした。