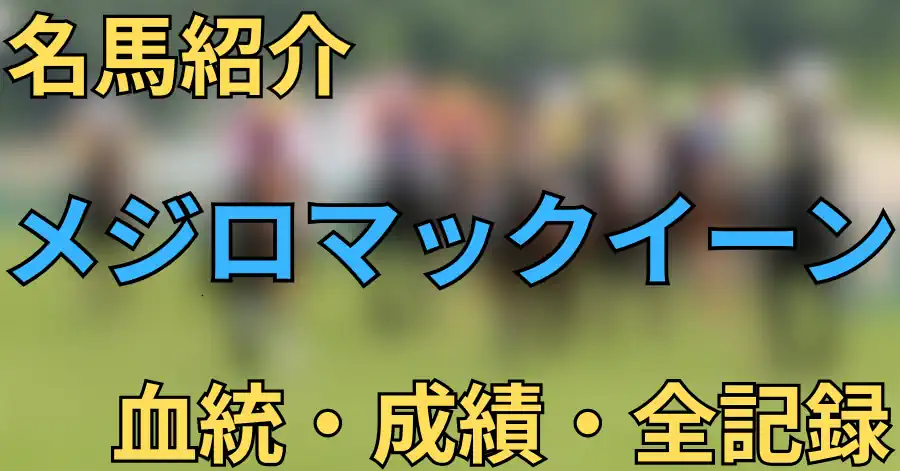メジロマックイーンとは?【競走馬プロフィール】
メジロマックイーンは日本長距離路線の金字塔を打ち立てた名ステイヤーで、菊花賞と二度の天皇賞(春)を制し、現役最終年にはグランプリの宝塚記念まで戴冠した偉大なチャンピオンです。
父は先行粘りと底力を伝えるメジロティターン、母は名牝メジロオーロラ(母父リマンド)で、父子三代にわたる春天制覇という“メジロ三代制覇”の血統物語でも知られます。
平均より速いラップを長く刻む巡航力と、コーナーで減速しにくい大きなストライドが持ち味で、戦術の軸は好位からのロングスパート。
重・不良の消耗戦でもフォームの崩れが小さく、直線半ばでもう一段ギアを上げる“二段加速”で後続を突き放すのが勝ち筋でした。
本記事では血統的背景、育成とデビューまでの足取り、主要レースのラップと戦術、ライバル比較、得意条件、引退後の影響に至るまで、メジロマックイーンの強さの本質を立体的に解説します。
| 生年月日 | 1987/04/03 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牡・芦毛 |
| 生産 | 吉田 堅(北海道・浦河町荻伏) |
| 調教師 | 池江 泰郎/栗東 |
| 馬主 | メジロ商事(株) |
| 通算成績 | 21戦12勝[12-6-1-2] |
| 主な勝ち鞍 | 菊花賞(1990)/天皇賞(春)(1991・1992)/宝塚記念(1993)/京都大賞典(1991・1993)/阪神大賞典(1991・1992)/産経大阪杯(1993) |
| 父 | メジロティターン |
| 母 | メジロオーロラ(母父:リマンド) |
目次
本記事では血統背景、デビューまでの歩み、主要重賞を含む競走成績の推移、名レースBEST5、同世代比較、競走スタイル、引退後の歩みを順に解説します。
各章は句点ごとに改行し、重要語句は赤マーカーで強調し、馬名は青マーカーで示します。
必要に応じて目次から各章へ移動し、知りたいトピックをピンポイントでご覧ください。
- メジロマックイーンの血統背景と特徴
- メジロマックイーンのデビューまでの歩み
- メジロマックイーンの競走成績とレース内容の詳細
- メジロマックイーンの名レースBEST5
- メジロマックイーンの同世代・ライバルとの比較
- メジロマックイーンの競走スタイルと得意条件
- メジロマックイーンの引退後の活動と功績
- メジロマックイーンのよくある質問(FAQ)
- メジロマックイーンの成績表
- メジロマックイーンのまとめ
メジロマックイーンの血統背景と特徴
父メジロティターン、母メジロオーロラ(母父リマンド)という配合は、日本の在来ステイヤー血脈に欧州的な底力と機動力をブレンドした設計でした。
父系はメジロアサマから続く心肺機能の強さと踏み込みの深さが大きな柱で、急坂や長い下りでもスピードを削られにくい“地力”を安定的に伝えます。
母系は古典的英系のしなやかさを通じてフォームの伸びやかさと手前替えの正確さを供給し、コーナーで減速の少ないストライドを実現。
この両者が噛み合うことで、メジロマックイーンはテンで無理をせず好位に収まり、隊列が動く局面でロングスパートへ移行できる“持続加速型”の完成形に到達しました。
気性は前向きながら折り合いに優れ、ハミの取り方が素直で息の入れどころを騎手が作りやすいのも長所です。
さらに骨量のある体躯と柔らかな背中が反動を吸収し、連戦や長距離輸送でもパフォーマンスを落としにくい耐久性を担保しました。
長距離でこそ真価を発揮しますが、瞬時の反応が鈍いわけではなく、直線半ばでの再加速や二段階のギアチェンジにも高い再現性。
日本の芝中長距離が高速化する過程でも対応できた普遍性は、巡航速度の高さと骨格・筋腱の強固さに根ざしています。
メジロマックイーンの父馬・母馬の戦績と特徴
父メジロティターンは天皇賞(秋)を制した名ステイヤーで、先行して渋太く脚を使う競馬に長けた血を伝えました。
祖父メジロアサマ由来の心肺能力と踏み込みの深さは、3000m超の厳しいラップでも踏ん張れる粘着的な強さに直結します。
母メジロオーロラは繁殖成績に優れ、母父リマンドがもたらす欧州的持久力とバランス感覚が、直線でのフォームの崩れにくさを支えました。
この配合から生まれたメジロマックイーンは、反応の速さより“止まらない持続”が際立つタイプで、早仕掛けからの押し切りや、馬場が悪化した場合の底力勝負に強さを発揮します。
加えて骨量のある体躯と柔らかな背中は長距離輸送や連戦にも耐えるタフさを生み、年間を通じてパフォーマンスを維持できる“壊れにくい資質”を備えていました。
結果として父子三代の天皇賞(春)制覇に連なる血の物語が完成し、日本のステイヤー史における一大系譜として記憶されています。
同牝系からはメジロデュレンなどの活躍馬も出ており、持続力とタフネスの遺伝が立証されています。
メジロマックイーンの血統から見る適性距離と馬場
ベストは芝3000〜3200mで、好位〜番手からのロングスパートで押し切る展開がもっとも再現性の高い勝ち筋です。
コースは下りを利用してスピードを乗せやすい京都外回りが理想で、直線に向くまでに加速を完了できる点が強みとなりました。
一方で阪神のタフな起伏でも持続力で押し切れるため、高負荷条件への適応力も一線級です。
馬場は良で指数を伸ばしますが、やや時計のかかるコンディションでもフォームが崩れにくく、スタミナ勝負を歓迎できます。
中距離の2000〜2400mでも地力で上位争い可能で、実際に宝塚記念や京都大賞典で高いパフォーマンスを示しました。
極端な上がり勝負では見せ場が遅れる可能性があるため、早め進出と長いスパートで“先に動いて押し切る”設計が最適解です。
メジロマックイーンのデビューまでの歩み
メジロマックイーンは育成段階から長いキャンターで楽に時計を出せる素材として評価され、坂路・周回ともに“終いで止まらない”タイプでした。
背中の柔らかさと肩の可動域の広さが際立ち、二段階のギアチェンジを行っても背腰に無理がかからないため、負荷を上げても翌日に疲労を残しにくい体質。
気性は前向きながら制御性が高く、並走調教で自らハミを取りにいく一方で折り合いを欠かないバランスの良さを見せました。
早期はダートから実戦を開始しましたが、芝に替わると追走がぐっと楽になり、長手前の大きな伸びでトップスピードへスムーズに移行できることが確認されます。
育成陣営は“ローテの密度より完成度の維持”をテーマに調整を重ね、夏を越えてからの本格化を見据えた体づくりに注力しました。
こうした基礎能力の積み上げが、クラシック路線後半で一気に花開く下地になりました。
メジロマックイーンの幼少期から育成牧場での様子
放牧地では群れの先頭に立つタイプではなく、常に自分のリズムを刻む“マイペースの強さ”が目立ちました。
肩甲骨の可動が大きく、ストライドは水平伸展が効いたロスの少ないフォームで、キャンターの段階から疲れにくい走りを体現。
坂路ではテンに無理をせず終い重点でラップを詰め、周回コースではコーナーで減速しないライン取りを自然に選べるセンスを示します。
暑さ寒さに対する耐性が高く、季節の変わり目の体調管理が容易であったことも、後年の長丁場での安定感につながりました。
柔らかい関節と厚みのある筋腱が負荷を吸収し、週中の強め追いの翌日も歩様がぶれない“壊れにくさ”は特筆でした。
育成スタッフの総合評価は“扱いやすく破綻の少ない一級素材”で、デビュー前から長距離適性と将来性が高く見積もられていました。
メジロマックイーンの調教師との出会いとデビュー前の評価
管理したのは栗東の名伯楽池江 泰郎師。基礎体力と長距離適性に着目し、早い段階から持続力強化を主眼に置いたメニューを導入しました。
追い切りでは終い重点のパターンでもラップを落とさず、併せ馬で前に出られてから再加速して差し返す“粘着的な強さ”が際立ちます。
ダートでの実戦始動後に芝へスイッチしてからは、序盤の追走に余裕を残しつつ、直線での一段上の伸びを見せ、陣営は長距離路線での大成を確信。
クラシック本番に向け、反動の少ないローテを重視して馬体の張りと筋肉の柔軟性を維持する調整に徹し、秋のピークに矢印を合わせました。
ゲートの駐立は落ち着きがあり、遠征や輸送にも動じないメンタルの強さが仕上がりの安定を後押し。
結果として菊花の大輪を咲かせる準備が整い、名ステイヤーへの扉が開かれます。
メジロマックイーンの競走成績とレース内容の詳細
デビューはダート1700mで楽々と先頭へ立ち完勝し、春の芝替わりで持久力を武器に台頭、夏の函館で連勝して素質を一気に開花させました。
秋の嵐山ステークスを経て本番の菊花賞では重馬場の消耗戦を長いスパートでねじ伏せ、ホワイトストーンら同世代の有力馬を完封します。
翌1991年は阪神大賞典でレコード、続く天皇賞(春)で完勝と内容・指数ともに抜群。
夏の宝塚記念はメジロライアンに屈するも、秋の京都大賞典で立て直して快勝しました。
続く天皇賞(秋)は1位入線ながら進路妨害で18着に降着し、レースメイクと進路の明確化が以後の課題として共有されます。
それでもジャパンカップでは世界のゴールデンフェザントらと互角に戦い、年末の有馬記念はダイユウサクの差し脚に惜敗の2着。
1992年は阪神大賞典から天皇賞(春)へと連勝し、帝王の座を固めます。
1993年は距離短縮の産経大阪杯をレコードで制し、春天はライスシャワーの執念のマークに屈して2着も、夏の宝塚記念で堂々と巻き返し、秋の京都大賞典を再びレコードで締めくくりました。
内容・勲章・再現性の三拍子が揃い、歴代屈指のステイヤーとしての評価を不動にしました。
メジロマックイーンの新馬戦での走りとその後の成長
新馬戦はダ1700mの不良馬場を二完歩目から楽に先行、道中は息を入れ過ぎず一定の巡航速度を保ち、直線での再加速で後続を完封しました。
続く条件戦で取りこぼしはあったものの、夏の函館でダ→芝の両条件を制してからは“止まらない持続”が明確な武器となります。
秋の嵐山ステークス2着で長距離適性を再確認し、本番の菊花賞では重馬場をものともせず3コーナーからロングスパートを開始、最後は力でねじ伏せました。
この時点で先行押し切りと早め進出の最適解が固まり、以後は道中での呼吸合わせと仕掛けどころの精度がさらに高まって、古馬相手の長距離戦でも主導権を握れる完成度に到達します。
経験の蓄積とともに手前替えの精度が上がり、上がりのラップを落とさない“王道の伸び”へ研ぎ澄まされていきました。
安定したメンタルと輸送耐性がシーズン通してのパフォーマンス維持に寄与し、完成度は年を追うごとに向上しました。
メジロマックイーンの主要重賞での戦績と印象的な勝利
1991年の阪神大賞典では3分07秒3のレコードで押し切り、続く天皇賞(春)を完勝して三代制覇を達成。
1992年は再び阪神大賞典から天皇賞(春)へと連勝し、長距離王としての地位を不動にしました。
1993年春は産経大阪杯をレコードで逃げ切り、距離短縮でも地力の高さを証明。
夏の宝塚記念は道中3番手から早めにスピードを乗せて直線半ばで抜け出し、後続のイクノディクタスらを完封しました。
秋の京都大賞典は2分22秒7のレコードで押し切り、2400mでも巡航力が落ちない“普遍的な強さ”を改めて示しました。
敗戦でも内容は濃く、1993年の春天ではライスシャワーの徹底マークを受けながらも0.4秒差の2着と地力を誇示。
輸送や馬場差といった外的要因の影響を受けにくい“完成度の高さ”が、各重賞で一貫して表出していました。
メジロマックイーンの敗戦から学んだ課題と改善点
1991年の天皇賞(秋)は1位入線ながら進路妨害による18着降着で、以後は3〜4角での進路明確化と接触回避の徹底が課題として共有されました。
同年末の有馬記念は内でタイトな競馬となり、直線でスペースを失って差し脚を伸ばし切れず2着。
1993年の春天はライスシャワーに厳しくマークされ、ロングスパートの開始をわずかに遅らせざるを得なかった点が誤差となりました。
これらの経験から、道中での位置取りを“半馬身だけ前”に置く意識と、仕掛け開始地点を早めに固定する戦術へ微調整。
結果的に夏の宝塚記念と秋の京都大賞典の完勝につながり、最終年にして完成度はむしろピークへ到達しました。
敗戦の質が高かったこと自体が“崩れにくい王者”である証左でもあります。
メジロマックイーンの名レースBEST5
メジロマックイーンの名レース第5位:京都大賞典(1993)
秋初戦の2400mで2分22秒7というレコードタイムを叩き出し、距離短縮でも巡航力が落ちないことを証明しました。
道中は淡々としたミドルラップを自ら刻み、3角手前からロングスパートを開始して直線半ばで完全に抜け出す王道の勝ち方。
相手は古馬の強豪陣で、レースレベル自体が高い中での押し切りは“全適性型ステイヤー”としての完成度を示しました。
良馬場の高速条件でストライドが伸び切ると、トップスピードの持続時間が他馬と段違いであることが数値でも明確に示されました。
この内容が、のちの種牡馬像においても“息の長い加速を伝える”という評価につながります。
メジロマックイーンの名レース第4位:菊花賞(1990)
重馬場で体力の消耗が激しい条件下、3コーナーからの早仕掛けで主導権を奪い、最後はホワイトストーンらを完封しました。
直線ではストライドの伸長と手前替えがほぼ同時に決まり、二段階のギアチェンジで後続を寄せ付けない完勝。
この勝利によって長距離路線の主役に名乗りを上げ、翌年以降の帝王ロードの入口に立ちました。
重馬場という逆境下で“崩れない”ことを可視化した一戦で、持続力の上限値とメンタルの強さが際立っています。
条件不問の持続力が“グランプリ級”であることを初めて世に示した象徴的勝利でした。
メジロマックイーンの名レース第3位:天皇賞(春)(1992)
前年に続く連覇のかかった大一番で、序盤から深追いしない好位策を選択し、向正面で自然にスピードを乗せて直線半ばで抜け出しました。
長距離馬にありがちな“瞬発の弱さ”を感じさせず、隊列が動いた局面での再加速の速さが際立つ完勝劇。
着差以上に余力を残しており、長距離王としての地位を国内で確固たるものにしました。
父子三代の春天制覇を“連覇”で飾った象徴性も含め、内容・指数・文脈が高い次元で整った名勝負です。
メジロマックイーンの名レース第2位:宝塚記念(1993)
春の古馬路線の締め括りで、距離2200mというタフな舞台ながら、3番手から早め進出で直線半ばで押し切る横綱相撲。
後続のイクノディクタスらの追撃を凌ぎ、マイル〜中距離指向の強い相手にも巡航力と持続力で上回りました。
コースの起伏とコーナーのきつさをものともしないフォームの安定が、道中のロスを最小化し勝利を引き寄せました。
中距離における地力の高さを明確化し、長距離専科に非ずという“普遍性”を強く印象づけた一戦です。
翌秋のレコード走破へと続く上昇線のターニングポイントでもありました。
メジロマックイーンの名レース第1位:天皇賞(春)(1991)
三代にわたる天皇賞(春)制覇を達成した歴史的一戦。
スタートから無理なく好位を確保し、3〜4角でロングスパートを開始、直線では余力十分に抜け出して完勝しました。
内容・指数・象徴性の三点が最高水準で、以後の“長距離王”としての評価を決定づけた金字塔です。
当時の世代・路線の勢力図を一変させ、日本のステイヤー像を更新した、キャリアのベストと断じて差し支えません。
勝ち方の普遍性が後年まで語り継がれる所以でもあります。
メジロマックイーンの同世代・ライバルとの比較
同時代の古馬・三冠路線には多様な個性が並び、長距離では地力型、グランプリでは瞬発力・機動力型との激突が続きました。
メジロライアンの中距離適性、末脚持続型のイクノディクタス、タフな差し脚のナイスネイチャ、世界のゴールデンフェザントらとの対戦がレースレベルを押し上げます。
それでもメジロマックイーンは先行からのロングスパートで主導権を握り、距離・馬場・展開の違いを跨いで安定して上位に居続けました。
指数面でも高水準を継続し、輸送や時期によるブレが小さい“再現性の高さ”が、同世代群を一歩リードする要因でした。
総合力×再現性という観点で、王道の完成度が最大の差異として浮き彫りになります。
メジロマックイーンの世代トップクラスとの直接対決
1991年の春は阪神大賞典レコードから天皇賞(春)完勝へと駆け上がり、夏の宝塚記念ではメジロライアンに凌がれたものの、秋の京都大賞典で巻き返して地力の差を示しました。
国際舞台ではジャパンカップでゴールデンフェザントら一線級と堂々の勝負、年末の有馬記念は展開の綾でダイユウサクに及ばず2着。
翌1992年には天皇賞(春)連覇で“王者の強さ”を再確認させ、1993年には距離短縮の産経大阪杯と中距離の宝塚記念を制して適性幅の広さを立証しました。
直接対決の累積で見ても、地力・戦術の完成度が一段高い存在であることが明確です。
対戦相手の質が高いほどパフォーマンスが上がる“対強敵性能”も目立ちました。
メジロマックイーンのライバルが競走成績に与えた影響
厳しいマークや瞬発特化型との対戦が続いたことで、3角手前からの“早めの踏み上げ”と直線入口での再加速という二段構えが磨かれました。
また、渋化や不良での経験値がスタミナとフォームの安定性を高め、良馬場でもバテない“持続力の上限”を押し上げています。
結果としてメジロマックイーンは距離・馬場・展開の三条件がそろわなくても崩れにくく、勝ち筋を複数持つ完成形へと到達。
ライバルの存在は王者の戦術に必要な微調整を促し、最終年の高パフォーマンスへとつながりました。
多様な個性との対峙が“普遍性のある強さ”を醸成したと言えます。
メジロマックイーンの競走スタイルと得意条件
理想形はスタート後に無理なく好位〜番手に取りつき、ペースが動く3角手前から長いスパートで押し切る王道路線です。
道中は呼吸を乱さずに一定の巡航速度を維持し、直線半ばでの再加速で決着を付けるパターンがもっとも強みを発揮します。
先行差しの自在性はありますが、差し一辺倒にせず主導権を握ることでパフォーマンスが安定し、厳しいラップでも最後の一完歩まで脚色が鈍りません。
持続加速の質が問われる厳しい展開ほど優位性が大きく、逆に瞬発一点勝負では早め進出で主導権を取りに行くのが最適解。
枠順は内外を問わず、外を回してもフォームが崩れにくい点がリスクヘッジとなります。
メジロマックイーンのレース展開でのポジション取り
二完歩目の推進力で自然に好位へ、1〜2角ではラチ沿いを丁寧に進めてロスを最小化し、向正面で徐々にギアを上げます。
3角で一段上の巡航速度に入れてから直線入口でエンジン全開、残り300mでさらに“もう一段”伸びる二段加速が理想形です。
外を回してもコーナリングで減速しないため、進路の自由度が高く、馬群が密になる大舞台でも安全マージンを確保しやすいのが強み。
ペースが緩んだ際には早めに仕掛けて持久戦に持ち込み、スピードの絶対値より“止まらない持続”で上からねじ伏せます。
道悪では脚抜きの良さを活かし、良馬場ではストライドの伸びで圧をかける柔軟な対応が可能です。
メジロマックイーンの得意な距離・馬場・季節傾向
距離は3000〜3200mが最良で、総合力勝負なら2400mや2200mでも地力で上位。
馬場は良で指数が伸びますが、重・不良の消耗戦でも持続力で押し切れるため適性幅は広いと言えます。
季節は春先と初夏にピークを作りやすく、秋は叩きつつ上昇してグランプリ前に仕上がる循環が理想的でした。
輸送や連戦に対する耐性が高く、ローテーションの密度が上がっても崩れにくいのが特徴です。
総じて“条件不問の持続力”が土台にあり、相手関係や展開の違いを跨いで勝ち筋を複数描けます。
メジロマックイーンの引退後の活動と功績
引退後は種牡馬として供用され、長く脚を使える資質と前進気勢の強さを広く伝えました。
平地・障害を問わずスタミナと気の良さを活かす産駒が多く、地方・交流重賞でも活躍馬を輩出しています。
母父としても影響は着実で、長距離・中距離問わずに“粘ってもう一段伸びる”型を多く遺した点が特徴です。
功労馬としても厚く愛され、日本のステイヤー像を体現した存在として今なお語り継がれています。
引退馬支援の文脈でも象徴的な存在で、名馬の価値を世代横断で伝える役割を担い続けています。
メジロマックイーンの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
産駒には重賞勝ち馬をはじめ、持続力勝負に強いタイプが多く見られます。
代表例としては重賞ウイナーのヤマニンメルベイユ、ホクトスルタン、オープン級のタイムフェアレディなどが挙げられ、先行押し切り型・持続差し型の双方で結果を出しました。
繁殖牝馬を通じても“巡航速度の高さ”と“壊れにくい体質”を伝え、古馬になってからの上積みが見込める傾向が強い系統を形成しています。
母父としても牝馬重賞や長距離戦での活躍例が多く、血脈の持続力は世代を超えて受け継がれています。
配合面ではスタミナの土台の上に瞬発力を補う配合が好相性で、実戦でも完成度の高い走りを引き出しました。
メジロマックイーンの産駒の活躍と後世への影響
スピード一辺倒ではない“粘って勝つ”スタイルを次世代に継承し、日本の中長距離戦での戦術多様化に寄与しました。
スタミナ×柔軟性というバランスの良さが、厳しいラップを刻む現代競馬でも通用することを産駒が証明し続けています。
また、ファン層においても“王道の強さ”を象徴する存在として語り継がれ、引退馬支援の機運を高める象徴的ブランドとなりました。
名血の継承は競走成績のみならず、文化的側面にも波及し、写真展・回顧記事・記念イベントなど多層的に価値が再発見されています。
血統と文化の両面で、日本競馬に長く影響を与え続けるレガシーです。
メジロマックイーンのよくある質問(FAQ)
Q. 天皇賞(秋)で降着になったのはなぜ?
A. 1991年の天皇賞(秋)は1位入線後に進路妨害が認定され18着へ降着、2位入線のプレクラスニーが繰り上がり優勝となりました。
以後は接触回避と進路の明確化がチームの最重要課題となり、タイトな馬群では安全マージンを広く取る戦術へ微調整が施されています。
この経験は“早めの踏み上げ”と“二段加速”の徹底につながり、後年の安定感を高める転機となりました。
Q. 最も得意な条件は?
A. 芝3000〜3200mでのロングスパートが最良です。
好位〜番手で運び、3角手前から加速を始めて直線半ばで勝ち切る設計がもっとも再現性が高く、良馬場でも渋化でも大きくパフォーマンスを落としません。
中距離では宝塚記念や京都大賞典のように巡航力で圧をかける競馬が有効で、普遍性の高さを示します。
Q. 主なライバルは?
A. 中距離の強豪メジロライアン、持続型のイクノディクタス、タフな末脚のナイスネイチャ、国際舞台ではゴールデンフェザントなどが代表格です。
それぞれ異なる強みを持ちますが、メジロマックイーンはロングスパートの質で上回り、総合力勝負で優位に立ちました。
厳しいマークを受けても崩れにくい完成度が最大の武器です。
Q. 種牡馬としての評価は?
A. 産駒数は多くありませんが、持続的なスピードと素直な気性を伝えることで、平地・障害・地方交流まで幅広く勝ち上がりを出しました。
母父としても息の長い脚と体質の丈夫さを伝える例が多く、血統の価値は世代を超えて評価されています。
配合の観点では、瞬発力を補う速い血との組み合わせで完成度が高まりやすい傾向があります。
メジロマックイーンの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/02/03 | 阪神 | サラ系4才 新馬 | 2 | 1 | 村本 善之 | ダ1700 | 不良 | 1:47.7 |
| 1990/02/25 | 阪神 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 1 | 2 | 村本 善之 | 芝2000 | 重 | 2:04.6 |
| 1990/05/12 | 京都 | あやめ賞(500万下) | 1 | 3 | 村本 善之 | 芝2200 | 良 | 2:17.5 |
| 1990/09/02 | 函館 | 渡島特別(500万下) | 1 | 2 | 内田 浩一 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 |
| 1990/09/16 | 函館 | 木古内特別(500万下) | 1 | 1 | 内田 浩一 | ダ1700 | 重 | 1:47.3 |
| 1990/09/23 | 函館 | 大沼S(900万下) | 1 | 1 | 内田 浩一 | 芝2000 | 不良 | 2:04.5 |
| 1990/10/13 | 京都 | 嵐山S(1500万下) | 1 | 2 | 内田 浩一 | 芝3000 | 稍重 | 3:06.6 |
| 1990/11/04 | 京都 | 菊花賞(GI) | 4 | 1 | 内田 浩一 | 芝3000 | 重 | 3:06.2 |
| 1991/03/10 | 中京 | 阪神大賞典(GII) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝3000 | 良 | 3:07.3 |
| 1991/04/28 | 京都 | 天皇賞(春)(GI) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝3200 | 良 | 3:18.8 |
| 1991/06/09 | 京都 | 宝塚記念(GI) | 1 | 2 | 武 豊 | 芝2200 | 良 | 2:13.8 |
| 1991/10/06 | 京都 | 京都大賞典(GII) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 |
| 1991/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(GI) | 1 | 18 | 武 豊 | 芝2000 | 不良 | 2:02.9 |
| 1991/11/24 | 東京 | ジャパンC(GI) | 1 | 4 | 武 豊 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 |
| 1991/12/22 | 中山 | 有馬記念(GI) | 1 | 2 | 武 豊 | 芝2500 | 良 | 2:30.8 |
| 1992/03/15 | 阪神 | 阪神大賞典(GII) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝3000 | 稍重 | 3:13.5 |
| 1992/04/26 | 京都 | 天皇賞(春)(GI) | 2 | 1 | 武 豊 | 芝3200 | 良 | 3:20.0 |
| 1993/04/04 | 阪神 | 産経大阪杯(GII) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 |
| 1993/04/25 | 京都 | 天皇賞(春)(GI) | 1 | 2 | 武 豊 | 芝3200 | 良 | 3:17.5 |
| 1993/06/13 | 阪神 | 宝塚記念(GI) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝2200 | 良 | 2:17.7 |
| 1993/10/10 | 京都 | 京都大賞典(GII) | 1 | 1 | 武 豊 | 芝2400 | 良 | 2:22.7 |
メジロマックイーンのまとめ
メジロマックイーンは持続加速の質と巡航速度の高さで時代の長距離戦を支配し、菊花賞、天皇賞(春)連覇、宝塚記念と多彩な舞台で頂点に立った普遍性のチャンピオンでした。
父メジロティターンから受け継いだ粘着的な強さと、母系のしなやかさが融合して“止まらないロングスパート”を実現。
ライバルとの高密度な対戦で戦術を磨き、最後の一完歩まで脚色が鈍らない強さでファンを魅了しました。
引退後は種牡馬・母父としてもスタミナと気の良さを伝え、血統と文化の両面で日本競馬に長く影響を及ぼしています。
日本のステイヤー像を更新した永遠のベンチマークとして、今後も語り継がれる存在です。