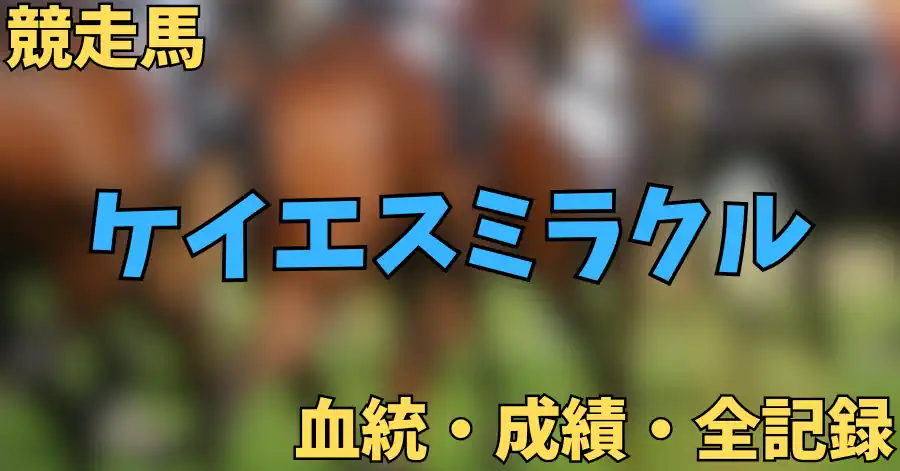ケイエスミラクルとは?【競走馬プロフィール】
ケイエスミラクルは1991年の京都・スワンステークス(GII)を制し、同年のマイルチャンピオンシップ(GI)3着で一線級の実力を証明した快速スプリンター/マイラーです。
米国産の輸入馬で、父はStutz Blackhawk、母はレデイベンドフエイジヤー(母父Never Bend)というスピード色の強い配合でした。
札幌の短距離条件戦を連勝して一気にオープン入りし、秋は重賞を勝ってマイルGIでも上位に食い込みました。
通算成績は10戦5勝、総賞金は1億3,422.6万円で、短距離路線に鮮やかな足跡を残しました。
最終戦のスプリンターズSでは不運にも競走中止となり、予後不良のため現役生活に幕を下ろしています。
- 生年月日
- 1988年3月16日
- 性別・毛色
- 牡・鹿毛
- 産地
- 米国(USA)
- 生産
- Tsukao Farm(USA)
- 調教師
- 高橋 成忠(栗東)
- 馬主
- 高田 喜嘉
- 通算成績
- 10戦5勝[重賞1勝]
- 獲得賞金
- 1億3,422.6万円
- 主な勝ち鞍
- スワンステークス(GII)、オパールS(OP)、藻岩山特別、石狩特別
- 父
- Stutz Blackhawk(父父:Mr. Prospector)
- 母
- レデイベンドフエイジヤー(母父:Never Bend)
- 没年月日
- 1991年12月15日(スプリンターズS競走中止後・予後不良)
目次
血統背景と特徴
ケイエスミラクルは米国生まれの輸入馬で、父にStutz Blackhawk、母にレデイベンドフエイジヤーを持つ、北米的スピードを核にした配合です。
父系は祖父Mr. Prospectorへさかのぼる名門で、初速の鋭さとトップスピードの持続を伝えるのが特徴です。
母父Never Bendは粘りと機動力を補い、コーナーで減速しにくいストライドを後押しします。
これらが合わさることで、序盤は無理せず折り合い、勝負所で一気に速度域を引き上げる「加速一閃」の走りが完成しました。
札幌の洋芝から京都の高速馬場まで適応し、どの舞台でもスピードの絶対値で勝負できた点に、この血統の再現性と普遍性が表れています。
父馬・母馬の戦績と特徴
父Stutz Blackhawkは米国の短距離で存在感を示した種牡馬で、祖父Mr. Prospector譲りの初速・切れ味・巡航速度の三拍子を伝えます。
母レデイベンドフエイジヤーはNever Bend直系の芯の強さを持ち、コーナーでスピードを落とさずに直線へ繋ぐレースセンスを供給しました。
父系の爆発的スピードと母系の安定した粘りが融合し、短距離〜マイルで「行き脚→機動→持続」を高いレベルで両立させる個性を生みました。
その結果、ケイエスミラクルは条件戦から重賞まで同じ勝ち筋で押し切れる一貫性を獲得し、相手強化にも対応できました。
血統段階で描ける理想図を、実戦でそのまま体現したタイプと言えるでしょう。
血統から見る適性距離と馬場
配合と走法から見たベストレンジは芝1200〜1600mで、特に1400mは機動力と持続が噛み合う適距離でした。
1200mでは好位確保が容易で、直線も速度を落とさず「止まらない脚」を発揮できます。
1600mは淀みない流れで脚を温存できれば、最後の直線でしっかりと弾けて上位争いが可能でした。
馬場は良〜稍重の高速〜標準域が理想で、札幌・京都などリズム良く加速できるコース形態と相性が良好でした。
平坦や緩やかな下りを活かすと強く、ペースが流れても崩れにくい持続的なスピード性能が最大の武器でした。
デビューまでの歩み
ケイエスミラクルは米国で育成され、日本へ輸入後に栗東へ入厩しました。
背中から腰にかけてのしなりが良く、踏み込みは深く回転は速いという、短距離型として理想的な素地を早期から見せています。
前向きな気性ですが扱いやすく、稽古では「速くてもブレないフォーム」を保ちながら終い重点で負荷をかけるプログラムを反復しました。
ゲートの反応も良好で、スタート後に自然と好位へ収まれる点が武器となりました。
新潟での実戦始動を皮切りに、夏の札幌で能力を一気に開花させる土台が整っていきます。
幼少期から育成牧場での様子
幼少期のケイエスミラクルは骨格のバランスが良く、背腰に柔らかさがあり、加速時のロスが少ないタイプでした。
歩様は軽く、回転の速いフットワークながら沈み込みも確保でき、短距離での初速と持続の両立が期待されました。
気性面は前向きでも折り合いに課題は少なく、追われてから集中を高める素直さが評価されました。
硬さが出やすい時期には段階的に負荷を上げる調整で弾け方を磨き、仕掛けてからのギアチェンジが一段と鋭くなりました。
ゲート練習の習熟も早く、実戦デビュー後の安定感につながっています。
調教師との出会いとデビュー前の評価
管理した高橋成忠調教師は、最大の武器であるスピードの質を落とさないことを最優先に、淀みのないリズムで運ぶ調整を徹底しました。
坂路とコース追いを組み合わせ、終い重点でも手応えに余力を残すメニューを反復し、速さと持続をバランスよく底上げしました。
入厩時から反応の良さが際立ち、短距離なら古馬相手でもスピードの絶対値で見劣らないという評価が早くから固まりました。
実戦でも「行き脚→コーナー機動→直線持続」の三拍子が噛み合い、札幌での連勝で一気にオープン入りして重賞戦線へ向かう青写真が明確になりました。
結果として、夏の時点で重賞級のポテンシャルを可視化できたことが、秋の活躍につながっています。
競走成績とレース内容の詳細
ケイエスミラクルは新潟で素質を示しつつ、夏の札幌で連勝して一気に軌道に乗りました。
秋は京都のオパールSを制して重賞へ駒を進め、1400mのスワンS(GII)で重賞初制覇。
さらにマイルGIでも価値ある3着に入り、1200〜1600mの広いレンジで一線級と互角以上の競馬を披露しました。
最終戦のスプリンターズSでは不運なアクシデントに見舞われましたが、積み上げた内容は短距離路線の強豪として遜色ないものでした。
デビューから1年足らずで駆け抜けた凝縮のキャリアが、その資質の高さを物語ります。
新馬戦での走りとその後の成長
1991年春の新潟で未出走戦に登場したケイエスミラクルは、初戦から先行力と反応の速さを披露しました。
2戦目で即勝ち上がると、その勢いのまま札幌へ移動し、石狩特別・藻岩山特別を連勝して一気にオープンの入り口へ到達します。
洋芝でスムーズにスピードへ乗れる点が再現性のある強みとなり、番手〜好位からロスなく抜け出す勝ち方を身につけました。
クラスが上がっても折り合いを欠かず、直線では“止まらないスピード”を発揮し、押し切る競馬が板につきます。
夏の時点で重賞級のスピード能力を可視化できたことが、秋以降の重賞・GI挑戦へ踏み切る確かな根拠となりました。
主要重賞での戦績と印象的な勝利
秋のオープン・オパールSを快勝し、京都外回り1400mのスワンステークス(GII)では中団からの機動力と末の持続で堂々の重賞制覇を果たしました。
スローからの立ち上がりでもトップスピードへの移行が速く、直線では内外どちらでも脚色が鈍らない完成度の高い内容でした。
続くマイルチャンピオンシップ(GI)でも王者級を相手に差のない3着に好走し、1600mでも十分に通用することを証明しました。
短距離の高い巡航速度にマイルの持続力を上積みできる希少なタイプで、舞台・流れを問わず上位争いが可能な総合力を示しました。
重賞制覇からGI善戦まで、上昇カーブを描く理想的な臨戦過程でした。
敗戦から学んだ課題と改善点
セントウルSは流れが合わず大敗しましたが、スピード負荷への耐性と進路取りの重要性を学ぶ材料になりました。
またスプリンターズSでは不運なアクシデントで競走を中止し、予後不良という悲しい結末を迎えました。
ただ、敗戦の中でもスタートの反応や道中のリズムに大きな問題はなく、展開の綾が勝敗に直結するカテゴリーであることを改めて示す結果でもありました。
1400mでの勝ちパターンをベースに、マイルでの仕掛けどころをどう最適化するかという戦術的課題も明確化しました。
総じて、経験は勝ち筋の精度を高め、短期間での完成度向上に寄与しています。
名レースBEST5
短距離〜マイルの主要ステージで存在感を示したケイエスミラクルのレースから、内容と価値の両面で印象に残る5戦を時系列と重要度を踏まえて選びました。
条件戦の快勝から重賞制覇、GIの上位入線まで、走りの核心である「機動×持続」の強みが一貫して表れています。
以下の5戦は、距離や展開が変わっても通用するスピードの普遍性を示す教材と言えるでしょう。
各レースの状況や舞台特性も併記し、当時の位置取りや勝ち筋の手触りが伝わるよう整理しました。
当日の時計や着差に加え、内容での圧力も評価しています。
第5位:1991年 石狩特別(札幌・芝1200m)
札幌の500万下を先行押し切りのセオリーで制した一戦です。
洋芝でもスピードに乗るまでの時間が短く、直線では手応えに余裕を残しつつゴールへ駆け抜けました。
この勝利が短距離路線での将来性を強く印象づけ、以後の連勝とクラス上昇の起点になりました。
札幌独特のコーナーでも減速せず回れる機動力は以降の強みとなり、ローカルから中央場所へ向かう足がかりとして価値の高い内容でした。
“スピードの再現性”という武器が、ここで明確になりました。
第4位:1991年 藻岩山特別(札幌・芝1200m)
石狩特別からの連勝で一気に格上挑戦ムードを高めたレースです。
コーナリングから直線に入るところでスムーズにギアを上げ、最後までスピードを落とさない“止まらない脚”を披露しました。
条件戦ながら勝ち方の質が高く、オープン級でも通用するスピードの絶対値と再現性のある立ち回りを示しました。
夏場にパフォーマンスのピークを作れた点も、秋の重賞戦線で即通用する下地となりました。
内容面の圧で、次走以降の相手強化にも不安を抱かせない完勝でした。
第3位:1991年 オパールステークス(OP・京都・芝1200m)
本州に戻ってのオープン特別は、京都内回りの流れでも行き脚を失わず、直線でしぶとく伸びて快勝しました。
ペースが流れても脚色が鈍らないマイペースの強みが出て、格上げ初戦として満点に近い内容でした。
1400mへの布石としても理想的で、先行策だけに縛られない自由度の高さを示したのが象徴的でした。
ここでの勝利が、外回り1400mのスワンS制覇へと直結します。
短距離での基礎スピードを、中距離寄りの機動へ転化できることを証明したステップでした。
第2位:1991年 マイルチャンピオンシップ(GI・京都・芝1600m)
一線級が揃う大舞台でも自身のリズムを崩さず、価値ある3着でした。
中団で脚を溜め、直線では減速しない巡航速度でゴールへ。
距離延長でも持続力が落ちないことを実戦で示し、1200〜1600mの幅広いレンジで強豪相手に戦えることを証明しました。
舞台適性と戦術の自由度が交差した、総合力の高さが光る一戦です。
内容での“強さ”が記録以上に語り継がれています。
第1位:1991年 スワンステークス(GII・京都・芝1400m)
キャリアのハイライトとなった重賞制覇です。
序盤は中団で落ち着いて流れに乗り、3〜4角で外からスムーズに進出、直線ではトップスピードを長く保って押し切りました。
1400mという距離が最も能力を発揮できるレンジであることを雄弁に物語る内容で、勝ち時計も堂々たるものでした。
以後のGIでも通用する裏付けとなった金星であり、「スピードの質×持続」を高次元で満たした名勝負でした。
短距離路線での到達点を示す、完成度の高い勝ち方でした。
同世代・ライバルとの比較
短距離〜マイル路線には強豪がひしめき、ケイエスミラクルはその隊列へ堂々と割って入りました。
京都外回り1600mのように直線の長い舞台では瞬発力と持続の総合力勝負になりやすく、3着好走は実力の証明でした。
一騎打ちというより強豪が作るハイペースに適応するタイプで、着差以上に内容で見せ場を作るのが持ち味でした。
1400mではコーナーで減速しにくい機動力が相対的なアドバンテージとなり、勝ち切る力を示しました。
結果として、その年の短距離路線において確かなポジションを確立しています。
世代トップクラスとの直接対決
重賞やGIで対峙したトップホース相手にも、ケイエスミラクルは自らの勝ち筋を崩さずに戦いました。
平均以上のラップでも巡航速度を保つ強みが、GIの総合力勝負で上位進出の根拠となりました。
位置取りは中団〜好位が理想で、4角での進出にロスがないため、直線の距離が伸びても脚色を落としません。
重賞制覇とGI善戦で示した内容は、相手関係を問わず通用するスピードの普遍性に裏づけられています。
強豪との対決が短期間での完成度向上を押し上げ、ハイレベルな実戦経験が武器になりました。
ライバル関係が競走成績に与えた影響
強敵と相まみえることで、序盤の力みを抑えて「勝負所でギアを上げる」理想形が洗練されました。
展開の幅に対応するため位置取りの柔軟性が増し、先行〜差しどちらでも末脚を失わない運びを確立できました。
結果として、距離が1400mなら勝ち切り、マイルでも上位争いという「勝ち筋の明確化」に繋がりました。
敗戦も含めて糧となり、短期間で重賞級まで押し上げるブーストとして機能しました。
対戦を重ねるごとに、相手強化への耐性が確かになりました。
競走スタイルと得意条件
ケイエスミラクルの勝ち筋は「中団〜好位で脚を温存→3〜4角で自然に速度域を一段上げ→直線は止まらない速度維持」です。
コーナーで減速しにくいフォームと、馬込みでも集中を切らさない気性が、進路取りの自由度を広げました。
極端なスローで隊列が固まると届かないリスクがある一方、平均的に流れるペースでは総合力で上回ります。
京都・札幌などリズム良く加速できるコースで最大値を発揮し、1200〜1600mの広いレンジで高いパフォーマンスを安定して示しました。
「機動×持続」を同時に満たせる舞台設定が理想です。
レース展開でのポジション取り
ケイエスミラクルはスタートの反応が良く、出せば先行、溜めれば中団差しの両構えが可能でした。
理想は中団〜好位でリラックスして運び、3〜4角でスムーズに進出して直線でトップスピードを長く保つ形です。
密集隊列でも怯まない集中力があり、最短距離と加速のしやすさを両立したコース取りが得意でした。
ペースが上がった際は前半で無理をせず、勝負所で一気にギアを上げることで最後の一伸びを引き出せます。
この“使いどころ”の精度が、短距離戦の勝敗を分けました。
得意な距離・馬場・季節傾向
ベストは芝1400mで、1200mでも高いパフォーマンスを安定して発揮できます。
1600mでは流れに乗れれば最後まで脚色が鈍らず、ハイレベル相手にも通用しました。
良馬場の高速〜標準域が得意で、直線の長い外回りや平坦コースで持続力がより活きます。
夏のローカルで力を蓄え、秋の中央場所で一段階上の内容を見せるリズムを確立しました。
総じて、展開に左右されにくい高質な巡航速度が最大の武器でした。
引退後の活動と功績
ケイエスミラクルはスプリンターズSで競走中止となり、予後不良の判断が下されました。
したがって、繁殖入り(種牡馬供用)は行っていません。
本項では、実産駒の実績ではなく、競走生活を通じて残した「戦術・血統・育成面への示唆」という観点で足跡を記します。
短期間で重賞制覇とGI上位を同時に成し遂げたプロセスは、短距離路線における上昇曲線の作り方の好例として今も参照されます。
最後までブレないフォームでスピードを保つことの重要性は、育成・調整の現場で語り継がれる財産になりました。
種牡馬・繁殖牝馬としての実績
ケイエスミラクルは予後不良となったため、種牡馬としての供用実績はありません。
よって、血統登録上の産駒も存在せず、繁殖成績の数値的評価はできません。
その一方で、父Stutz Blackhawk—祖父Mr. Prospectorに連なるスピードの系統が、短距離〜マイルの配合設計で重視され続けている事実は見逃せません。
現役時に示した「1200〜1600mでの機動と持続の両立」という走りのモデルは、種牡馬としての足跡こそ残せなかったものの、配合・戦術の議論に影響を与え続けています。
実産駒の欄は空白でも、そのスピード概念が“学び”として残った点は、広義の功績だと言えます。
産駒の活躍と後世への影響
産駒は存在しないため、直接的な血統的影響は残していません。
しかし、短距離路線での到達点を短期間で示したキャリアは、育成・臨戦過程の設計にヒントを与えました。
具体的には「夏に洋芝で土台をつくり、秋に中央場所で上積みを示す」というリズムや、「1400mを軸に1200・1600mへ枝分かれする勝ち筋」の考え方です。
また、ラストランの事故を受け、馬の安全と福祉をいかに確保するかという視点も広く共有されました。
血を残せなかった一方で、戦い方と学びは後世へ受け渡されています。
成績表
※ユーザー様提供のnetkeibaデータおよび公的データベースを照合し、古い順で掲載しています。
タイム欄が空白のレースは公式記録に従い「-」表記としています。
| 日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/04/20 | 新潟 | 4歳未出走 | 2 | 佐伯清久 | 芝1600 | 稍 | 1:37.2 | 初陣で素質示す |
| 1991/05/04 | 新潟 | 4歳未出走 | 1 | 佐伯清久 | 芝1400 | 稍 | 1:23.5 | 先行押し切りで初勝利 |
| 1991/05/11 | 新潟 | わらび賞(500万下) | 2 | 佐伯清久 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | マイルでも崩れず |
| 1991/06/08 | 札幌 | 石狩特別(500万下) | 1 | 南井克巳 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 札幌で鮮やか勝利 |
| 1991/06/22 | 札幌 | 藻岩山特別(900万下) | 1 | 南井克巳 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 連勝で一気に昇級 |
| 1991/09/08 | 中京 | セントウルS(GIII) | 13 | 南井克巳 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 流れ合わず大敗 |
| 1991/10/05 | 京都 | オパールS(OP) | 1 | 南井克巳 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | オープン初勝利 |
| 1991/10/26 | 京都 | スワンS(GII) | 1 | 南井克巳 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | 重賞制覇 |
| 1991/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 3 | 南井克巳 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | GIで価値ある3着 |
| 1991/12/15 | 中山 | スプリンターズS(GI) | 中止 | 岡部幸雄 | 芝1200 | 良 | - | 競走中止(予後不良) |
まとめ
ケイエスミラクルは、米国生まれのスピード血統を背景に、日本の短距離〜マイル路線で強烈な存在感を放った快速馬です。
札幌での連勝から京都のスワンS制覇、さらにマイルCS3着へと駆け上がり、わずか一年で重賞級の地位を確立しました。
ベストは1400mで、1200m・1600mにも対応できる器用さと持続力を兼備していました。
最終戦のアクシデントは痛恨でしたが、短期間で積み上げた内容は一流の証です。
通算10戦5勝という凝縮されたキャリアに、「機動×持続」で頂点へ迫った短距離の理想形が凝縮されています。