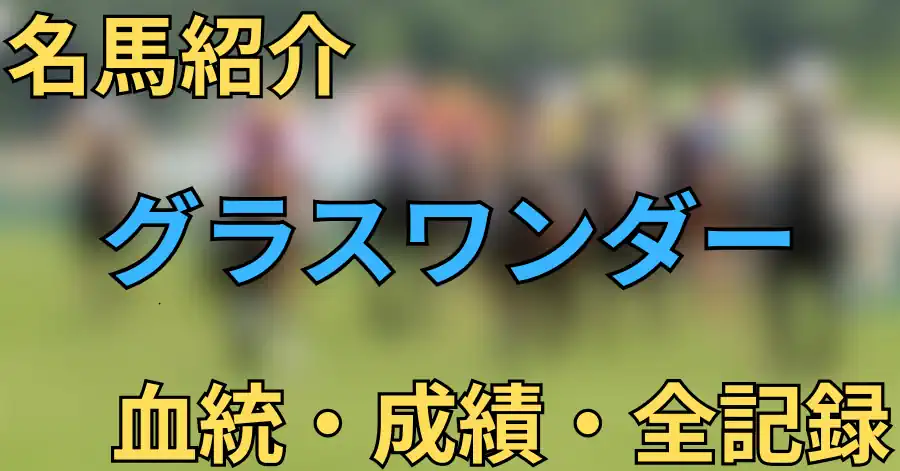グラスワンダーとは?【競走馬プロフィール】
グラスワンダーは1990年代後半の古馬路線を席巻した米国産の持ち込み馬で、2歳時は無傷の4連勝で朝日杯3歳Sをレコード制覇、古馬になってからは宝塚記念と有馬記念を制して“グランプリ3連勝”を達成した名馬です。
父はロベルト直系のSilver Hawk、母はAmeriflora(母父Danzig)で、骨太な持久力と北米的なスピードを高い次元で兼備しました。
実戦では好位から長く脚を使う戦法を基本とし、加速を一度掛けるとラスト50メートルでもう一段伸びる独特の“二枚腰”で接戦をもぎ取りました。
主な勝ち鞍は朝日杯3歳S、有馬記念(1998・1999)、宝塚記念、毎日王冠、京王杯スプリングC、京成杯3歳Sなどで、通算15戦9勝[9-1-0-5]という密度の高いキャリアでした。
引退後は種牡馬としてスクリーンヒーロー、アーネストリー、セイウンワンダーらを輩出し、父系はモーリスへ継承されて日本芝の質を押し上げました。
2025年8月8日に30歳で逝去しましたが、グランプリ連覇と系譜の繁栄により、その名は今なお語り継がれています。
| 生年月日 | 1995年2月18日 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牡・栗毛 |
| 生産 | Phillips Racing Partnership & John Phillips(米国) |
| 調教師 | 尾形充弘/美浦 |
| 馬主 | 半沢(有) |
| 通算成績 | 15戦9勝[9-1-0-5] |
| 主な勝ち鞍 | 朝日杯3歳S(1997)/有馬記念(1998・1999)/宝塚記念(1999)/毎日王冠(1999)/京王杯スプリングC(1999)/京成杯3歳S(1997) |
| 父 | Silver Hawk |
| 母 | Ameriflora(母父:Danzig) |
目次
本記事では血統背景、デビューまでの歩み、主要重賞を含む競走成績の推移、名レースBEST5、同世代比較、競走スタイル、引退後の歩みを順に解説します。
各章は句点ごとに改行し、重要語句は赤マーカーで強調し、馬名は青マーカーで示します。
必要に応じて目次から各章へ移動し、知りたいトピックをピンポイントでご覧ください。
- グラスワンダーの血統背景と特徴
- グラスワンダーのデビューまでの歩み
- グラスワンダーの競走成績とレース内容の詳細
- グラスワンダーの名レースBEST5
- グラスワンダーの同世代・ライバルとの比較
- グラスワンダーの競走スタイルと得意条件
- グラスワンダーの引退後の活動と功績
- グラスワンダーのよくある質問(FAQ)
- グラスワンダーの成績表
- グラスワンダーのまとめ
グラスワンダーの血統背景と特徴
グラスワンダーは父Silver Hawk、母Ameriflora、母父Danzigという国際色豊かな配合で、ロベルト系特有の体幹の強さと、ノーザンダンサー系がもたらす瞬時の加速を両立しました。
父系から受け継いだのは骨密度の高さに裏打ちされた持久力と先行持続性能で、厳しいラップを受け続けてもフォームが崩れない点が強みでした。
一方で母系は柔軟性と反応の速さに優れ、道中の“息の入れ方”に長けた自在性を与えました。
2歳時の完成度の高さは気性面の成熟とフォーム再現性の高さの賜物で、稽古と実戦のギャップが小さい“再現可能な強さ”が最大の個性でした。
直線での勝負根性は、ラスト1ハロンでギアをもう一段上げる二枚腰として発現し、接戦で前に出る勝ち切り性能を演出しました。
加えて、馬場・展開を問わずに高水準のパフォーマンスを出せる総合力が、グランプリのような総合力勝負でこそ真価を発揮した要因です。
グラスワンダーの父馬・母馬の戦績と特徴
父Silver Hawkはロベルト直系の重厚なスタミナとしなやかさを兼備し、英ダービー路線で上位を争った実績馬です。
産駒には末脚の持続力に優れ、道悪でもフォームが乱れにくい特質がしばしば見られ、芝中距離で一貫して高い水準を保つ傾向があります。
母Amerifloraは競走実績に恵まれませんでしたが、母父Danzigの強いスピード因子を伝え、肩の可動域が広く、着地時の衝撃を素早く推進力へ転化できる柔らかい前躯をもたらしました。
この父母の資質が噛み合った結果、先行しても差しに回っても“長く脚を使って押し切る”という戦法が可能になりました。
加えて、筋腱の強さと心肺機能の余裕が若駒時から際立ち、休み明けや距離短縮でもブレない再現性を支えました。
血統的には過度なインブリードを避け、アウトブリード傾向の中で機能的なバランスを確保している点も完成度の早さに寄与しています。
グラスワンダーの血統から見る適性距離と馬場
最適レンジは1800~2500メートルで、ワンターンの高速戦から内回りの消耗戦まで幅広く対応しました。
1800~2000メートルでは巡航速度の高さを活かして先行押し切り、2200~2500メートルでは心肺能力とスタミナを前面に押し出す競馬がはまりました。
良馬場で最も信頼度が高く、時計が速いコンディションでも上がり一辺倒にならず、途中からロングスパートをかけて粘り込む芸当が可能でした。
稍重程度までなら踏み込みが深くなってもストライドが縮まず、フォームの再現性が高いためパフォーマンス低下が限定的でした。
展開面ではミドルペースからやや速めで真価を発揮し、3~4コーナーで一気に進出して直線序盤で先頭圏に取り付く設計が最良でした。
この特性は宝塚記念や有馬記念のような心身のタフネスが問われる舞台で特に威力を発揮しました。
グラスワンダーのデビューまでの歩み
米国で生まれ、日本で育成される過程で徹底した基礎付けが施され、放牧地から坂路、ウッドチップでのキャンターに至るまで一貫してフォームの再現性と心肺の強化が図られました。
幼少期から肩の可動域が広く踏み込みが深いフットワークを見せ、早い段階でバランスの良い体型に整っていきました。
調教は速い時計に依存せず、息を入れてから再加速する“実戦型”のメニューが中心で、これが2歳の重賞連勝と3歳以降のロングスパート戦術の土台になりました。
ゲート練習や折り合いの学習もスムーズで、集中力を維持したまま巡航速度を高く保てる特性が育成段階から確認されていました。
こうして迎えた2歳秋の新馬戦(中山芝1800m)を余力十分に快勝し、アイビーS、京成杯3歳S、朝日杯3歳Sへとスムーズに階段を駆け上がりました。
早期完成でありながら奥行きも備え、古馬になっても勝ち切れる“完成の質”がこの時点で既に醸成されていたと言えます。
グラスワンダーの幼少期から育成牧場での様子
放牧地では常に先頭を駆け、他馬を引っ張るリーダー気質を見せました。
筋腱が強く背中が柔らかいため、速いキャンターでも前後の連動が乱れず、一定のピッチで長く走れる資質が際立っていました。
坂路では終い重点の加速を繰り返し学習し、ラスト1ハロンでギアをもう一段上げる感覚を体に染み込ませました。
気性は前向きでスイッチが入りやすい一方、我慢を教えれば素直に従う素性の良さがあり、追い切りでも折り合い面の不安は少ないタイプでした。
調教担当者の所感として“速い時計を出した後でも飼い食いが落ちず、疲労回復が早い”点がしばしば挙げられ、これは本番での連戦連勝を支える重要な素因でした。
育成期から一貫してフォーム動画の確認と微修正が行われ、接地から推進への移行を効率化する“機能的な走り”が確立されていきました。
グラスワンダーの調教師との出会いとデビュー前の評価
尾形充弘調教師は“速さより再現性”を重視し、終い重点での加速を繰り返す内容と、心肺に負荷をかけるロングキャンターを組み合わせて基礎を築きました。
助手・騎手の跨り感は共通して“背中が良く、最後にもうひと伸びする”で一致し、これが後年のグランプリでの勝ち切りに直結しました。
デビュー直前の追い切りは終い12秒前後でまとめるパターンが多く、実戦でも同様の加速曲線を再現できる準備が整っていました。
調整過程での馬体維持も優秀で、負荷を上げても硬さが出にくく、回復の早さがスケジュール面の柔軟性を支えました。
こうして迎えた新馬戦から重賞路線まで、練習通りの走りを“何度でも再現できる”という希少な強さを武器に階段を登っていきました。
グラスワンダーの競走成績とレース内容の詳細
2歳秋は中山の新馬(芝1800m)からアイビーS(芝1400m)を連勝し、続く京成杯3歳S(芝1400m)も危なげなく押し切って重賞初制覇、締めくくりの朝日杯3歳Sでは1分33秒6のレコードで世代頂点に立ちました。
3歳春は骨折で戦列を離れましたが、秋に復帰して毎日王冠5着、アルゼンチン共和国杯6着と試行錯誤ののち、年末の有馬記念で圧巻の復活Vを果たしました。
4歳時は距離短縮の京王杯スプリングCを差し切り、続く安田記念はハナ差の2着、夏の宝塚記念で強豪を3馬身突き放し、秋の毎日王冠、年末の有馬記念連覇まで走り切りました。
5歳春は調整難と故障の影響で勝ち切れませんでしたが、通年を通して見れば“早め進出からの長い脚”という勝ち筋の再現性は極めて高く、名馬の条件である勝負強さを満たしていました。
キャリアの要所要所で強敵と当たり続け、なお勝ち切った点が価値を高めています。
グラスワンダーの新馬戦での走りとその後の成長
新馬戦は中山芝1800mで好位から抜け出し、2着に0.5秒差をつける完勝で素質を誇示しました。
2戦目のアイビーSは東京芝1400m、道中は中団外で息を入れ、直線序盤でスッと加速して先頭へ、1分21秒9の好時計で上がりは34秒0と優秀でした。
3戦目の京成杯3歳Sは東京芝1400mで2番手から楽に抜け出し、1分21秒9で重賞初制覇。ラストまでスピードを落とさない巡航力の高さが際立ちました。
4戦目の朝日杯3歳Sは中山芝1600m、道中で脚を溜めつつ3~4角で進出、直線で一気に抜け出してレコードの1分33秒6。完成度と勝負根性を証明した一戦でした。
この4連勝の共通項は“稽古の加速曲線をそのまま実戦で再現できる”点にあり、以後のキャリアでも状況に応じて同じ勝ち筋を繰り返し描ける強みとなりました。
グラスワンダーの主要重賞での戦績と印象的な勝利
1998年の有馬記念は復帰3戦目での大仕事でした。向正面で徐々に進出し、直線外から押し切って2分32秒1の好時計で古馬一線級をねじ伏せました。
1999年春の京王杯スプリングCは距離短縮にも対応し、中団外から長く脚を使って差し切り。続く安田記念はエアジハードにハナ差及ばず2着でしたが、スピード耐性の高さを示しました。
初対決となった宝塚記念ではスペシャルウィークを直線で3馬身突き放し、総合力の差で完勝。
秋の毎日王冠は好位から早め進出で押し切り、年末の有馬記念はスペシャルウィークとの歴史的なハナ差決着を2分37秒2で制して連覇を達成しました。
距離・展開・馬場をまたいで勝ち切った“万能の強さ”こそ、グラスワンダーを名馬たらしめた核心でした。
グラスワンダーの敗戦から学んだ課題と改善点
3歳秋の毎日王冠(5着)、アルゼンチン共和国杯(6着)は復帰直後で余力配分と距離延長の難しさが露呈し、フォーム維持と反応面に課題を残しました。
4歳春の安田記念は内で脚を溜めたエアジハードにハナ差屈した一戦で、瞬時のギアチェンジ勝負に対する最適化の余地が示されました。
5歳春の日経賞6着、京王杯スプリングC9着は仕上がりと馬体の増減が影響し、ピーク管理とスケジュール設計の難しさを教える結果に。
陣営は以後、勝負所での進出角度とペースコントロールを微調整し、秋の大一番に照準を合わせる“逆算型”の仕上げで安定度を取り戻しました。
敗戦を糧に戦術と調整をアップデートできた適応力こそ、通算成績の質を高めた最大の要因です。
グラスワンダーの名レースBEST5
グラスワンダーの名レース第5位:京王杯スプリングC(1999)
春の始動戦に選んだのは距離短縮の1400m。中団外でリラックスして運び、ラスト3ハロンの入口でスムーズにエンジン点火、長く脚を使って差し切りました。
弾けるというより“スピードを落とさない”加速特性で、直線半ばからの持続力は古馬マイルGⅠ級にも通用する内容でした。
道中の息の入らないラップを受け流しつつ、最後にもう一段の伸びを引き出す二枚腰は、後の安田記念2着にもつながる資質の証明でした。
全体時計1分20秒台前半の高速決着に対応したことは、スピード耐性と器用さの両立を示す重要なファクターでした。
グラスワンダーの名レース第4位:毎日王冠(1999)
秋初戦の1800m戦。好位インで脚を溜め、3~4コーナーで機動的に進出、直線序盤で先頭に並びかけてから二枚腰で押し切りました。
相手はGⅠ常連の強豪揃いでしたが、先行勢を射程に入れてからの持続加速で完封。
“早めに動いて最後まで落とさない”戦法が東京の直線でも有効であることを改めて証明し、年末のグランプリへ向けた地力の高さとメンタルの充実を印象づけました。
この時点で仕上がりは八分ながらも走りの質が高く、総合力で上回る“横綱相撲”の内容でした。
グラスワンダーの名レース第3位:有馬記念(1998)
復帰後の試走を経て挑んだ年末の大一番。向正面でスムーズに加速を開始し、4コーナー外から手応え良く先団へ。
直線で抜け出してからもスピードを落とさず、最後まで二枚腰を保って押し切りました。
勝ち時計2分32秒1は当時としても優秀で、古馬の壁を実力で破った価値の高い勝利でした。
精神的なタフさとフォームの再現性が復帰3戦目で早くも最盛期に近い水準に戻ったことを物語っています。
グラスワンダーの名レース第2位:宝塚記念(1999)
最大のライバルスペシャルウィークとの初対決。スタート後は同馬を射程に入れて追走し、3~4コーナーで馬体を併せるとパワーで押し切って3馬身差の完勝でした。
ペースはミドル~やや速めで、最後までラップを落とさない持続戦。
心肺能力と体幹の強さが問われる阪神内回り2200mで“真っ向勝負に勝つ”という、名馬にふさわしい王道の勝ち方でした。
距離適性とロングスパート性能が最高の形で結実した一戦と言えます。
グラスワンダーの名レース第1位:有馬記念(1999)
歴史的な“ハナ差”決着。スペシャルウィークとの一騎打ちは、直線で完全に並ばれてからなお一完歩伸びる二枚腰で勝負を制しました。
勝ち時計は2分37秒2で時計的には平凡ながら、ラップの厳しさと精神力のぶつかり合いという点で極めて高質なレースでした。
写真判定の末に軍配が上がるほどの接戦を制した勝負根性は、グラスワンダーという馬の本質を最もよく表すものです。
この勝利でグランプリ連覇を達成し、年間二度のGⅠ制覇で“時代の主役”を決定づけました。
グラスワンダーの同世代・ライバルとの比較
同時代にはスペシャルウィーク、同世代外国産ではエルコンドルパサー、上の世代にはサイレンススズカといった怪物級が並び、歴史的な高密度の世代相関を形成しました。
その中でグラスワンダーは中距離での巡航スピードとロングスパートの質で互角以上に渡り合い、特にグランプリ舞台での勝負強さで一歩抜けていました。
瞬発力一辺倒の相手には早め進出で脚を使わせ、逃げ先行型には最後にもう一段の伸びで並び掛ける戦法がハマり、戦術の幅が優位性を生みました。
直接対決の文脈とレーティングの両面から見ても、名馬群の中で“勝ち切る力”という独自の価値を体現しています。
グラスワンダーの世代トップクラスとの直接対決
宝塚記念ではスペシャルウィークに完勝し、年末の有馬記念では同馬との死闘をハナ差で制しました。
3歳秋の毎日王冠ではサイレンススズカの圧倒的逃げに屈しましたが、早めに動いて勝負どころで抵抗した内容は高い評価を受けています。
また、上の世代の強豪メジロブライト、同年の新星テイエムオペラオーらとの力比べでも互角以上に渡り合い、総合力の優位性を示しました。
番組や枠順、馬場差を超えて“勝負所で前へ出る”力が、対強豪戦での最大の強みでした。
グラスワンダーのライバルが競走成績に与えた影響
強敵の存在は調整の質を引き上げ、戦術の明確化を促しました。
具体的には、向正面からのロングスパートを基本線とし、3~4コーナーでの進出角度を一定に保つことで直線序盤での先頭圏確保を再現可能にしました。
ライバル比較の視点では、瞬発型のスペシャルウィーク、逃げ圧殺型のサイレンススズカ、成長曲線型のテイエムオペラオーに対し、グラスワンダーは“持続力でねじ伏せる”という明確な勝ち筋を確立した点が特徴でした。
結果として年間を通じたパフォーマンスの再現性が高まり、混戦のグランプリで最後に前へ出る勝負勘へと結実しました。
グラスワンダーの競走スタイルと得意条件
理想形はスタート後にリズム良く好位~中団へ取りつき、向正面から徐々に加速を開始、3~4コーナーで先頭圏に並びかけるロングスパート型です。
平均~やや速めの流れで強く、直線序盤での二枚腰で押し切る競馬が真骨頂でした。
広いコースでも内回りでも、進出のタイミングと外へ持ち出すコース取りが噛み合えばパフォーマンスは安定します。
良馬場での信頼度が最も高く、稍重程度までならフォームが崩れず、時計のかかる馬場でも対応可能でした。
グラスワンダーのレース展開でのポジション取り
二完歩目の出脚で無理なく隊列の中~前に収まり、道中は折り合い重視で巡航速度を高く維持します。
向正面でじわっとペースアップし、3~4コーナーで馬なりのまま進出して直線入り口で先頭圏へ。
ここでスムーズに進路を確保できれば一気にギアを上げ、最後の50メートルでさらにもう一伸びするのが勝ちパターンです。
ペースが落ち着いた場合でも、早めに動いてロングスパート戦へ持ち込めば総合力で上回れます。
この設計図を何度でも再現できたことが、高勝率とビッグレースでの勝ち切りに直結しました。
グラスワンダーの得意な距離・馬場・季節傾向
ベストは1800~2500m。春は気温の上昇とともに心肺の強さが活き、夏場もコンディションが整えばグランプリ級の走りが可能でした。
秋は休み明けでも能力を出しやすく、仕上がり早の特性が年間設計を助けました。
良馬場で最も信頼度が高い一方、稍重までならストライドが縮まずパフォーマンスの低下が限定的です。
総じて“早め進出からの持続押し切り”がどの季節・馬場でも通用する再現性の高さが、名馬たるゆえんでした。
グラスワンダーの引退後の活動と功績
引退後は種牡馬としてスクリーンヒーロー(ジャパンカップ)、アーネストリー(宝塚記念)、セイウンワンダー(朝日杯FS)などのGⅠ馬を輩出しました。
なかでもスクリーンヒーローからは名マイラー兼中距離王者のモーリスが誕生し、父系の太い枝を形成しました。
産駒は総じて巡航持続力と勝負根性に優れ、接戦で前に出る“二枚腰”を受け継いだタイプが多い点が特徴です。
高齢まで元気に過ごし、2025年8月8日に30歳で逝去。ファンや関係者から多くの追悼の声が寄せられ、功績の大きさを改めて示しました。
グラスワンダーの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
種牡馬成績では、少数精鋭ながらGⅠウイナーを複数送り出し、量より質で強い印象を残しました。
スクリーンヒーローは国際GⅠのジャパンカップを制し、種牡馬としてモーリス(安田記念ほか)を輩出。
アーネストリーは夏のグランプリを完勝し、セイウンワンダーは2歳GⅠを制覇するなど、父譲りの持続力と勝負強さを体現しました。
配合面ではスピード型牝系との相性が良く、ボールドルーラー系やサンデーサイレンス系との組み合わせで中距離の完成度を高める例が多く見られます。
グラスワンダーの産駒の活躍と後世への影響
スクリーンヒーロー-モーリスへ続く強力な父系の枝は、日本の芝マイル~中距離の水準を底上げしました。
接戦での強さとフォームの再現性という遺伝特性は産駒にも共通し、厳しいラップでもパフォーマンスを落とさない血統的武器となっています。
繁殖牝馬としても前向きな気性と体幹の強さを伝え、世代を超えて重賞戦線に影響を残しています。
名と血の両面で長く語り継がれる“礎”を築いたと言えるでしょう。
グラスワンダーのよくある質問(FAQ)
Q. グラスワンダーの主な勝ち鞍は?
A. 朝日杯3歳S、有馬記念(1998・1999)、宝塚記念、毎日王冠、京王杯スプリングC、京成杯3歳Sです。2歳時のレコード勝ちと、古馬になってからのグランプリ二連覇の双方で高い再現性を示した点が評価の核心です。
Q. 得意距離や適性は?
A. ベストは1800~2500mで、良馬場のミドルペース以上で強みを発揮します。
向正面からのロングスパートで直線序盤に先頭圏へ取りつく競馬が最適解で、瞬発力勝負でも消耗戦でも対応できる総合力があります。
Q. 主戦騎手は?
A. 大半のレースで的場均騎手が騎乗し、最後の宝塚記念(2000)は蛯名正義騎手でした。
両騎手とも“最後にもう一伸びする”特性を引き出す騎乗で好結果を残しました。
Q. 代表的なライバルは?
A. スペシャルウィーク、エルコンドルパサー、サイレンススズカ、世代を跨げばテイエムオペラオーなどが挙げられます。
特に1999年の宝塚記念と有馬記念の攻防は、世代の質を示す象徴的な名勝負でした。
Q. 種牡馬としての評価は?
A. GⅠ馬を複数輩出し、父系の枝を作った点で高評価です。
とりわけスクリーンヒーロー→モーリスという継承は、日本の芝マイル~中距離における基準値を押し上げました。
グラスワンダーの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/09/13 | 中山 | 新馬 | 1 | 1 | 的場均 | 芝1800 | 良 | 1:52.4 |
| 1997/10/12 | 東京 | アイビーS | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 |
| 1997/11/08 | 東京 | 京成杯3歳S(GII) | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 |
| 1997/12/07 | 中山 | 朝日杯3歳S(GI) | 1 | 1 | 的場均 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 |
| 1998/10/11 | 東京 | 毎日王冠(GII) | 2 | 5 | 的場均 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 |
| 1998/11/07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 1 | 6 | 的場均 | 芝2500 | 良 | 2:33.5 |
| 1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(GI) | 4 | 1 | 的場均 | 芝2500 | 良 | 2:32.1 |
| 1999/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC(GII) | 1 | 1 | 的場均 | 芝1400 | 良 | 1:20.5 |
| 1999/06/13 | 東京 | 安田記念(GI) | 1 | 2 | 的場均 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 |
| 1999/07/11 | 阪神 | 宝塚記念(GI) | 2 | 1 | 的場均 | 芝2200 | 良 | 2:12.1 |
| 1999/10/10 | 東京 | 毎日王冠(GII) | 1 | 1 | 的場均 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 |
| 1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(GI) | 1 | 1 | 的場均 | 芝2500 | 良 | 2:37.2 |
| 2000/03/26 | 中山 | 日経賞(GII) | 1 | 6 | 的場均 | 芝2500 | 良 | 2:36.3 |
| 2000/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC(GII) | 1 | 9 | 的場均 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 |
| 2000/06/25 | 阪神 | 宝塚記念(GI) | 2 | 6 | 蛯名正義 | 芝2200 | 良 | 2:14.7 |
グラスワンダーのまとめ
グラスワンダーは2歳のレコード勝ちから古馬グランプリ連覇へと続く“再現可能な強さ”で時代を象徴した名馬でした。
父Silver Hawk×母Ameriflora(母父Danzig)の配合が生んだ持続力と反応の両立は、距離や展開、馬場をまたいで通用する普遍性を備えていました。
主要重賞での勝ち切りと接戦で前へ出る勝負勘は一貫しており、グランプリ3連勝という離れ業で“記録と記憶”の双方に名を刻みました。
種牡馬としてもスクリーンヒーローを通じてモーリスへつながる太い父系を築き、競馬の質を高める遺伝的資産を残しました。
30歳で静かに生涯を閉じましたが、その血と物語は今後も競馬ファンの心に生き続けます。