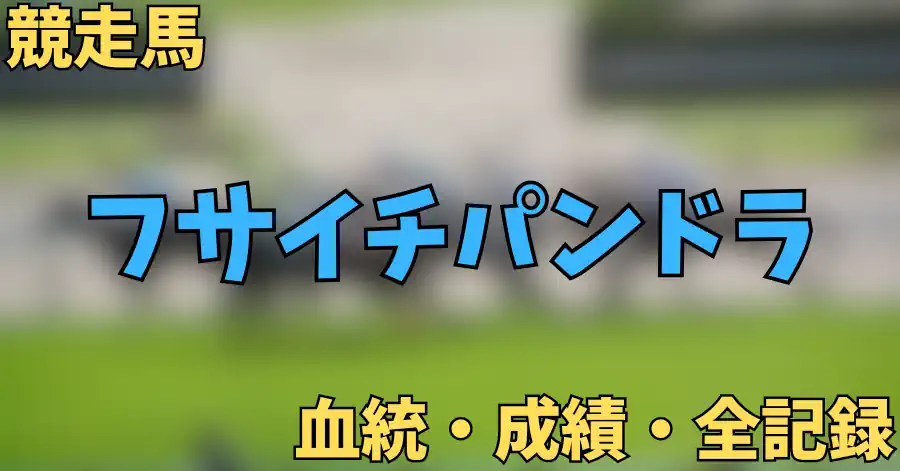フサイチパンドラとは?【競走馬プロフィール】
フサイチパンドラは2006年のエリザベス女王杯を制し、翌2007年には混合の札幌記念で牡馬を相手に勝利した名牝です。
父は日本競馬史を変えた大種牡馬サンデーサイレンスで、同馬はその最終世代として誕生しました。
母ロッタレース、母父ヌレイエフという欧州色の濃い牝系により、柔らかな可動域と持続力を兼備したストライドが武器でした。
現役引退後は繁殖牝馬としてアーモンドアイ(父ロードカナロア)を送り出し、母としても歴史的価値を確立しました。
- 生年月日
- 2003年2月27日
- 性別・毛色
- 牝・栗毛
- 生産
- ノーザンファーム(北海道・早来〈現・安平町〉)
- 調教師
- 白井 寿昭(栗東)
- 馬主
- 関口 房朗
- 通算成績
- 21戦4勝[重賞2勝/GI1勝]
- 獲得賞金
- 3億7811万3000円
- 主な勝ち鞍
- エリザベス女王杯(2006)、札幌記念(2007)
- 父
- サンデーサイレンス
- 母
- ロッタレース(母父:ヌレイエフ)
目次
血統背景と特徴
フサイチパンドラは、父サンデーサイレンス、母ロッタレース(母父ヌレイエフ)という王道配合で、日本の芝に適したしなやかさと欧州的な底力を同居させた血統構成です。
父は日本のサラブレッド改良に絶大な影響を与え、反応の速さと心肺機能の強さを伝える名種牡馬でした。
母系のヌレイエフは、直線でのトップスピードへ“滑らかに移行”する資質と、持続局面でのパワー維持を強化します。
結果として、同馬は長めのストライドでロスなくスピードを保ち、コーナーから直線へかけてギアを段階的に上げる走りが再現性高く発現しました。
牝馬ながら前受けも差しも選べる“自在性”を確保し、厳しい流れでも最後まで脚色を鈍らせない粘着力を併せ持っていました。
繁殖牝馬としてもこのバランスは強く伝わり、代表産駒のアーモンドアイが示した高速域の持続と操縦性は、まさに配合の妙の結晶と言えるでしょう。
父馬・母馬の戦績と特徴
父サンデーサイレンスは名だたる名牝・名牡を世に送り、反応速度と持続力を産駒に広く伝えました。
母ロッタレースは現役実績こそ目立ちませんが、母父ヌレイエフ由来のスピードと柔らかさが配合のキーポイントになりました。
この組み合わせにより、同馬は序盤で力まずに運び、直線で“二段階目の伸び”を引き出すフォームを確立しました。
父系の心肺と体幹の強さに対し、母系は可動域と操作性を補い、ペースが上がってもストライドの質を落とさないのが特徴でした。
実戦では馬群の中でも姿勢が崩れず、進路が開けば確実に加速できる安定感を発揮し、タイトル獲得につながりました。
血統から見る適性距離と馬場
配合とレース内容から、適性の中心は芝2000~2200mの中距離で、外回りの長い直線や小回りの機動戦でも大崩れしない点が強みでした。
良~稍重のスピード持続型コンディションに強く、平均ペース以上のラップ推移でも脚勢を落としにくいタイプです。
一方で極端な超高速上がりの瞬時の切れ勝負では半歩遅れる場面もありましたが、ロスのない立ち回りと早めのギアアップで補える再現性を持っていました。
“切れ×持続”のバランスが取れた王道配合の体現者として、牝馬戦に限らず混合重賞でも通用する総合力を備えていたと言えるでしょう。
デビューまでの歩み
幼少期から育成牧場での様子
フサイチパンドラは北海道早来のノーザンファームで誕生し、幼少期から肩の可動域と背腰の連動性が良い柔らかな歩様を示しました。
当歳時から骨格のバランスが整い、負荷を上げてもフォームが乱れない体質の強さが目を引きました。
坂路・コース併用の育成では、終いで自然にギアをもう一段上げられる“我慢からの再加速”が早くから身につきました。
放牧地でもオンとオフの切り替えが利き、気性面の安定が後の長丁場ローテを支える要素となりました。
こうした素地が、中距離での持続戦と立ち回り勝負の双方に適応できる将来像へ直結し、名牝への階段を静かに上っていきました。
調教師との出会いとデビュー前の評価
管理は栗東の白井寿昭調教師に託され、入厩当初から折り合い面の素直さと追い切りでの反応の良さが評価されました。
併せ馬では控えてラストで抜けるパターンを徹底し、直線での“持続的な伸び”を最大化することに主眼が置かれました。
ゲートの出も安定しており、スタート直後に無理なく好位~中団を確保できるレースセンスは早期からの資質です。
育成から厩舎まで一貫した方針のもと、位置取りの柔軟性とコーナーでの減速幅を抑える技術が磨かれ、完成度の高いデビューへとつながりました。
陣営内の評価は「中距離で早期から結果を出せる万能型」で一致し、のちのG1制覇と混合重賞Vに結び付きました。
競走成績とレース内容の詳細
新馬戦での走りとその後の成長
デビュー後はクラスが上がるほど中距離での地力が際立ち、牝馬路線の要所で常に上位へ顔を出しました。
春のクラシック路線では距離延長や展開の揺れにも対応し、直線での“もうひと伸び”を再現性高く示しました。
夏を越えてもフォームの質が落ちず、秋競馬では外回りでの溜めと小回りでの機動を使い分けられる総合力が確立しました。
経験を重ねるたびに仕掛けのタイミングが洗練され、馬群の中でも姿勢を崩さずに進路を見つける“実戦対応力”が向上しました。
この積み上げが、秋のビッグタイトル獲得へ結実していきます。
主要重賞での戦績と印象的な勝利
最大の勲章は2006年のエリザベス女王杯です。
上位入線を果たす走りの質を示したうえで、直線の進路妨害により1位入線馬が降着となり、フサイチパンドラが繰り上がり優勝を飾りました。
翌2007年は札幌記念で先行から長く脚を使い、牡馬相手の中距離戦を押し切り勝ち。
良馬場での持続戦に強く、小回りでもストライドを乱さず走り切る総合力が証明されました。
さらに2007年のエリザベス女王杯では三冠牝馬ダイワスカーレットに肉薄の2着と健闘し、牝馬路線の中心級として存在感を確固たるものにしました。
敗戦から学んだ課題と改善点
敗れたレースでは、瞬時のギアチェンジが極端に問われた場面で進路確保に時間を要し、末脚の解放が半拍遅れるケースがありました。
また、超高速上がりへの一本勝負になった際は、持続型の脚質ゆえに取りこぼしが生じるリスクも抱えていました。
一方で、道中でのロス削減と4角の“出口作り”を徹底することで課題は逐次解消され、位置取りの柔軟性と再加速の精度が引き上げられました。
総じて、課題のコアは“切れ味そのもの”ではなく“展開対応とコース取り”にあり、経験の蓄積で改善していくタイプでした。
その過程で得られた実戦知見は、のちの混合重賞Vへ直結しています。
名レースBEST5
第5位:2006年 秋華賞(GI・京都2000m)3着
三冠最終戦で見せた内容は、同世代上位の地力を裏づけるものでした。
道中はロスを抑えて折り合い、直線では馬群を割って持続的に伸び続けました。
瞬時の切れ味勝負一辺倒では分が悪い局面でも、最後にもう一段の脚を引き出す再現性が優れていました。
このレースで“中距離の総合力型”としての輪郭がより鮮明になり、のちのG1制覇へ確かな手応えを残しました。
敗戦の中に多くの収穫があった価値ある3着でした。
第4位:2006年 オークス(GI・東京2400m)2着
距離延長の大一番で落ち着いて運び、直線の長い府中でしぶとく脚を使い切りました。
トップスピードへ滑らかに移行する血統的な強みが表れ、ラストまで脚色が鈍らずに2着を確保。
スタミナ面の不安を払拭するとともに、立ち回りと末脚の両立という勝ち筋が明確になりました。
この経験が古馬混合戦での対応力を底上げし、秋以降の成長曲線を一段と引き上げる分岐点になりました。
“王道路線で勝ち負けできる牝馬”としての評価が決定づけられた一戦でした。
第3位:2007年 エリザベス女王杯(GI・京都2200m)2着
三冠牝馬ダイワスカーレットを相手に、正攻法の競馬でクビ差まで迫ったハイレベルな一戦でした。
道中の立ち回りから直線の再加速まで淀みなく、内容面でも胸を張れる走りでした。
勝ち味に一歩届かなかった要因はペース支配の違いにありましたが、持続戦の地力で見劣らなかった点は高評価に値します。
前年のタイトルが偶然ではないことを示し、牝馬路線の一角としての地位を不動のものにしました。
“価値ある2着”として語り継がれる好内容でした。
第2位:2007年 札幌記念(GII・札幌2000m)1着
小回り平坦の舞台で先行からペースを作り、直線は長く良い脚で押し切りました。
ロスの少ないコーナーワークと、外へ持ち出してからの持続的な加速が噛み合い、牡馬混合の格上げ重賞で堂々の完勝。
持続力を核にした“前受けの勝ち筋”を確立し、配合どおりの総合力を証明しました。
夏場でもフォームが崩れない体質の強さもアピールし、秋のビッグレースへ弾みを付ける内容でした。
結果と内容が一致した象徴的な重賞Vです。
第1位:2006年 エリザベス女王杯(GI・京都2200m)1着
直線での進路妨害により1位入線馬が降着となり、フサイチパンドラが繰り上がりでG1初制覇を達成しました。
裁定の是非が議論となった一戦でしたが、上位入線を果たすだけの内容を示していたことが前提にあります。
中団からロスを抑えて進め、勝負所で集中力を切らさずに末脚を伸ばした“勝ち切るための位置”にいたことが勝因でした。
この一冠がその後の混合重賞制覇と繁殖での大成功に直結し、名牝としての評価を決定づけました。
キャリア最大のハイライトです。
同世代・ライバルとの比較
世代トップクラスとの直接対決
同時期にはカワカミプリンセス、近しい世代にスイープトウショウ、翌年には三冠牝馬ダイワスカーレットらがひしめき、牝馬路線のレベルは極めて高い時代でした。
フサイチパンドラは連勝で圧倒するタイプではありませんが、平均以上のラップで“長く脚を使う”勝負で互角以上に戦い抜きました。
外回りの直線勝負でも、小回りの機動戦でもパフォーマンスを維持し、条件に左右されにくい点が強みでした。
接戦の多いハイレベル戦線において、常に勝ち負け圏にいる“堅実さ”は、名牝が並ぶ時代にあっても見劣らない資質でした。
積み重ねた善戦とビッグタイトルの両立が、最終的な評価の高さにつながりました。
ライバル関係が競走成績に与えた影響
強豪と対峙する中で、道中のポジション取りや4角の出口づくりが洗練され、レース運びから無駄が削ぎ落ちていきました。
瞬発力勝負だけでなく、消耗戦や道中のペースアップにも対応し得る“総合力”が磨かれ、接戦をものにする確率が高まりました。
敗戦は課題の可視化に直結し、次走での修正へとスムーズに反映される循環が確立しました。
こうしてビッグレースでの再現性が向上し、タイトル獲得と混合重賞Vという成果へ結びつきました。
ライバルの存在が成長の触媒として機能した好例と言えるでしょう。
競走スタイルと得意条件
レース展開でのポジション取り
理想形は折り合い重視で好位~中団に収まり、3~4コーナーで徐々にギアを上げて直線で長く脚を使う形です。
馬群の中でも姿勢が崩れにくく、進路を確保できれば狭いスペースからでも加速できる器用さがあります。
ハイペースでもスローでも自分のラップに持ち込みやすく、展開不問の安定感が最大の武器でした。
一方、極端な瞬発力勝負ではタイミングひとつで取りこぼす可能性もありますが、立ち回り次第でマイナスを小さくできます。
自在性と持続力のバランスが取れた“王道の差し・先行型”として完成度の高い走りを見せました。
得意な距離・馬場・季節傾向
ベストレンジは芝2000~2200mで、良~稍重の持続戦に強みを発揮します。
小回りでもストライドが乱れず、外回りでは直線で二段階目の伸びを引き出せるのが特徴です。
夏場~秋口にかけて状態の維持が利きやすく、札幌記念の内容に象徴されるようにローカルの機動戦でも真価を発揮しました。
消耗戦と瞬発戦の両方に一定水準で対応できるため、条件替わりや相手強化でも崩れにくい普遍性を備えていました。
配合どおりの“切れ×持続”のハイブリッド型と言えるでしょう。
引退後の活動と功績
種牡馬・繁殖牝馬としての実績
繁殖牝馬として9頭を送り、代表は史上級の名牝アーモンドアイ(父ロードカナロア)です。
ほかにパンデリング(父キングカメハメハ)、ダノンエール(父ハービンジャー)、ユナカイト(父ヨハネスブルグ)、サトノエスペランサ(父ルーラーシップ)などが名を連ね、牝系の厚み形成に寄与しました。
産駒には母譲りのしなやかなストライドと持続性能が色濃く伝わり、適性はマイル~中距離に振れやすい配合傾向を示しました。
“名牝の母”を超えて、現代日本競馬のスピードと持続性の潮流を体現する重要な母系の柱となりました。
産駒の活躍と後世への影響
アーモンドアイは芝G1・9勝を達成し、世界基準の瞬発力と持続力を両立した走りで時代を画しました。
近親では繁殖入りしたパンデリングが母としてのポテンシャルを示し、血脈の価値を世代を跨いで高めています。
同馬の牝系は、スピード型種牡馬との配合でトップスピードと操縦性を、スタミナ型種牡馬との配合で粘着力を上積みしやすい柔軟性があります。
“切れ×持続”の再現性が高く、配合設計のうえでも示唆に富む系統として今後も重視され続けるでしょう。
名牝系の系譜として、日本の王道路線に長期的な影響を与えています。
成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/12 | 5京都3 | 2歳新馬 | 1 | 角田晃一 | 芝1800 | 稍 | 1:48.1 | 新馬勝ち。好位から抜け出す。 |
| 2005/12/04 | 5阪神2 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 3 | 角田晃一 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 2歳牝馬G1で健闘の3着。 |
| 2005/12/25 | 5阪神8 | 2歳500万下 | 3 | 角田晃一 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 直線伸びて3着。地力示す。 |
| 2006/02/04 | 2京都3 | エルフィンS(OP) | 6 | 角田晃一 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 距離短縮で差し届かず。 |
| 2006/02/25 | 2中山1 | きんせんか賞(500万下) | 1 | 角田晃一 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 先行抜け出しで2勝目。 |
| 2006/03/18 | 2中山7 | フラワーC(GIII) | 2 | 角田晃一 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 早め先頭から粘って2着。 |
| 2006/04/09 | 2阪神6 | 桜花賞(GI) | 14 | 角田晃一 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | クラシック初戦は伸び欠く。 |
| 2006/05/21 | 3東京2 | 優駿牝馬(GI) | 2 | 福永祐一 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 長距離で堂々2着。惜敗。 |
| 2006/09/17 | 3中京3 | 関西TVローズS(GII) | 3 | 福永祐一 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 前受けの形で粘り強く3着。 |
| 2006/10/15 | 5京都4 | 秋華賞(GI) | 3 | 福永祐一 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 三冠最終戦で世代上位の地力。 |
| 2006/11/12 | 6京都4 | エリザベス女王杯(GI) | 1 | 福永祐一 | 芝2200 | 良 | 2:11.6 | 進路妨害により繰り上がりG1制覇。 |
| 2006/11/26 | 5東京8 | ジャパンC(GI) | 5 | 福永祐一 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | 世界の強豪相手に善戦の5着。 |
| 2007/02/28 | 川崎 | エンプレス杯(JpnII) | 2 | 福永祐一 | ダ2100 | 良 | 2:16.7 | 交流重賞で堂々の2着。 |
| 2007/03/24 | 3中山1 | 日経賞(GII) | 9 | 福永祐一 | 芝2500 | 良 | 2:33.0 | 中山の持久戦で伸びを欠く。 |
| 2007/04/14 | 2阪神7 | 読売マイラーズC(GII) | 9 | 福永祐一 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 距離短縮で見せ場作れず。 |
| 2007/05/13 | 2東京8 | ヴィクトリアマイル(GI) | 12 | 福永祐一 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 直線で伸び切れず苦戦。 |
| 2007/08/12 | 1札幌2 | クイーンS(GIII) | 5 | 福永祐一 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | 末脚発揮も届かず5着。 |
| 2007/09/02 | 1札幌8 | 札幌記念(GII) | 1 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 逃げ切りで混合重賞V。 |
| 2007/09/17 | 2札幌4 | エルムS(GIII) | 11 | 藤岡佑介 | ダ1700 | 稍 | 1:45.1 | ダート挑戦は厳しく大敗。 |
| 2007/11/11 | 5京都4 | エリザベス女王杯(GI) | 2 | ルメール | 芝2200 | 良 | 2:12.0 | 女王にクビ差。価値ある2着。 |
| 2007/11/25 | 5東京8 | ジャパンC(GI) | 9 | 藤田伸二 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | ハイレベル戦で健闘の9着。 |
| 2007/12/23 | 5中山8 | 有馬記念(GI) | 取消 | 藤田伸二 | 芝2500 | 稍 | — | 出走取消。 |
まとめ
フサイチパンドラは、サンデーサイレンス×ヌレイエフという王道配合が生んだ中距離万能型の名牝です。
2006年のエリザベス女王杯、2007年の札幌記念という性格の異なる舞台で結果を残し、配合どおりの“切れと持続の両立”を走りで証明しました。
繁殖牝馬としてはアーモンドアイを送り出し、母系の潜在力を歴史的スケールで可視化しました。
堅実な地力と器用さ、そして血の強さを兼備した、語り継がれるべき存在です。