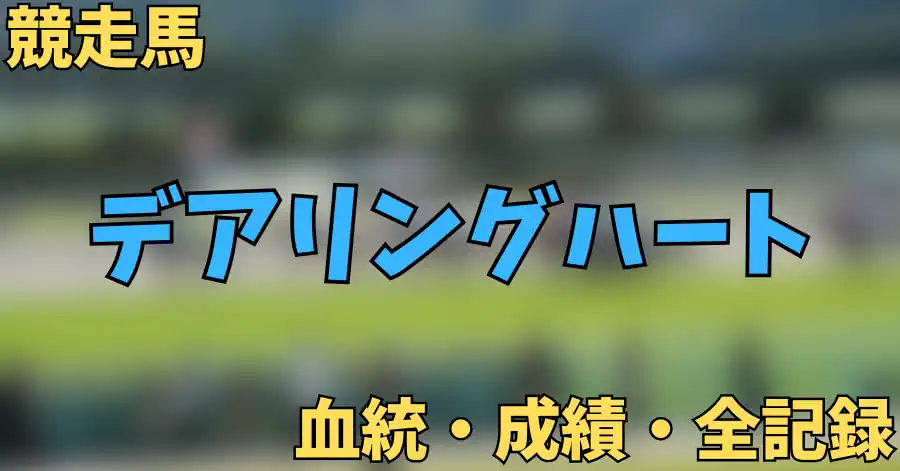デアリングハートとは?【競走馬プロフィール】
デアリングハートは2006年のクイーンステークス、同年と翌2007年の府中牝馬ステークス連覇で名を刻んだ中距離~マイルの実力派牝馬です。
3歳春にはNHKマイルカップで2着、桜花賞で3着と世代上位の走りを披露し、古馬になって完成度を高めながら重賞タイトルをつかみました。
父は日本競馬の基盤を築いた大種牡馬サンデーサイレンス、母は米国産のデアリングダンジグ(母父Danzig)で、反応の速さと持続力を両立する配合でした。
引退後は繁殖牝馬としてデアリングバードを生み、その仔から牝馬三冠馬デアリングタクトが誕生するなど、母系としても重要な位置を占めています。
- 生年月日
- 2002年3月9日
- 性別・毛色
- 牝・栃栗毛
- 生産
- 社台ファーム(北海道・千歳)
- 調教師
- 藤原 英昭(栗東)
- 馬主
- (有)社台レースホース
- 通算成績
- 26戦4勝[重賞3勝/GI0勝]
- 獲得賞金
- 2億7486万2000円(JRA・NAR計)
- 主な勝ち鞍
- 府中牝馬ステークス(2006・2007)、クイーンステークス(2006)
- 父
- サンデーサイレンス
- 母
- デアリングダンジグ(母父:Danzig)
目次
血統背景と特徴
デアリングハートは、父サンデーサイレンス、母デアリングダンジグ(母父Danzig)という王道配合により、スピードの“質”と心肺の“持続”を高次元で両立しました。
父系は反応の速さと勝負所での加速力を、母系は北米スプリント~マイル血脈らしい機動力と推進力を供給し、直線でのトップスピードへ滑らかに移行できるのが最大の強みでした。
ストライドは大きい一方で手前の切り替えが素直で、好位で脚を溜めてからの“二段階目の伸び”が再現性高く出現します。
この性質は1800mの府中牝馬Sや札幌のクイーンSで特に顕在化し、流れに応じて前受けも差しも選べる自在性を裏打ちしました。
配合面のバランスが良く、相手や馬場が変わってもパフォーマンスを大きく落としにくい“総合力型”の資質を色濃く受け継いだと言えます。
父馬・母馬の戦績と特徴
父サンデーサイレンスは瞬時の反応と末脚の持続を産駒に広く伝え、日本の芝で決め手を要する局面に抜群の適性を示す血です。
母デアリングダンジグはDanzig直仔で、スタートの出脚とトップスピード到達までの短さを伝えやすく、コーナーで減速幅を最小化できる操縦性も付与します。
両者の配合により、同馬は序盤で力まずポジションを確保し、道中はフットワークのロスを抑え、直線で長く良い脚を維持する“王道の勝ち筋”を確立しました。
瞬発戦一辺倒ではなく、平均~やや厳しい流れでも脚色を落としにくい点が重賞級の安定感につながりました。
これらの資質は後年、母としての伝達力にもつながり、牝系の価値を高める礎となりました。
血統から見る適性距離と馬場
ベストレンジは芝1600~1800mで、良馬場の高速~平均ペースに強い一方、札幌などやや力の要る馬場でもフォームが崩れにくい耐性があります。
東京や京都の外回りでは溜めてからの持続的な伸びが活き、小回りでは先行して押し切る柔軟性を発揮しました。
極端な超瞬発戦では半拍待たされると取りこぼすリスクがありますが、進路さえ確保できれば二段階目の加速で取り返せるのが同馬の美点です。
総じて、血統段階から“切れ×持続”のハイブリッド型として完成度の高い適性を示しました。
デビューまでの歩み
幼少期から育成牧場での様子
幼少期から肩と背腰の連動性が良く、ピッチとストライドを自在に切り替えられる柔軟な歩様が目を引きました。
基礎期は無理に速い時計を求めず、フォームの安定と呼吸の余裕を優先するメニューで土台を構築しました。
坂路では終い重点、コースでは折り合い重視で、序盤の力みを抑えつつラストでひと脚を長く使う習慣を醸成。
オンとオフの切り替えが利くタイプで、放牧明けでも心身のバランスを崩しにくい体質の強さが光りました。
こうした育成過程が、実戦での“位置を取ってから切れる”競馬につながり、上のクラスで通用する再現性の高い走りを形作りました。
調教師との出会いとデビュー前の評価
管理は栗東の藤原英昭調教師で、入厩当初から気性面の素直さと追い切りでの反応の良さが評価されました。
併せ馬では控えてラストだけ抜けるパターンを反復し、直線での加速を持続させるトレーニングを徹底。
ゲートの出脚が安定しており、スタート直後に無理なく好位~中団を確保できるレースセンスは早期から顕在でした。
デビュー前の評価は「マイル~中距離で上を狙える万能型」で一致し、クラシック路線とマイル路線の両にらみで臨む設計が描かれました。
結果として、世代の大舞台で善戦を繰り返し、古馬になって重賞タイトルを連取する“完成の青写真”どおりの軌跡を歩むことになります。
競走成績とレース内容の詳細
新馬戦での走りとその後の成長
2歳秋の新馬戦で2着と素質を示し、続く未勝利をきっちり勝ち上がって重賞路線へ合流しました。
3歳春はフィリーズレビュー2着、桜花賞3着とマイル適性を裏づけ、続くNHKマイルカップでは古馬顔負けの末脚で2着と大健闘。
夏を越えてもフォームの質を保ち、4歳時には距離1800mでの“溜めてからの持続”が一段と洗練されました。
レースを重ねるごとに仕掛けのタイミングと進路づくりが磨かれ、好位から押し切る形と差す形の両立が可能に。
この積み上げが、札幌と東京での重賞制覇、そして翌年の連覇へとつながります。
主要重賞での戦績と印象的な勝利
2006年のクイーンステークスでは札幌の小回りで先行から粘り、ゴールまで長く良い脚で押し切りました。
秋の府中牝馬ステークスは上がりの速い決着を差し切りで制し、東京1800mでの適性を明確に証明。
2007年の同競走も勝利して連覇を達成し、条件が変わっても崩れない総合力を見せました。
加えて2007年のヴィクトリアマイルでは上がり最速級で3着に食い込み、GIの檜舞台でも堂々の存在感を示しました。
世代戦から古馬混合まで幅広い舞台で安定したパフォーマンスを発揮した点が、同馬最大の価値です。
敗戦から学んだ課題と改善点
瞬発力勝負一極化や進路取りがタイトな状況では、末脚の解放が半拍遅れて取りこぼすケースがありました。
しかし敗戦の度に、4角の“出口作り”と加速開始点の最適化が図られ、直線入口での姿勢と接触リスクの管理が洗練。
先行作と差し作を相手関係に応じて使い分ける戦術理解も深まり、ペースの揺れに対する耐性が向上しました。
総じて、課題の本質は切れ味そのものではなく“展開対応とポジション”であり、経験がそのまま次走の上積みに転化していきました。
その蓄積が重賞3勝という確かな勲章に結実しています。
名レースBEST5
第5位:2007年 ヴィクトリアマイル(GI・東京1600m)3着
マイルGIの舞台で、道中は中団の外を確保しつつ直線で進路を確実に確保。
ラストは上がり33秒台の鋭脚で差を詰め、強豪相手にクビ差まで迫るハイレベルな内容でした。
平均からの瞬発戦という難しい流れでもラストの“もうひと伸び”を引き出し、東京の長い直線で持続性能を最大化。
GIタイトルには手が届きませんでしたが、勝ちに等しい価値のある掲示板確保で、適性の核心を再確認させました。
完成期の地力を示す、堂々たるパフォーマンスでした。
第4位:2005年 NHKマイルカップ(GI・東京1600m)2着
三歳春の大一番で、序盤は折り合いを重視して好位を確保。
直線では狭い間を割って進出し、最後まで長く良い脚を使って2着に食い込みました。
スピードだけでなく、馬群の中でストライドを乱さない“実戦対応力”を証明した価値ある好走です。
世代トップクラスと互角以上に戦える裏付けとなり、のちの重賞制覇へ弾みをつける重要な一戦となりました。
将来像を鮮明にした出世レースでした。
第3位:2006年 府中牝馬ステークス(GIII・東京1800m)1着
速い上がりが要求される東京1800mで、道中はロスの少ない立ち回りから直線で堂々と抜け出しました。
上がり性能と持続力の双方を発揮し、ゴールまで脚色が衰えない“内容で圧倒”する勝ち方。
進路を外に求める冷静な判断と、前を捕らえ切るまでの加速の持続が噛み合いました。
この勝利が翌年の同競走連覇と、牝馬重賞路線での安定感へ直結します。
完成度の高さを示した代表的なベストレースの一つです。
第2位:2007年 府中牝馬ステークス(GIII・東京1800m)1着
前年度覇者として臨んだ一戦で、プレッシャーの中でも落ち着いた運び。
道中は好位で無駄を省き、直線では追われてからの持続的な伸びで後続を完封しました。
同一重賞連覇は再現性の証明であり、ラップの揺れに対する耐性とメンタルの強さを同時に示しています。
操作性に富む配合の利点を最大限に活かし、東京コースでの適性を決定づけた価値ある勝利でした。
王道の手順で掴んだ連覇は歴史的意義が大きい一戦です。
第1位:2006年 クイーンステークス(GIII・札幌1800m)1着
小回りで立ち回りと粘りが同時に問われる札幌1800mで、先行からロスのないコーナーワークを実践。
直線はしぶとく脚を伸ばして押し切り勝ちを収め、配合どおりの“切れ×持続”のバランスを体現しました。
やや力の要る馬場でもフォームが崩れず、ペースが厳しくなってからの粘着力でライバルを寄せ付けませんでした。
この勝利により牝馬重賞戦線の主役級へ浮上し、以後の連覇街道へとつながる決定打となりました。
同馬の強みが最もクリアに現れた金字塔です。
同世代・ライバルとの比較
世代トップクラスとの直接対決
同世代にはラインクラフトやエアメサイアが並び、翌年以降はダンスインザムード、同時期にコイウタ、牝馬路線でアサヒライジングら強敵が揃うハイレベル時代でした。
デアリングハートはマイル~1800mで、位置取りと進路づくりの巧さで互角に渡り合い、僅差の勝負に強い地力を披露。
東京の長い直線では差し脚の持続で、札幌の小回りでは先行押し切りでと、舞台に応じて勝ち筋を変える自在性が際立ちました。
強敵の個性に合わせて自らの戦術を調整し、内容で上回るレースを積み重ねた点が、重賞3勝と数々の善戦へつながりました。
厚みのある直接対決が評価を押し上げたと言えるでしょう。
ライバル関係が競走成績に与えた影響
強豪との対戦は、道中のロス削減と仕掛けのタイミングの精度向上に直結しました。
差す形と前受けの両立が進み、ペースが一定でないレースでもラストの“二段階目”を確実に引き出す技術が醸成。
接戦を繰り返すことで精神面の粘りが強化され、厳しい圏内争いでも集中力が切れにくくなりました。
結果として、年間を通じたパフォーマンスのブレが小さくなり、重賞での安定した走りへ昇華。
ライバルの存在が完成度を押し上げる、好循環の触媒として機能しました。
競走スタイルと得意条件
レース展開でのポジション取り
理想形は折り合い重視で好位~中団に収まり、3~4コーナーで自然にギアを上げて直線で長く脚を使う運びです。
馬群の中でも姿勢が崩れにくく、狭いスペースからでも加速できる器用さがあり、進路さえ確保できれば確実に末脚を解放できます。
ハイペースでもスローでも自分のラップに持ち込みやすく、展開不問の安定感が武器でした。
反面、極端な超瞬発戦で“ひと呼吸の進路待ち”が発生すると取りこぼしの余地は残りますが、早めの進出と出口づくりで補正可能です。
自在性と再現性を兼備した“王道の先行・差し型”です。
得意な距離・馬場・季節傾向
ベストは芝1600~1800mで、良馬場の高速~平均ペースに強く、札幌のようなややスタミナを要す条件でもフォームが崩れません。
東京では直線の長さを活かした二段階加速、小回りではコーナーで減速幅を抑える立ち回りが勝ち筋。
夏場~秋口にかけて状態維持が利きやすく、2006~2007年の重賞Vに象徴される“夏の上積み→秋のピーク”のサイクルがはまりました。
総合力で戦うタイプゆえに、相手強化や条件替わりでも崩れにくい普遍性を備えていました。
配合どおりのハイブリッド型と評価できます。
引退後の活動と功績
繁殖牝馬としての実績
繁殖入り後はデアリングバード(父キングカメハメハ)、ラヴファンシフル(父ハービンジャー)、エターナルハート(父キングカメハメハ)、デアリングウーマン(父ロードカナロア)、オーサムデアラー(父マインドユアビスケッツ)などを送り出しました。
産駒には母譲りのしなやかなストライドと持続性能が伝わりやすく、マイル~中距離で堅実な走りを示すタイプが目立ちました。
配合の振れ幅に対する適応も良く、スピード型種牡馬と組んだ際はトップスピード、スタミナ寄りと組んだ際は粘着力の上積みが期待できる柔軟性があります。
数値上の大物級は限定的ながら、牝系の“伝える力”は確かで、次世代の大輪開花へとつながりました。
母としての存在価値は世代を跨いで高まっています。
産駒の活躍と後世への影響
娘のデアリングバードからは牝馬三冠馬デアリングタクトが誕生し、母系のポテンシャルを歴史的スケールで可視化しました。
これはサンデーサイレンス×Danzigという基盤が、現代日本競馬のスピード持続志向に適合していることの証左でもあります。
以後、この牝系は配合設計上の重要な参照点となり、瞬発と持続のバランスを求める交配において価値を発揮しています。
“走るだけでなく、伝える”という名牝の条件を満たし、後世への影響は今後も継続していくでしょう。
名牝系の柱として長期的なインパクトを残しています。
成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/09 | 4京都1 | 2歳新馬 | 2 | 武幸四郎 | 芝1400 | 稍 | 1:24.8 | 先行粘って素質示す。 |
| 2004/10/30 | 4京都7 | 2歳未勝利 | 1 | 武幸四郎 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 好位抜け出しで初勝利。 |
| 2004/12/05 | 5阪神2 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 5 | 武幸四郎 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 2歳女王決定戦で健闘。 |
| 2005/01/16 | 1京都6 | 紅梅S(OP) | 3 | 武幸四郎 | 芝1400 | 良 | 1:24.4 | 直線伸びて3着。 |
| 2005/02/05 | 2京都3 | エルフィンS(OP) | 6 | 武幸四郎 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 差し届かず。 |
| 2005/03/13 | 1阪神6 | フィリーズレビュー(GII) | 2 | 武幸四郎 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 末脚鋭く2着。 |
| 2005/04/10 | 2阪神6 | 桜花賞(GI) | 3 | Mデムーロ | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 先行粘って表彰台。 |
| 2005/05/08 | 2東京6 | NHKマイルC(GI) | 2 | 後藤浩輝 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 直線鋭伸で惜敗。 |
| 2005/08/14 | 1札幌2 | クイーンS(GIII) | 4 | 後藤浩輝 | 芝1800 | 良 | 1:47.2 | 重賞で内容十分。 |
| 2005/10/16 | 4京都4 | 秋華賞(GI) | 12 | 後藤浩輝 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 流れ向かず。 |
| 2005/10/29 | 4京都7 | スワンS(GII) | 15 | 松永幹夫 | 芝1400 | 重 | 1:22.8 | 道悪で苦戦。 |
| 2006/04/08 | 2阪神5 | 阪神牝馬S(GII) | 12 | Mデムーロ | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 流れ速く脚使えず。 |
| 2006/05/14 | 2東京8 | ヴィクトリアマイル(GI) | 6 | 藤田伸二 | 芝1600 | 稍 | 1:34.6 | 見せ場十分。 |
| 2006/06/11 | 3東京8 | エプソムC(GIII) | 4 | 藤田伸二 | 芝1800 | 重 | 1:49.5 | 道悪でも善戦。 |
| 2006/08/13 | 1札幌2 | クイーンS(GIII) | 1 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1:46.7 | 重賞初制覇。先行押し切り。 |
| 2006/10/15 | 4東京4 | 府中牝馬S(GIII) | 1 | 後藤浩輝 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | 差し切りで重賞2勝目。 |
| 2006/11/19 | 6京都6 | マイルCS(GI) | 13 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 相手強く伸び欠く。 |
| 2007/04/01 | 3中山4 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 6 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 流れに乗るも及ばず。 |
| 2007/05/13 | 2東京8 | ヴィクトリアマイル(GI) | 3 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 豪脚でGI3着。 |
| 2007/06/10 | 3東京8 | エプソムC(GIII) | 9 | 藤田伸二 | 芝1800 | 稍 | 1:49.2 | 見せ場なく。 |
| 2007/08/12 | 1札幌2 | クイーンS(GIII) | 7 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1:47.2 | 前受け粘れず。 |
| 2007/10/14 | 4東京5 | 府中牝馬S(GIII) | 1 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1:45.4 | 府中牝馬S連覇。 |
| 2007/11/11 | 5京都4 | エリザベス女王杯(GI) | 12 | 藤田伸二 | 芝2200 | 良 | 2:13.0 | 距離延長で脚余す。 |
| 2007/12/05 | 船橋 | クイーン賞(JpnIII) | 3 | 藤田伸二 | ダ1800 | 稍 | 1:52.5 | 交流重賞で健闘。 |
| 2008/01/16 | 大井 | TCK女王盃(JpnIII) | 2 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 堂々の2着。 |
| 2008/02/24 | 1東京8 | フェブラリーS(GI) | 7 | 藤田伸二 | ダ1600 | 良 | 1:36.5 | ダートGI挑戦で善戦。 |
まとめ
デアリングハートは、サンデーサイレンス×Danzigという配合が生む“切れと持続の融合”を、芝1600~1800mで高い再現性をもって体現した名牝です。
2006年のクイーンS、2006・2007年の府中牝馬S連覇に象徴されるように、舞台や流れを問わず勝ち筋を描ける自在性が最大の武器でした。
繁殖としても牝系の価値を高め、孫に三冠牝馬デアリングタクトを得たことで、走って伝える“名牝の条件”を満たしています。
結果と内容が一致した“総合力型の手本”として、これから競馬を学ぶ方にも分かりやすい強さのモデルケースと言えるでしょう。