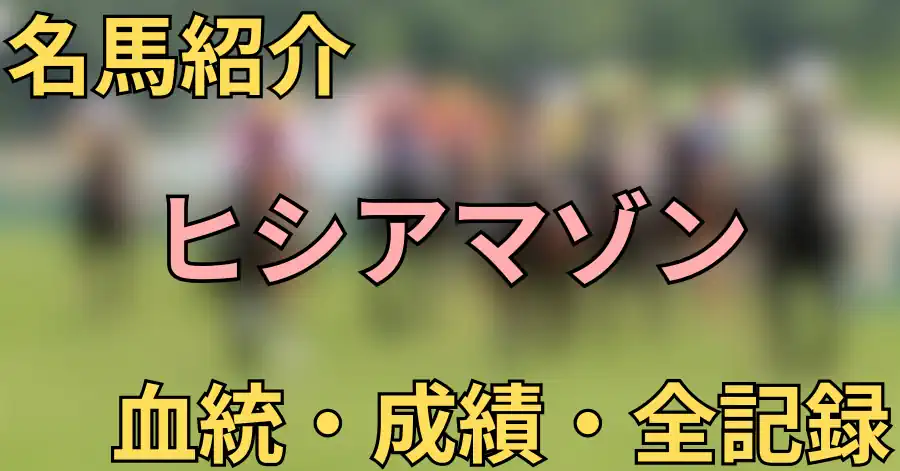ヒシアマゾンとは?【競走馬プロフィール】
ヒシアマゾンは日本競馬の黎明期における外国産牝馬の象徴で、阪神3歳牝馬Sとエリザベス女王杯のG1を制した名牝です。
先行して速い流れを自ら作り、直線で二枚腰を繰り出すロングスパート性能を武器に、牡牝混合の舞台でも臆せず主導権を握りました。
父は北米の芝王者シアトリカル、母は名牝ケイティーズ、母父はノノアルコで、柔らかさと底力を兼備する国際配合です。
通算20戦10勝で重賞9勝、阪神3歳牝馬S(G1)とエリザベス女王杯(G1)に加え、NZトロフィー4歳S(G2)、ローズS(G2)、オールカマー(G2)、京都大賞典(G2)、クイーンC(G3)、クリスタルC(G3)、クイーンS(G3)など多彩な条件で結果を残し、世代屈指の総合力を証明しました。
| 生年月日 | 1991/03/26 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牝・黒鹿毛 |
| 生産 | Masaichiro Abe(米国) |
| 調教師 | 中野隆良/美浦 |
| 馬主 | 阿部雅一郎 |
| 通算成績 | 20戦10勝 |
| 主な勝ち鞍 | 阪神3歳牝馬S(G1)、エリザベス女王杯(G1)、NZトロフィー4歳S(G2)、ローズS(G2)、オールカマー(G2)、京都大賞典(G2)、クイーンC(G3)、クリスタルC(G3)、クイーンS(G3) |
| 父 | シアトリカル(Theatrical) |
| 母 | ケイティーズ(母父:ノノアルコ) |
目次
ヒシアマゾンの血統背景と特徴
父シアトリカルはBCターフ制覇で知られる名芝馬で、柔らかい背中と長い可動域が産駒のストライドに直結します。
母ケイティーズはしなやかな体質と伸縮性を伝える名牝で、牝系は持続力の高い脚質を多く送り出してきました。
この配合によりヒシアマゾンはテンの速さと折り合いの両立、トップスピードへの移行の滑らかさ、直線での粘り腰という三拍子を獲得します。
道中を締め上げても終いが鈍りにくい持久性能が核にあり、先行押し切りのみならず好位差しにも自在に対応できる万能性が光りました。
輸送や連戦にも強いタフネスを備え、牝馬の枠を超えて古馬・牡馬と互角以上に渡り合える資質を血統面から裏付けます。
ヒシアマゾンの父馬・母馬の戦績と特徴
北米芝中距離の名手シアトリカルは、先行して長く良い脚を使える産駒を多数輩出し、体幹の安定と推進力の効率性を伝える種牡馬でした。
産駒の特徴はフォームの崩れにくさで、直線の坂でもラップを落とさず踏み込める点が共通項です。
母ケイティーズは繁殖として傑出した実績を残し、胴伸びと背腰の柔らかさ、気性の前向きさを安定的に次世代へ供給しました。
母父ノノアルコは古典的な欧州スピードを伝え、仕掛けてからの瞬時反応を補完します。
これらが合成されたヒシアマゾンは、序盤から主導権を握りつつも無理なく折り合えるバランスに優れ、直線での持続的な伸び脚に加えて最後のもうひと押しを引き出す底力を備えていました。
血統表全体に硬すぎない質感が並び、道悪や洋芝でもストライドが乱れにくい点も強調材料です。
ヒシアマゾンの血統から見る適性距離と馬場
ベストは芝1600~2400mで、ワンターンのマイルからコーナー4つの中距離まで幅広く対応しました。
テンの2完歩で位置を取り、3角からロングスパートで圧力を掛ける持続力勝負が理想形で、道中でラップを緩めない設計ほど再現性が高まります。
良~稍重の馬場でストライドが崩れにくく、多少の向かい風や内外の不利でも大崩れしないのが長所でした。
一方で極端な瞬発力勝負では切れ負けする懸念があり、ポジション確保と早仕掛けで優位を作るのがセオリーでした。
ヒシアマゾンのデビューまでの歩み
放牧地では後肢の踏み込みが深く、トモの回転の速さと大きなストライドが共存していました。
育成段階では周回での呼吸の安定と坂路での反発力を磨き、単走でも併せでも最後までフォームが崩れない点が高評価でした。
心拍回復が速く負荷を上げやすかったため、早期から高強度の追い切りに耐える土台が整い、ゲートを出てからの2完歩の速さも顕著でした。
遠征や輸送時のテンション管理も良好で、デビュー前からレース当日にパフォーマンスのブレが少ない安定性が確認されました。
こうした素地が、2歳末のG1制覇へ一直線につながっていきます。
ヒシアマゾンの幼少期から育成牧場での様子
幼少期は背中の柔らかさが際立ち、常歩からキャンターへ滑らかに移行できる運動神経を見せました。
育成初期は周回コースでのフォーム固めを優先し、後期は坂路で終い重点のメニューへ移行、心肺機能と筋力の両面を段階的に積み上げています。
併せ馬では相手の動きに合わせつつも最後の1ハロンで自然に抜け出せる競走本能を示し、その際も首差しの使い方に無駄がないのが特徴でした。
脚元のケアを徹底しながらも稽古量をしっかり確保でき、攻め過ぎによる反動が出にくい体質は実戦でも活きました。
結果として、スピードと持久力のバランス、そして実戦での再現性という強みが育成段階でほぼ完成の域に達していました。
ヒシアマゾンの調教師との出会いとデビュー前の評価
中野隆良厩舎は先行して押し切る戦術を主眼に、ゲート~二完歩の加速とコーナーでの減速幅の最小化をテーマに調整しました。
追い切りは終い12秒台でまとめるパターンを繰り返し、負荷を掛けた翌日でも歩様が硬くならない点から強いタフネスが裏付けられました。
助手・騎手の跨り感は共通して「背中が沈み、前向きに進む」タイプで、先行しても掛からないのが最大の美点と評価されます。
デビュー前からオープン級との見立てで、2歳夏から秋にかけてはスピード能力、冬場は持続力強化へと比重を移し、完成度を高めていきました。
こうして迎えた新馬戦は狙い通りの先行押し切りで、以後の重賞戦線で発揮される王道パターンが早くも輪郭を現しました。
ヒシアマゾンの競走成績とレース内容の詳細
デビューは中山ダ1200mの3歳新馬で、好発から楽にハナへ立つと直線で後続を完封しました。
その後はプラタナス賞(500万下)でダート適性を磨き、芝へ戻した京成杯3歳S(G2)で世代上位のスピードを証明します。
阪神3歳牝馬S(G1)は先行から早めに抜け出し、後続に大差を付ける圧巻の内容で2歳女王に輝きました。
古馬・牡馬と当たる機会が増えた以降も、クイーンC、クリスタルC、NZトロフィー4歳S、クイーンS、ローズSと重賞5連勝でエリザベス女王杯へ直行、京都外回り2400mを先行押し切りで制して名牝の座を確定させます。
翌1995年は中距離G2を連勝し、ジャパンCでは独の強豪ランドに次ぐ2着で世界水準の決着へ対応、年末の有馬記念でも見せ場十分と、ハイレベル相手でも崩れない安定感を示しました。
ヒシアマゾンの新馬戦での走りとその後の成長
新馬戦は中山ダ1200m、スタート直後に二完歩で先頭へ、3角まで息を入れずに隊列を決め直線へ向かいました。
最後は手綱を抑えつつも1:13.7で完勝し、持久的なトップスピードを長く維持できる体質をアピールします。
続くプラタナス賞(500万下)はダ1400mで2着ながら、道中で砂を被っても怯まず進める精神面の強さを確認できました。
芝へ戻した京成杯3歳S(G2)では外から長く脚を使って2着、阪神3歳牝馬S(G1)では早め先頭から突き抜けて世代頂点を確定させました。
以後の成長は「道中の締め付けを強めても終いが鈍らない」という方向へ加速し、翌年の重賞連勝につながっていきます。
ヒシアマゾンの主要重賞での戦績と印象的な勝利
1994年のクイーンC(G3)は好位差しで堂々押し切り、クリスタルC(G3)は1200mでもスピード負けしない対応力を見せました。
NZトロフィー4歳S(G2)は向正面から自らペースを引き上げる強気の競馬で、直線は半馬身差の完勝、世代マイル路線の主役に浮上します。
秋はクイーンS(G3)を経てローズS(G2)へ、阪神2000mで先行からねじ伏せる内容で秋の牝馬路線に主導権を確立しました。
エリザベス女王杯(G1)は京都外回り2400mを好位インで運び、4角で外へ持ち出して先頭へ、オークス馬チョウカイキャロルらを押し切る堂々の完勝でした。
1995年はオールカマー(G2)、京都大賞典(G2)を連勝し、ジャパンC(G1)はランドに次ぐ2着、年末の有馬記念でも見せ場を作るなど、一線級相手でも高い持久力と勝負根性を披露しました。
ヒシアマゾンの敗戦から学んだ課題と改善点
1995年の高松宮杯(G2)は中距離での決め手勝負に巻き込まれて5着、直線入口での位置と進路の選択が課題として浮上しました。
ジャパンC(G1)の2着は完璧に運びながらも世界クラスの上がりに僅かに屈したもので、3角からのギアチェンジをさらに早める選択肢が検討されます。
1996年の安田記念(G1)はペースへの適応に苦戦し10着、マイル超高速決着では序盤の行きっぷりに対する負荷が大きいことが明確になりました。
それでも秋のエリザベス女王杯(G1)、有馬記念(G1)では形を作って善戦し、陣営は道中のラップ設計と直線入口での隊列の作り方を再定義することで再現性を高めていきました。
ヒシアマゾンの名レースBEST5
ヒシアマゾンの名レース第5位:NZトロフィー4歳S(G2)
東京マイルで内の好位をすんなり確保し、向正面から息を入れずにペースを引き上げました。
3~4角で外に張らず無駄のないコーナーワーク、直線は楽に先頭へ立ち、最後は半馬身差で押し切る完勝。
序盤から中盤、終盤へと段階的にギアを上げるレース設計がハマり、トップスピードの持続という個性をはっきりと示した一戦でした。
この勝ち方は以後の中距離戦でも再現され、主導権を握って押し切るという勝ち筋を盤石にしました。
ヒシアマゾンの名レース第4位:ローズS(G2)
阪神2000mでスタート直後に先行圏へ、道中は全体のラップを締めながらも折り合い良く進みました。
3角過ぎから進出を開始し4角で先頭射程、直線は内からしぶとく伸びて完勝。
スローバランスに落とさず自らペースを作ることで、鋭い瞬発力型を封じ込める戦術価値を証明しました。
秋の大一番へ向けて、道中から相手をねじ伏せる力業の競馬が最も合うことを確信させる内容でした。
ヒシアマゾンの名レース第3位:有馬記念(G1)
3歳牝馬が挑むには苛烈な中山2500mで、先行して内々をロスなく運ぶ理想のコース取りを実現しました。
勝ったナリタブライアンは歴代屈指の名馬ですが、道中で無理をせず直線で力強く抜け、2着を確保。
長いコースでもフォームが崩れないこと、そして前々で戦いながら終いまで脚色が衰えないことを全国区に示した名走です。
この日を境に、牡牝混合G1でも主役級として評価されるに至りました。
ヒシアマゾンの名レース第2位:阪神3歳牝馬S(G1)
序盤から隊列を締め上げるハイラップを刻みつつ、向正面で息を入れず3角から再加速。
直線は後続を一気に突き放し、5馬身差の圧勝で2歳女王へ。
先行しても掛からない折り合い、トップスピードまでの移行の滑らかさ、そしてラストまで落ちない伸び脚という、のちの代表的勝ち筋が凝縮された一戦でした。
同世代の強豪を一掃したインパクトは、翌年の牝馬路線を牽引する原動力になりました。
ヒシアマゾンの名レース第1位:エリザベス女王杯(G1)
京都外回り2400mで好位インを確保、3~4角で外へ出して進路を確保し、直線半ばで先頭へ抜け出しました。
古馬牝馬勢の追撃を抑え切り、ゴールでは余裕の完勝。
距離延長でもフォームが崩れず、先行して押し切る王道の勝ち方で名牝の地位を不動のものにしました。
条件や展開が変わっても高いパフォーマンスを再現できることを、最も説得力のある形で示した決定打でした。
ヒシアマゾンの同世代・ライバルとの比較
同世代には三冠馬ナリタブライアンが君臨し、古馬にはマヤノトップガン、サクラローレルら強者が並びました。
ヒシアマゾンはマイルから中距離の広いレンジで好位を確保し、早め先頭で押し切る設計により直線特化型を封じ込めることができました。
国際舞台のジャパンCでは独の名馬ランドの2着、日本勢最先着で世界水準の上がりに対応する耐久スピードを示しています。
総合的に見て、局面を自ら作り出せる戦術的主導権が、瞬発力勝負偏重の相手に対する優位を生みました。
ヒシアマゾンの世代トップクラスとの直接対決
有馬記念ではナリタブライアンに屈しつつも2着を確保し、隊列とコース取りの妙で最後まで食い下がりました。
翌年の中距離G2ではアイリッシュダンス、タマモハイウェイら実力馬を撃破、牡牝混合でも勝ち切れるだけの地力を証明しました。
ジャパンCではランドに次ぐ2着で、世界級の決着ラップでもパフォーマンスを落とさないことが裏付けられました。
対戦を重ねるごとに直線入口での位置取りと仕掛けのタイミングが洗練され、勝ち筋の精度が高まりました。
ヒシアマゾンのライバルが競走成績に与えた影響
一線級と当たり続けた経験は、序盤の二完歩、向正面のラップ設計、直線入口のポジショニングなど細部の質を押し上げました。
持久力型のマヤノトップガン、末脚特化のサクラローレルらと渡り合う中で、道中を厳しくして直線で先頭に立つ型が最適解であることが明確になります。
この蓄積が牝馬限定戦では余裕につながり、ローテーションや調整の幅を広げる副次的効果も生みました。
結果として、条件が変わっても崩れにくい再現性が強化され、長期にわたり高いレベルで戦い続ける土台になりました。
ヒシアマゾンの競走スタイルと得意条件
理想は先行からロングスパート、直線入口までに主導権を確立して押し切る展開です。
外枠でも二完歩で位置を取り、3~4角で外へ張らず最短距離を通る操縦性が強みでした。
良~稍重を中心にパフォーマンスが安定し、洋芝や時計の掛かる馬場でもストライドの再現性が高いのが特長です。
刺し馬の決め脚を封じる意味でも、道中を締めて直線で先頭に立つ設計が最適でした。
ヒシアマゾンのレース展開でのポジション取り
スタート直後に先行圏へ入り、最初のコーナーで内目のラインを確保することを最優先とします。
向正面はペースを緩めず、3角から進出して直線入口で優位を作るのが勝ち筋です。
4角で外へ膨らまず最短距離で回る操縦性があり、直線はフォームを崩さずスピードを持続できます。
この「先に動いて先にゴールへ向かう」思想が、消耗戦での優位性に直結しました。
ヒシアマゾンの得意な距離・馬場・季節傾向
距離は1600~2400mが最適で、ワンターンとツーターン双方に高い適性を示しました。
馬場は良~稍重がベストで、道悪でもストライドが乱れにくい柔軟性があります。
季節面では春はスピード寄り、秋は持久力寄りの仕上げでピークを形成でき、シーズンを通じてコンスタントに結果を出しました。
総じて、舞台と展開をコントロールできれば凡走が少ない安定感が魅力でした。
ヒシアマゾンの引退後の活動と功績
引退後は繁殖牝馬として供用され、先行して長く脚を使うタイプを多く伝えました。
大舞台級の大物は限定的ながら、条件~特別での勝ち上がりを安定供給し、母系としての価値を維持しました。
スピード質の高い種牡馬との配合で序盤の行きっぷりが強化される傾向が見られ、マイル~中距離で高い適性を示す産駒が目立ちます。
現役時のレースメイク思想は産駒の戦い方にも影響し、道中から圧力を掛ける主導権型の競馬が得意な系統を形成しました。
ヒシアマゾンの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
産駒はテンの行きっぷりが良く、直線での踏ん張りに長所を示すタイプが多いのが特徴です。
配合の自由度が高く、柔らかな背中と体幹の強さがバランス良く伝わるため、洋芝や道悪にも対応できる個体が育ちました。
勝ち上がりを積み重ねる堅実さが評価され、母系としての安定供給に寄与しています。
繁殖としては長期的に血脈の価値を支える役割を果たし、後世へと連なる基盤作りに貢献しました。
ヒシアマゾンの産駒の活躍と後世への影響
スピード型種牡馬との交配では序盤の加速と直線の持続が強化され、条件戦からオープンまで幅広い舞台で堅実に走るタイプを多く出しました。
育成・戦術面の示唆が系譜内で共有され、道中の締め付けを強めて直線で前に出る戦い方が自然に選択される傾向があります。
大物感の点では控えめでも、配合と育成の妙でポテンシャルを引き出しやすい母系として評価され、血統の持続性に貢献しました。
こうして現役時の資質は、形を変えながら次代へと伝播していきます。
ヒシアマゾンのエピソードとトリビア
外国産馬にクラシック出走制限があった時代に、牝馬ながら牡馬一線級へ挑み続けた姿勢がファンの支持を集めました。
阪神3歳牝馬Sの圧勝からエリザベス女王杯制覇までの流れは、道中を締めて直線で前に出るという一貫した勝ち筋の実証でもあります。
主戦の中舘英二騎手とのコンビはゲートからの二完歩の速さを最大化し、位置取りで優位を築く戦術を徹底しました。
有馬記念での2着、ジャパンCでの2着はいずれも世界水準の決着で、先行力と持続性能の高さが際立った名場面として語り継がれています。
外国産馬ゆえのローテーションと挑戦の軌跡
当時は外国産馬がクラシックに出走できず、春の中心はクイーンC、クリスタルC、NZトロフィー4歳Sという別ルートでした。
それでも勝ち続けることで評価を積み上げ、秋はクイーンS、ローズSを制してエリザベス女王杯へ。
王道路線から外れつつも強豪相手に競り勝った連勝街道は、番組を跨いで適応できる普遍性を示すものでした。
さらに有馬記念で牡馬トップクラスと互角以上に戦った実績は、外国産牝馬の新たな可能性を拓いた意義深いものです。
勝負服と中舘英二騎手のコンビネーション
序盤からの行きっぷりを活かし、道中の緩みを最小化して消耗戦へ誘導するのが中舘騎手のスタイルでした。
ゲート~二完歩の加速を最大化するために、調教段階から体幹の安定とフォーム維持を重視し、直線での伸びを落とさないことに主眼が置かれました。
結果として、先行押し切りという明快な勝ち筋が確立し、相手や条件が変わっても実力を発揮できる再現性が生まれました。
このコンビネーションの強度は、年を跨いだ重賞連勝とG1での好走という形で結実しています。
ヒシアマゾンのよくある質問(FAQ)
Q. 主な勝ち鞍は?
A. 阪神3歳牝馬S(G1)、エリザベス女王杯(G1)のG1に加え、NZトロフィー4歳S(G2)、ローズS(G2)、オールカマー(G2)、京都大賞典(G2)、クイーンC(G3)、クリスタルC(G3)、クイーンS(G3)です。
世代牝馬に留まらず、牡牝混合中距離のG2で連勝し、ジャパンC(G1)では日本馬最先着の2着と世界水準の実力を示しました。
Q. ベストの適性距離は?
A. 芝1600~2400mのレンジが最適で、先行からロングスパートで押し切る戦術が最も再現性の高い勝ち筋でした。
良~稍重の馬場でストライドが乱れにくく、道中を締める設計ほど安定感が増すタイプです。
Q. 代表的なライバルは?
A. ナリタブライアン、マヤノトップガン、サクラローレル、同世代牝馬ではチョウカイキャロル、海外ではランドが挙げられます。
強豪が顔をそろえた時代にあって、位置取りとラップ設計で優位を作る戦略性で互角以上に渡り合いました。
ヒシアマゾンの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/09/19 | 中山 | 3歳新馬 | 1 | 1 | 中舘英二 | ダ1200m | 良 | 1:13.7 |
| 1993/10/24 | 東京 | プラタナス賞(500万下) | 3 | 2 | 江田照男 | ダ1400m | 良 | 1:26.3 |
| 1993/11/13 | 東京 | 京成杯3歳S(G2) | 6 | 2 | 中舘英二 | 芝1400m | 良 | 1:22.9 |
| 1993/12/05 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 2 | 1 | 中舘英二 | 芝1600m | 良 | 1:35.9 |
| 1994/01/09 | 中山 | 京成杯(G3) | 1 | 2 | 中舘英二 | 芝1600m | 良 | 1:34.2 |
| 1994/01/30 | 東京 | デイリー杯クイーンC(G3) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝1600m | 良 | 1:35.3 |
| 1994/04/16 | 中山 | クリスタルC(G3) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝1200m | 良 | 1:08.5 |
| 1994/06/05 | 東京 | NZトロフィー4歳S(G2) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝1600m | 良 | 1:35.8 |
| 1994/10/02 | 中山 | クイーンS(G3) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝2000m | 稍重 | 2:02.9 |
| 1994/10/23 | 阪神 | ローズS(G2) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝2000m | 良 | 2:00.0 |
| 1994/11/13 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝2400m | 良 | 2:24.3 |
| 1994/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 6 | 2 | 中舘英二 | 芝2500m | 良 | 2:32.7 |
| 1995/07/09 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 1 | 5 | 中舘英二 | 芝2000m | 良 | 2:03.0 |
| 1995/09/18 | 中山 | オールカマー(G2) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝2200m | 稍重 | 2:16.3 |
| 1995/10/08 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 1 | 1 | 中舘英二 | 芝2400m | 良 | 2:25.3 |
| 1995/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 2 | 2 | 中舘英二 | 芝2400m | 良 | 2:24.8 |
| 1995/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 1 | 5 | 中舘英二 | 芝2500m | 良 | 2:34.6 |
| 1996/06/09 | 東京 | 安田記念(G1) | 4 | 10 | 中舘英二 | 芝1600m | 良 | 1:33.9 |
| 1996/11/10 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 5 | 7 | 中舘英二 | 芝2200m | 良 | 2:14.3 |
| 1996/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 5 | 5 | 河内洋 | 芝2500m | 良 | 2:35.0 |
ヒシアマゾンのまとめ
先行からロングスパートに持ち込み、道中の締め付けで主導権を握る王道パターンで大舞台を制した名牝です。
柔らかな可動域と体幹の強さに裏打ちされた持久性能は、牡牝混合の一線級相手でもブレずに力を出せる安定感へ直結しました。
G1での圧勝と世界水準の好走を両立し、配合・育成・戦術の三位一体で完成した万能型として記憶されます。
総括すれば、舞台設定とラップ設計で優位を築き続けたのがヒシアマゾンの真骨頂でした。