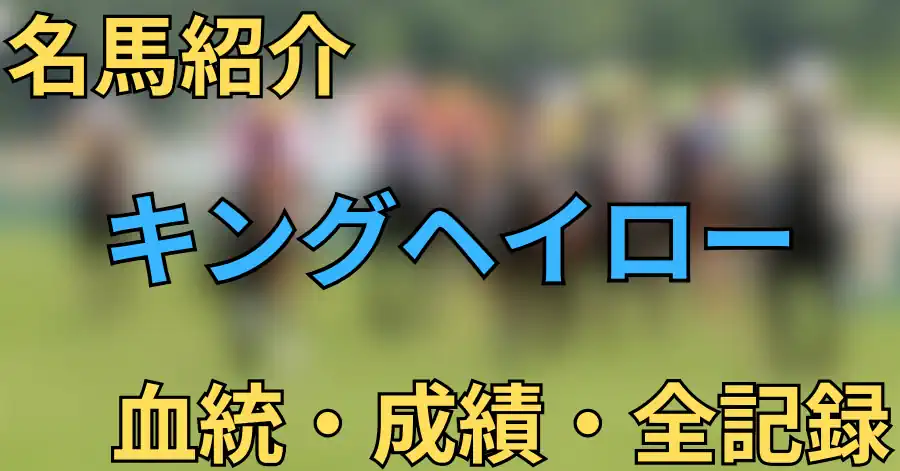キングヘイローとは?【競走馬プロフィール】
キングヘイローは欧州最強級の父と米国の名牝を両親に持つ超良血で、日本の短距離〜マイル戦線において個性と存在感を放った名馬です。
クラシック期は皐月賞2着、日本ダービーで大敗を喫しましたが、古馬で距離適性を再定義し、2000年の高松宮記念で悲願のG1初制覇に到達しました。
同世代のスペシャルウィーク、セイウンスカイ、古馬のグラスワンダー、のちの覇者テイエムオペラオーら強敵と伍し、戦術の幅と精神力で常に上位争いを演じました。
引退後は種牡馬・母父としても短距離・ダート路線の層を厚くし、配合面でも指標となる存在です。血統背景と適性転換の巧みさがキャリアの核でした。
| 生年月日 | 1995/04/28 |
|---|---|
| 性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
| 生産 | 協和牧場(北海道新冠) |
| 調教師 | 坂口正大/栗東 |
| 馬主 | 浅川吉男 |
| 通算成績 | 27戦6勝 |
| 主な勝ち鞍 | 高松宮記念(G1)、中山記念(G2)、東京新聞杯(G3)、東京スポーツ杯3歳S(G3) |
| 父 | ダンシングブレーヴ |
| 母 | グッバイヘイロー(母父:Halo) |
目次
- 1 目次
- 2 キングヘイローの血統背景と特徴
- 3 キングヘイローのデビューまでの歩み
- 4 キングヘイローの競走成績とレース内容の詳細
- 5 キングヘイローの名レースBEST5
- 6 キングヘイローの同世代・ライバルとの比較
- 7 キングヘイローの競走スタイルと得意条件
- 8 キングヘイローの引退後の活動と功績
- 9 キングヘイローの2000年高松宮記念の価値と戦術的意義
- 10 キングヘイローの配合傾向と短距離・ダート適性の継承
- 11 キングヘイローの東京スポーツ杯3歳Sレコードの意味と評価
- 12 キングヘイローの脚質転換プロセスとローテ最適化
- 13 キングヘイローのよくある質問(FAQ)
- 14 キングヘイローの成績表
- 15 キングヘイローのまとめ
目次
本記事では血統背景、デビューまでの歩み、主要重賞を含む競走成績の推移、名レースBEST5、同世代比較、競走スタイル、引退後の歩みを順に解説します。
重要語句は赤マーカーで強調し、馬名は青マーカーで示します。
必要に応じて目次から各章へ移動し、知りたいトピックをピンポイントでご覧ください。
- キングヘイローの血統背景と特徴
- キングヘイローのデビューまでの歩み
- キングヘイローの競走成績とレース内容の詳細
- キングヘイローの名レースBEST5
- キングヘイローの同世代・ライバルとの比較
- キングヘイローの競走スタイルと得意条件
- キングヘイローの引退後の活動と功績
- キングヘイローの2000年高松宮記念の価値と戦術的意義
- キングヘイローの配合傾向と短距離・ダート適性の継承
- キングヘイローの東京スポーツ杯3歳Sレコードの意味と評価
- キングヘイローの脚質転換プロセスとローテ最適化
- キングヘイローのよくある質問(FAQ)
- キングヘイローの成績表
- キングヘイローのまとめ
キングヘイローの血統背景と特徴
父は欧州の歴史的名馬ダンシングブレーヴ、母は米国でG1を7勝した名牝グッバイヘイローという、世界的な名血同士の黄金配合です。
父系からはトップスピードへの到達が速い反応と高い巡航速度、直線での姿勢制御の巧さが伝わり、母系からは勝負所での闘争心とラストにもう一段伸びる持続力が補強されました。
肩の可動域が広い前躯と柔らかな背中によりストライドは大きく、コーナーで減速幅が小さいため直線入口で自然に速度が乗るのが特長です。
若駒期に中距離で質を示しつつ、完成が進むにつれて短距離〜マイルでの再現性が上がったのは、血統的に瞬発力と持続力を高い次元で両立できた結果といえます。
総じて、名血のシナジーが機動力と直線の推進力を後押しし、王道路線からスプリントまで横断可能な基礎性能を形成しました。
キングヘイローの父馬・母馬の戦績と特徴
父ダンシングブレーヴは凱旋門賞を含む欧州の大舞台を席巻した歴史的名馬で、産駒には柔らかな背中と高速巡航を長く維持できる資質を伝えます。
母グッバイヘイローは米国でG1・7勝の名牝で、タフなローテでも崩れにくい気質と、馬群を割る時の推進力が武器でした。
母父Haloは瞬時の反応と闘争心を産駒に授け、出脚と二完歩目の加速を後押しします。
この三層構造がキングヘイローにおける『道中は我慢、直線はロングスパート』という勝ち筋を下支えし、位置取りと進路確保の選択肢を広げました。
結果として速い流れでも遅い流れでも末脚を鈍らせにくく、舞台替わりへの適応力が高いという、現代競馬で価値の高い特性が揃いました。
評価軸は名血、遺伝力、再現性の三点です。
キングヘイローの血統から見る適性距離と馬場
血統的な適性レンジは1200〜2000で、完成後の最大値は1200〜1600にあります。
理想は3角手前からの一貫加速で、直線入口の減速幅を小さくし、上がり11台が並ぶ持続戦で真価を発揮します。
コースは東京のワンターンや中京の平坦、京都外回りで強みが出やすく、中山の4角勝負でも手前替えの速さで減速を抑制できます。
馬場適性は良〜稍重で安定し、重でも極端に指数が落ちにくい耐性を示しますが、極端な力の要る馬場では直線のギアがわずかに鈍ります。
まとめると、距離短縮適性、ロングスパート適性、道悪耐性がキーワードで、戦術設計と相性が良好でした。
キングヘイローのデビューまでの歩み
幼少期から背腰の強さと重心移動の滑らかさが目立ち、放牧地でも群れの中でバランスよく走れる直進性を備えていました。
育成初期は直線主体のキャンターで心肺機能を養成し、坂路では序盤我慢・終い重点のメニューで『粘った後にもう一段』の伸びを体得します。
ゲートでは二完歩目の加速が速く、実戦でも無理なく好位〜中団を確保できるため、道中で息を入れて直線で爆発力を引き出せました。
調整過程は負荷と回復のサイクルが明確で、追い切り後の回復が早い体質は連戦でもパフォーマンスを落としにくい利点となりました。
その結果、新馬→黄菊賞→東京スポーツ杯3歳Sと一気に重賞まで駆け上がり、若駒離れした完成度でクラシック候補へ名乗りを上げています。
総合すると、早期からの完成度、高い再現性、そして調整の柔軟性が、キャリアの飛躍を生みました。
キングヘイローの幼少期から育成牧場での様子
放牧ではトモの可動域が広く、踏み込みの深さが推進力へ直結していました。
基礎期は直線ウッドで12〜13のラップを安定して刻み、心拍の戻りが早い『タフな体質』が育成スタッフの高評価に繋がります。
中盤以降は坂路でビルドアップ、ラスト1Fで自然に加速できるフォームを固め、左右回りでも外へ張らずに真っ直ぐ走れる直進性を獲得しました。
実戦を想定し、コーナーでの重心移動と手前替えを繰り返し練習することで、直線入口の減速を最小化する技術が早期に身につきました。
これらの積み重ねがデビュー直後の連勝、そして年内の重賞制覇に直結し、弱点の少ない完成形へと近づいていきます。
キーワードは基礎体力、機動力、回復力です。
キングヘイローの調教師との出会いとデビュー前の評価
坂口正大厩舎は、週半ばの終い重点と週末の回復重視を軸にしたリズムで、過負荷を避けつつ瞬発のキレを磨く調整を施しました。
助手やジョッキーの跨り感は『背中が柔らかい』『自分で前へ進む』で一致し、追ってから止まらない持続を高く評価しています。
ゲートは素直で、二完歩目の加速で自然に好位へ取りつけるため、戦術の幅が広く、距離や展開が変わっても崩れにくいのが強みでした。
評価はデビュー前から主役級で、クラシックを見据えつつも短距離〜マイルの資質を並行して確認する柔軟な方針が採られ、適性の最適化へ滑らかに移行できました。
総括すれば、厩舎の調整力と馬の学習能力が高い次元で噛み合い、早期完成と将来の適性転換を両立させたと言えます。
キングヘイローの競走成績とレース内容の詳細
新馬→黄菊賞→東京スポーツ杯3歳Sを3連勝で突破し、年末のラジオたんぱ杯3歳Sは2着と地力を誇示しました。
弥生賞3着、皐月賞2着と王道路線で強豪と互角に渡り合い、日本ダービーは馬場と展開のミスマッチで14着と大敗しましたが、秋は神戸新聞杯3着、京都新聞杯2着、菊花賞5着と巻き返して素質の高さを裏付けます。
古馬になると距離短縮で適性を最適化し、1999年は東京新聞杯・中山記念を連勝、秋は毎日王冠から天皇賞(秋)を経てマイルCS2着、スプリンターズS3着と短距離〜マイルで存在感を強めました。
2000年はフェブラリーSでダートを試した後、高松宮記念で悲願のG1初制覇、続く安田記念3着、有馬記念4着まで走り切り、年間を通じて高い下限値を維持しています。
通算27戦で6勝、重賞4勝という数字以上に、相手・舞台・流れが変わっても崩れにくい再現性と失敗からの修正力がキャリアの価値を押し上げました。
キングヘイローの新馬戦での走りとその後の成長
京都の3歳新馬は稍重でも出脚が良く、外から好位確保。
道中は無理をせずリズムを刻み、直線で外に持ち出すと余力十分に抜け出して1着でした。
黄菊賞は最後方近くからインで溜め、直線で馬群を割って伸び切る内容で、若駒ながら進路取りの巧さが際立ちました。
続く東京スポーツ杯3歳Sは道中で一切の無駄を排して先頭へ、ラストまで加速し続ける一貫ラップを押し切ってレコード勝ち。
年末のラジオたんぱ杯3歳Sは2着でしたが、立ち回りの確かさと終いのしぶとさは維持され、春への課題と収穫を両取りしています。
この一連で『先行押し切り』『差し切り』『ロングスパート』の複線化が進み、春のクラシックでの安定走へ直結しました。
キーワードは完成度、学習曲線、進路確保です。
キングヘイローの主要重賞での戦績と印象的な勝利
皐月賞は先行して渋太く伸び2着、日本ダービーは稍重と展開の逆風で大敗するも、秋のトライアル〜菊花賞で地力を再確認しました。
古馬初期の東京新聞杯、中山記念の連勝は、直線入口の減速を抑えるコース取りと、追ってから止まらない巡航性能の融合で、いずれも最後の200で『もう一段』伸びています。
1999年秋はマイルCS2着、スプリンターズS3着と短距離・マイルのG1で互角以上に戦い、適性の最終解が見えてきました。
そして2000年の高松宮記念は中団外からスムーズに進出、直線は狭いスペースを割って力強く抜け出し、悲願のタイトルを手中に収めました。
安田記念3着、有馬記念4着も含め、距離と舞台を跨いで結果を残した多面性は特筆に値します。
総じて、勝負強さと機動力が光るキャリアでした。
キングヘイローの敗戦から学んだ課題と改善点
日本ダービーの大敗は道中での位置取りのロスと馬場適性のズレが複合し、直線入口で大きく減速したのが主因でした。
菊花賞はスロー瞬発戦で外を回らされる展開が響き、持続型の長所を最大化できませんでした。
一方で臨戦過程の修正が早く、古馬では距離短縮とコース取りの最適化で安定ゾーンに収束、秋のマイルCS2着やスプリンターズS3着へと繋がっています。
失敗を要素分解して次走へ反映するプロセスが確立しており、年間を通して下限値が高いのが強みでした。
要するに、修正力と適応力こそが名馬の証でした。
キングヘイローの名レースBEST5
キングヘイローの名レース第5位:東京新聞杯(G3)
中距離からの距離短縮で臨んだ東京マイルは、ミドルペースで淡々と流れる持続戦でした。
序盤は無理に位置を取りに行かず中団で折り合い、向こう正面で外3列目へスライド、3〜4角でじわっと進出して加速の助走を確保します。
直線は馬群の外を選び、手前替えと同時にトップスピードへ移行すると、ラスト200でもう一段伸びて完勝。
ラップは11台が並ぶ持続質で、直線入口の減速幅を最小化できたことが勝因でした。
距離適性の再定義に成功し、そのまま中山記念連勝、秋のマイルCS2着へと繋がる重要な分岐点となりました。
ここで確立した『直線入口で減速しない』『再加速を引き出す』という勝ち筋が、以後の王道路線と短距離路線を横断する礎になりました。
キングヘイローの名レース第4位:中山記念(G2)
東京新聞杯からの連勝を狙った中山1800は、コーナー4回の機動力勝負。
1コーナーで内に潜ってロスを抑え、向こう正面で外の3列目へスイッチ、4角出口で手前替えをスムーズに行って加速の助走を取りました。
直線は内のスペースを最短距離で抜け、最後まで減速せずに押し切り。
起伏が大きいコース形状で持続型の強みを最大化し、進路確保とコース取りの質が勝敗を分けることを証明しました。
春競馬の主役へと躍り出たターニングポイントであり、以後の短距離〜マイル路線での主軸化に直結する内容でした。
キングヘイローの名レース第3位:マイルチャンピオンシップ(G1)
秋の京都外回りはスピードの持続が問われる舞台。
中団やや前で運び、3〜4角で外へ持ち出しつつジワッと加速、直線では長いフットワークでゴールまで伸び続け2着に好走しました。
勝ち馬が強力な中、最後まで止まらない巡航性能を高いレベルで示し、G1級の地力を明確に証明。
以後のスプリント寄りローテにも好影響を与え、適性転換の正しさを裏付けるレースになりました。
ハイレベルな持続戦で見せた総合力と勝負強さが評価点です。
キングヘイローの名レース第2位:安田記念(G1)
世界レベルのマイラーが集う東京1600で3着。
序盤は折り合いに専念し、直線で馬場の良い外へスムーズに進路を確保すると、長いフットワークで伸び続けました。
前後半がほぼイーブンの国際標準ラップで、直線入口のロスを抑え、被されないラインを選べたことが結果に直結。
短距離〜マイルの二刀流としての資質を再確認し、秋のG1戦線へ向けた重要な布石となりました。
一貫ラップで崩れない再現性と適応力が凝縮された好走です。
キングヘイローの名レース第1位:高松宮記念(G1)
11度目のG1挑戦でついに掴んだ初タイトル。
中団外で脚を温存し、3〜4角で外へ持ち出しながら加速、直線は馬群の狭いスペースを割ってから長いフットワークで先頭へ躍り出ました。
勝負所での加速の助走が完璧で、残り200でもう一段伸びる理想形を体現。
距離短縮と進路確保の最適解を同時に満たした会心の一撃で、適性の最終解が確定した瞬間でした。
スプリント路線での地力証明と戦術完成が重なった、キャリアのハイライトです。
キングヘイローの同世代・ライバルとの比較
世代の主役はダービー馬スペシャルウィークと二冠馬セイウンスカイで、前者は直線の持続と総合力、後者は主導権を握る機動力が武器でした。
キングヘイローはその中間に位置し、展開と進路取りで勝ち筋を作るタイプで、相手が強いほど内容で食い下がる傾向があります。
古馬になるとグラスワンダー、のちにはテイエムオペラオーら最強クラスとも対峙し、マイル〜中距離で互角以上の内容を何度も示しました。
一貫ラップの消耗戦と直線の瞬発戦の双方に対応できるため、年間を通じて大崩れが少ないのが特徴でした。
総合して世代比較と適応力の観点で高評価が妥当です。
キングヘイローの世代トップクラスとの直接対決
皐月賞ではセイウンスカイの主導権に屈したものの、直線でしぶとく伸びて2着を確保しました。
日本ダービーは馬場と展開に泣きましたが、秋のトライアル〜菊花賞で地力を再確認しています。
古馬混合のG1でもマイルCS2着、安田記念3着と安定感を示し、スペシャルウィークやグラスワンダー相手にも内容で見劣らない走りを披露しました。
舞台ごとに最適解を選べるのが強みで、対戦相手の個性に応じて戦術を切り替える柔軟性が勝率を押し上げました。
直接対決の文脈で価値が際立ちます。
キングヘイローのライバルが競走成績に与えた影響
明確な個性を持つライバルの存在は、進路取りの精度と仕掛けのタイミングを研ぎ澄ましました。
セイウンスカイの主導権、スペシャルウィークの持続、グラスワンダーの瞬発へ対処する過程で、4角で勝負を決め切る技術が成熟しています。
厳しい相手と当たり続けた経験は精神面の安定にも寄与し、混戦でも慌てずに進路を選べる胆力を養いました。
挑戦と修正の積み重ねが年間の指標を安定させ、最終的にG1タイトルへ到達する原動力になりました。
相互作用による相乗効果と経験値が鍵でした。
キングヘイローの競走スタイルと得意条件
基本形は道中で脚を溜め、3〜4角でじわっと加速しながら外へ進路を確保、直線はロスなくトップスピードへ乗せる戦い方です。
被されても怯まない精神力があり、馬群の『隙間』を突いて抜けるのが得意で、直線入口の減速幅が小さいためラスト200でさらに再加速できます。
馬場は良〜稍重でブレが小さく、重でも極端に下がらない耐性があり、距離は1200〜1600が最適。
展開はミドル〜ハイの一貫ラップに強みを持ち、前半で無理をしない分だけ終いの粘りが効く設計です。
総合して、ロングスパート、進路確保、再現性の3要素が勝ち筋の核でした。
キングヘイローのレース展開でのポジション取り
スタート直後は出脚の速さを活かして無理なく好位〜中団を確保します。
向こう正面で外3列目へスライドして加速の助走を取り、4角出口で手前替えと同時に外へ持ち出すと、減速せずトップスピードへ移行できます。
密集隊列では早めに『出口』を用意する意識が重要で、直線入口までに外1頭分のスペースを確保できれば最後の200で更に伸びます。
こうした準備動作の質が接戦での勝負強さを生み、際どいゴール前で優位に働きました。
鍵語は位置取りとコース取りです。
キングヘイローの得意な距離・馬場・季節傾向
ベストは1200〜1600で、2000でも対応可能ですが最大値は短縮戦にあります。
春は仕上がりが早く、高速〜標準の時計域で安定、夏は一息入れて秋に向けて再ピークを作るサイクルが理想的でした。
馬場は良〜稍重で高い再現性を示し、重では直線のギアがわずかに鈍るため、直線入口のロスを減らすコース取りが有効です。
ターゲットの2〜3走前からビルドアップし、追い切りは終い重点で『減速しない直線入り』を体に覚え込ませるのが好適でした。
評価軸は距離適性と季節適性です。
キングヘイローの引退後の活動と功績
種牡馬としては短距離〜ダート寄りの推進力と気持ちの強さを伝え、地方・中央を問わず重賞ウィナーを多数輩出しました。
生粋のスプリンターからマイラー、ダートの先行型まで幅広く、配合次第で距離の融通が利く万能性が特徴です。
母父としても背中の柔らかさと直線での『もう一段』を供給し、配合設計の幅を広げました。
総合して、現代日本競馬の短距離〜マイル路線を底上げした血統的貢献は大きく、長期的な影響が続いています。
キーワードは万能性と継承力です。
キングヘイローの種牡馬・繁殖牝馬としての実績
産駒は芝・ダート双方で勝ち上がり、地方の交流重賞でも多数のタイトルを獲得しました。
スプリントでは先行して粘るタイプ、ダートでは推進力で押し切るタイプが多く、調教耐性の高さも共通項です。
配合ではスピードの持続を補うサンデー系や、体幹の強さを補う米国型パワー血統と好相性で、距離レンジの拡張に寄与しました。
母の父としても直線での『もう一伸び』を伝え、重賞級の素質馬を複数輩出しています。
評価の中心は適応力と遺伝力です。
キングヘイローの産駒の活躍と後世への影響
地方重賞でのタイトル獲得が多く、交流路線の厚みを作った意義は小さくありません。
短距離戦の平均水準を引き上げ、世代を超えて『直線で止まらない』特性を伝えることで、番組全体の質の底上げに貢献しました。
今後も母父としての価値が維持・上昇していく可能性が高く、配合設計における選択肢を広げる存在であり続けるでしょう。
血の広がりという観点で、長期的な持続的影響が期待されます。
キングヘイローの2000年高松宮記念の価値と戦術的意義
2000年の高松宮記念は11度目のG1挑戦で掴んだ初タイトルであり、距離短縮と進路確保という2つの課題を同時に解決した点に価値があります。
道中は中団外で脚を温存し、3〜4角で外へ持ち出しながら加速、直線で狭いスペースを割って伸び切るという『減速しない直線入り』を完璧に実装しました。
相手関係は内外の強豪が揃い、ラップは国際標準の一貫ペース。
それをコース取りと反応速度でねじ伏せた内容は、単なる展開利ではなく、地力の証明にほかなりません。
適性転換の決定打として、キャリアの総合価値を一段押し上げた歴史的な一勝でした。
戦術完成と地力証明がキーワードです。
キングヘイローの配合傾向と短距離・ダート適性の継承
種牡馬としては、牝系側に瞬発の要素を補う配合でスプリントの完成度が上がり、米国型パワー血統を重ねるとダートでの推進力が強化されます。
肩の可動域と体幹の強さを伝えるため、追ってから止まらないフットワークが産駒の共通項となり、短距離〜マイルでの『もう一伸び』が作りやすくなります。
また母父としても背中の柔らかさを供給し、直線での持続を底上げ。
まとめると、配合バランスと適応力を高い水準で両立しやすいのが特徴で、世代を超えて短距離戦の質の底上げに寄与しています。
キングヘイローの東京スポーツ杯3歳Sレコードの意味と評価
東京スポーツ杯3歳Sのレコード勝ちは、若駒の段階で『速い流れを自分で作って自分で押し切る』という能力を可視化した出来事でした。
ペースは中盤から締まり、直線でも加速を継続する一貫ラップ。
道中のロスを最小化し、直線入口で減速しないフォームを実戦の舞台で示せたことは、その後の短距離〜マイル適性の根拠となりました。
また、3歳秋以降の成長局面においても、直線での再加速が効く走法は安定して再現され、秋のG1戦線での上位争いに繋がっています。
早期からの高指標は過剰評価に繋がりやすい一方、キングヘイローは適性の見直しと戦術の最適化で価値を積み増し、最終的にスプリントG1制覇という結果に結びつけました。
キーワードは一貫ラップ、フォームの再現性、成長の持続です。
キングヘイローの脚質転換プロセスとローテ最適化
クラシック期は中距離の先行型として質を示しましたが、古馬で短距離〜マイルへターゲットを絞る過程で、調教とローテの設計が再定義されました。
週半ばの終い重点で瞬発を磨きつつ、実戦は『道中は我慢、直線はロングスパート』の再現に全振り。
前哨戦で基礎速度を引き上げ、ターゲットの2〜3走前からビルドアップすることで、シーズンを通じてパフォーマンスの下限を高く維持しました。
この最適化が、1999年の短距離・マイルG1での上位好走、2000年の高松宮記念制覇へと繋がっています。
適性の見立てを更新し続けた柔軟性と、失敗からの学習速度がキングヘイローの大きな武器でした。
要点は適性転換、調整設計、修正力です。
キングヘイローのよくある質問(FAQ)
Q. 主な勝ち鞍は?
A. 高松宮記念(G1)のほか、中山記念(G2)、東京新聞杯(G3)、東京スポーツ杯3歳S(G3)を制しています。
クラシック期は皐月賞2着、日本ダービーは不運でしたが、その後の適性転換でタイトル価値を高めました。
Q. ベストの適性距離は?
A. ベストは1200〜1600という距離適性で、ミドル〜ハイの一貫ラップに強みがあります。
直線入口の減速が小さいコースで最大値を発揮し、良〜稍重で再現性が高いのが特徴です。
Q. 代表的なライバルは?
A. 同世代ではスペシャルウィーク、セイウンスカイ、古馬ではグラスワンダー、のちにはテイエムオペラオーが代表格です。
それぞれの個性に対処する過程でライバル関係が競走内容の質を引き上げ、戦術の幅が広がりました。
キングヘイローの成績表
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/05 | 京都 | 3歳新馬 | 2 | 1 | 福永祐一 | 芝1600m | 稍重 | 1:37.0 |
| 1997/10/25 | 京都 | 黄菊賞(500万下) | 3 | 1 | 福永祐一 | 芝1800m | 良 | 1:48.8 |
| 1997/11/15 | 東京 | 東京スポーツ杯3歳S(G3) | 1 | 1 | 福永祐一 | 芝1800m | 良 | 1:48.0 |
| 1997/12/20 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S(G3) | 1 | 2 | 福永祐一 | 芝2000m | 良 | 2:04.0 |
| 1998/03/08 | 中山 | 弥生賞(G2) | 1 | 3 | 福永祐一 | 芝2000m | 良 | 2:02.6 |
| 1998/04/19 | 中山 | 皐月賞(G1) | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝2000m | 良 | 2:01.4 |
| 1998/06/07 | 東京 | 日本ダービー(G1) | 2 | 14 | 福永祐一 | 芝2400m | 稍重 | 2:28.4 |
| 1998/09/20 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 芝2000m | 良 | 2:02.2 |
| 1998/10/18 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 2 | 2 | 福永祐一 | 芝2200m | 稍重 | 2:15.1 |
| 1998/11/08 | 京都 | 菊花賞(G1) | 3 | 5 | 福永祐一 | 芝3000m | 良 | 3:03.9 |
| 1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 10 | 6 | 福永祐一 | 芝2500m | 良 | 2:32.9 |
| 1999/02/07 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 1 | 1 | 柴田善臣 | 芝1600m | 良 | 1:33.5 |
| 1999/03/14 | 中山 | 中山記念(G2) | 1 | 1 | 柴田善臣 | 芝1800m | 良 | 1:47.5 |
| 1999/06/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 2 | 11 | 柴田善臣 | 芝1600m | 良 | 1:35.1 |
| 1999/07/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 5 | 8 | 柴田善臣 | 芝2200m | 良 | 2:14.6 |
| 1999/10/10 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 2 | 5 | 横山典弘 | 芝1800m | 良 | 1:46.2 |
| 1999/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 9 | 7 | 柴田善臣 | 芝2000m | 良 | 1:58.6 |
| 1999/11/21 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 | 2 | 福永祐一 | 芝1600m | 良 | 1:33.0 |
| 1999/12/19 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 4 | 3 | 福永祐一 | 芝1200m | 良 | 1:08.4 |
| 2000/02/20 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 1 | 13 | 柴田善臣 | ダ1600m | 良 | 1:37.2 |
| 2000/03/26 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 4 | 1 | 柴田善臣 | 芝1200m | 良 | 1:08.6 |
| 2000/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 3 | 11 | 柴田善臣 | 芝1400m | 良 | 1:22.0 |
| 2000/06/04 | 東京 | 安田記念(G1) | 3 | 3 | 福永祐一 | 芝1600m | 良 | 1:34.1 |
| 2000/10/01 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 6 | 7 | 柴田善臣 | 芝1200m | 稍重 | 1:09.6 |
| 2000/10/28 | 京都 | スワンS(G2) | 3 | 12 | 柴田善臣 | 芝1400m | 良 | 1:21.5 |
| 2000/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 5 | 7 | 柴田善臣 | 芝1600m | 良 | 1:33.2 |
| 2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 9 | 4 | 柴田善臣 | 芝2500m | 良 | 2:34.3 |
キングヘイローのまとめ
名血のシナジーに裏打ちされた基礎性能と、適性転換を成し遂げた柔軟性が融合し、王道路線からスプリントまで横断して高い下限値を示した名馬でした。
失敗を要素分解し、コース取りと仕掛けの精度を磨くことで、11度目の挑戦で高松宮記念を制覇。
引退後は短距離〜ダートの層を厚くし、母父としても直線の『もう一段』を伝えて日本競馬の質的向上に貢献しました。
総合して、適応力と再現性を兼備した指標的存在であり、配合と戦術設計の両面で今なお学ぶ点が多い一頭です。